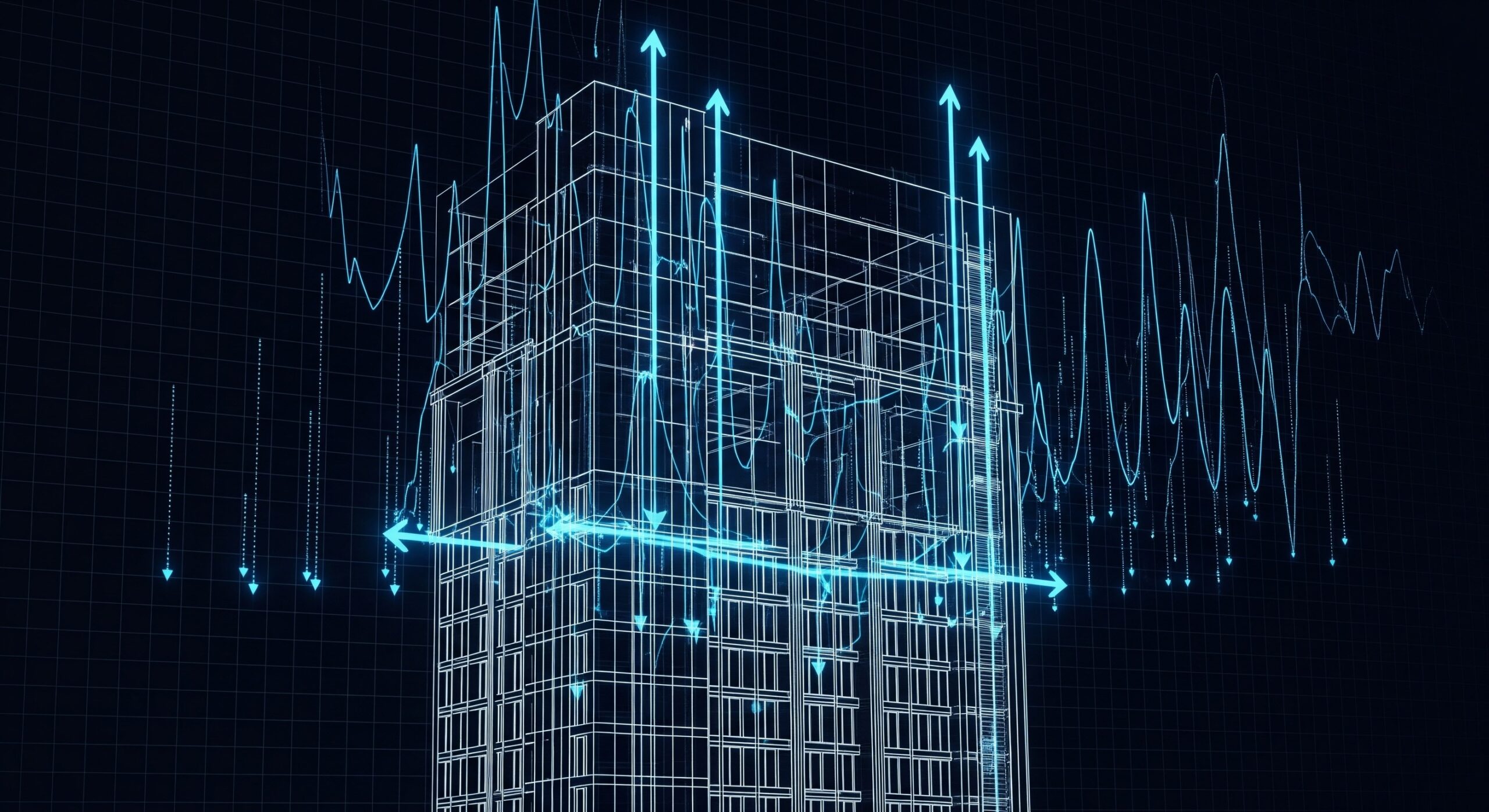『保有水平耐力計算とは』のシリーズになります。
保有水平耐力計算の中では外力分布の設定として1次設計と同様にAi分布を採用するだけでなく、必要保有水平耐力の分布を採用することができます。
今回の記事ではこの2つ方法にどのようなメリットとリスクがあるのかを知って、適切に使い分けられるような内容を書いていきます。
①外力分布とは何か?
まずはそもそも「外力分布」とは何かを見ていきます。
地震の力は建物の高さ方向に均一にかかるわけではありません。一般的に上層階ほど大きな力がかかります。この高さ方向の力の分布パターンを「外力分布」と呼びます。
そこで保有水平耐力計算では、主に2種類の外力分布が用いられます。
- Ai分布:建築基準法で定められている、建物の振動特性(一次固有周期)に応じて力の分布を標準化したものです。最も基本的で広く使われる外力分布です。
- 必要保有水平耐力の分布:偏心率や剛性率の影響も考慮して算出された各階が必要とする耐力(必要保有水平耐力)を、そのまま外力分布として用いる方法です。
Ai分布は建物の固有周期(建物高さと構造種別から算出)と各階の重量分布から算出されるのに対して、必要保有水平耐力の分布は各階の剛性バランスや偏心状態を踏まえているため、実際の地震時における建物の揺れ方や応答をより忠実に反映した外力分布になる可能性が高まります。
②どのような時に必要保有水平耐力分布を採用するのか?
外力分布の採用について法的な扱いとしては、平成19年国土交通省告示第594号第4に明示されています。特別な調査研究による採用を除いた一般的な条件は以下になります。
イ Aiを用いて増分解析を行い,架構の崩壊状態が全体崩壊形となることが確かめられた場合
ロ Aiを用いて増分解析を行い,架構の崩壊状態が部分崩壊形又は局部崩壊形となることが確かめられ,かつ,崩壊する階(部分崩壊形にあっては水平力に対して不安定になる階を,局部崩壊形にあっては局部的な崩壊が生じる階をいう。)以外の階である建築物の部分(崩壊する階が架構の中間である場合にあっては,当該階の上方及び下方のそれぞれの建築物の部分)について,すべてのはり(当該建築物の部分の最上階のはり及び最下階の床版に接するはりを除く。)の端部並びに最上階の柱頭及び最下階の柱脚に塑性ヒンジが生じることその他の要因によって当該建築物の部分の全体が水平力に対して耐えられなくなる状態となることが確かめられた場合
簡単に言うと、建物全体が崩壊する「全体崩壊形」であることが基本ですが、「部分崩壊形」や「局部崩壊形」であっても特定の条件を満たせば採用可能、ということです。
各階のDs値・Fes値がすべて同じ数値であれば、Ai分布と必要保有水平耐力分布は結果的に同じ形になります。
階によってDs・Fesが異なる場合に必要保有水平耐力分布を採用する意味が出てきます。
そのような場合には全階で保有水平耐力が必要保有水平耐力以上となるためには、全階の中で Ds・Fes の最大値を用いた必要保有水平耐力以上の保有水平耐力を全階で実質確保する必要があり階ごとに Ds・Fesを定めている意味がなくなってしまいます。
以上のことより、崩壊形が条件を満たしつつ、階ごとにDs・Fesが異なる場合に採用されます。
③必要保有水平耐力分布が危険側になるケースとは?
必要保有水平耐力分布の採用に合理性があることがわかりましたが、場合によっては危険側の評価となる(安全性を過大評価してしまう)ことがあります。具体的な場面を把握しておきましょう。
・剛性や耐力に差がある場合
例えば、下層階にRC造(鉄筋コンクリート造)、上層階に鉄骨造を採用した混構造建築物を考えてみましょう。このような建物では、下層階の必要耐力が大きく、上層階の必要耐力が相対的に小さくなりがちです。
上層階への外力が過小評価され、実際の地震時には上層階での変形や損傷が予想以上に大きくなる可能性があります。特に下層階が固く、上層階が柔らかい構造では注意が必要です。
また、ピロティ構造(1階が駐車場などで柱だけになっている建物)や、中間階に設備階を設けた建物など、特定の階の剛性・耐力が極端に小さい場合があります。このような建物では、その弱い階の必要保有水平耐力も小さくなります。
弱層への外力が過小評価され、実際の地震時にはその層に変形が集中して層崩壊を引き起こす可能性があります。いわゆる「ソフトストーリー崩壊」と呼ばれる現象です。
・高次モードの影響が大きい高層建築物
高層建築物では、建物の揺れ方(振動モード)が複雑になります。基本的な揺れ方(1次モード)だけでなく、S字型やもっと複雑な揺れ方(高次モード)の影響も無視できません。
④安全性を確保するための実務的な対策
これらのリスクを踏まえ、設計では以下のような多角的な検討が重要です。
- 複数の外力分布で検討する 基本ですが最も確実な方法です。Ai分布と必要保有水平耐力分布の両方で検討し、安全側の結果を採用することで、評価の抜け漏れを防ぎます。
- 高度な解析手法を活用する 高層建築物などでは、高次モードを評価できるモーダル解析を行ったり、より現実に近い応答をシミュレーションする時刻歴応答解析を補助的に用いたりして、外力分布の妥当性を検証することが望ましいです。
- 弱層の耐力を割り増して設計する 弱層の存在が明らかな場合は、意図的にその階の耐力を割り増して設計し、層崩壊のリスクを低減させるという基本的な配慮が不可欠です。
最終的には、建物の特性を踏まえた判断が重要です。マニュアル的に捉えるだけでなく、建物ごとの特性を理解した上での適切な判断をしていきましょう。
まとめ
今回の記事では、保有水平耐力計算における2つの主要な外力分布(Ai分布・必要保有水平耐力分布)の使い分けとその注意点について解説しました。 一貫計算ソフトの設定一つで切り替えられますが、その選択には設計者の明確な意図が必要です。
- 使い分けのメリット: 階によって構造特性(Ds値・Fes値)が異なる場合、「必要保有水平耐力分布」を採用することで、過剰な設計を避け、各階の実状に合った合理的な断面算定が可能になります。
- 採用の条件: どんな建物でも使えるわけではなく、原則として「全体崩壊形」であることが求められます。部分崩壊形となる場合でも、その他の階が健全に降伏するなどの厳しい条件をクリアする必要があります。
- 潜むリスク: 剛性に極端な差がある混構造やピロティ形式の場合、「必要保有水平耐力分布」を採用すると、弱い層への外力が過小評価され、危険側の設計(ソフトストーリー崩壊のリスク)になる恐れがあります。
迷ったときは「Ai分布」と「必要保有水平耐力分布」の両方で解析し、それぞれの結果を比較・検証する姿勢が、設計の安全性を担保します。
【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ
この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!
問題1 保有水平耐力計算において「必要保有水平耐力の分布」を外力分布として採用するためには、原則として増分解析の結果、架構が「全体崩壊形」となることが条件であるが、部分崩壊形であっても、崩壊する階以外の部分で塑性ヒンジが生じるなど、告示で定められた特定の条件を満たせば採用が可能である。
解答1:〇 解説: 基本原則は、エネルギー吸収能力の高い「全体崩壊形」であることです。しかし、告示(平19国交告第594号)により、部分崩壊形や局部崩壊形であっても、崩壊していない他の階でも梁端部などに塑性ヒンジが発生し、建物全体として水平力に耐えられなくなる状態が確認できれば、採用が認められています。
問題2 建物全体の各階における構造特性係数(Ds値)や形状係数(Fes値)がすべて同じ数値である場合、「必要保有水平耐力の分布」を採用すると、「Ai分布」を採用した場合と比較して、外力分布の形状が大きく変わり、より経済的な設計が可能になる。
解答2:× 解説: Ds値やFes値が全階で同じであれば、必要保有水平耐力(Qun)の分布形状は、基本的にAi分布の形状と相似形(ほぼ同じ)になります。 「必要保有水平耐力の分布」を採用するメリットが最大限に発揮されるのは、階によってDs値が異なり、Ai分布のままでは最も厳しい階の係数に全体が引っ張られて不経済になってしまうようなケースです。
問題3 ピロティ形式(1階が柔らかい)や、下層がRC造で上層が鉄骨造といった剛性・耐力に極端な差がある建物において、「必要保有水平耐力の分布」を採用することは、各階の必要耐力を忠実に反映しているため、Ai分布を用いるよりも常に安全側の設計となる。
解答3:× 解説: 剛性や耐力が低い層(弱層)は、計算上の「必要保有水平耐力」も小さくなります。これをそのまま外力分布として採用すると、その弱層にかかる地震力が小さく見積もられてしまう恐れがあります。 実際の地震では弱層に変形が集中しやすいため、こうしたケースではAi分布(より一般的な分布)を採用するか、弱層の耐力を意図的に割り増すなどの配慮が必要となり、必要保有水平耐力分布が必ずしも安全側とは限りません。