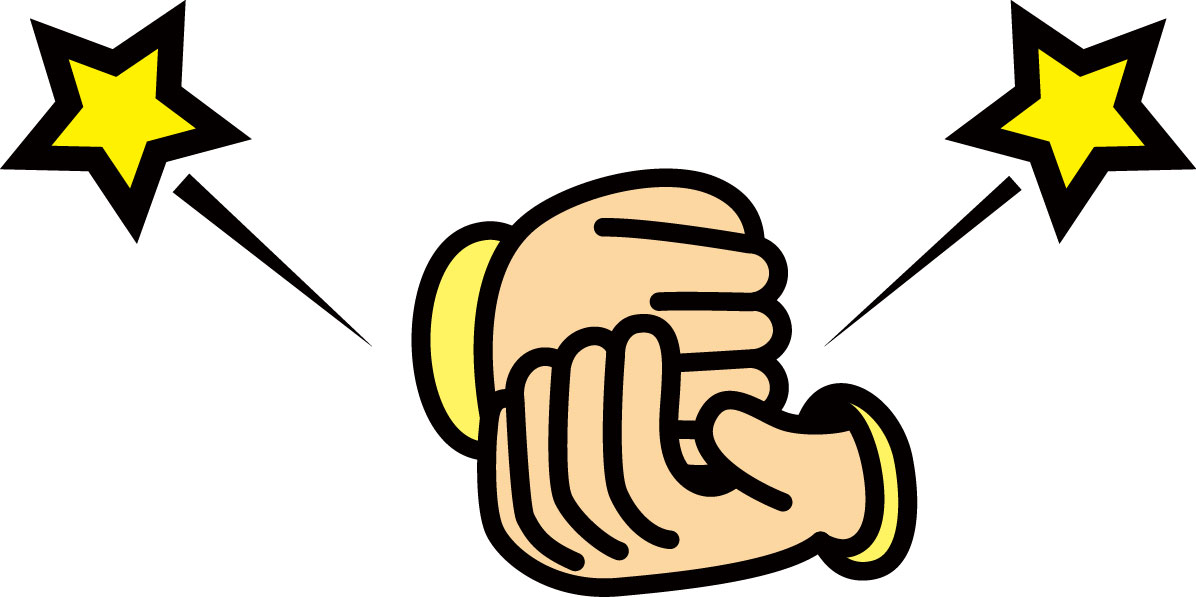日々、無意識なものも含めて無数の判断をしています。 構造設計の場面でも「決める」機会はたくさんありますが、その一つひとつを「自分で決めている」という感覚を持てているでしょうか?
「誰かに言われたから」「なんとなく周りに合わせて」と流されるのではなく、情報を集め、人に相談した上で、最後は「自分自身が納得して決める」という感覚。 この感覚を持っているか、それとも「なんとなくこなしている」のかで、設計者としての成果や成長、やりがいに大きな差が生まれます。
今回は、仕事の質を劇的に変える「自分で決める」ことの重要性と、そのための具体的な思考法について解説します。
①「やらされ仕事」から抜け出す
1. 「自分で決める」と「好き勝手」は違う
「自分で決める」とは、自分の好き勝手に物事を判断したり、経験の浅い人に「あとはよろしく」と丸投げしたりすることとは全く違うということです。
ここで言う「自分で決める」とは、多くの人に相談し、様々な情報を調べた上で、最終的な意思決定の責任は自分が持つということです。周囲の意見は重要な参考情報ですが、あくまで参考。それらの情報を元に、最後の決断は自分で行う必要があります。
2. なぜか「やらされ仕事」ばかりになる人の共通点
「急な課題が入ってきて、予定通りに進まなくなった」 段取りがうまくいかない人がよく口にする言葉ですが、心当たりはないでしょうか? この言葉を違和感なく使ってしまう人は、自分で決めずに「周りの流れ」に任せてしまっているサインかもしれません。
実際には、本当に予測不能な「急な課題」はほとんどありません。 関係者への事前の働きかけや、プロジェクト全体のスケジュールを確認しておけば、課題が発生する時期や規模はある程度予測できます。未知の要素が多いなら、その分だけ余力を多めに見ておけば対応可能です。
段取りが破綻するのは、自分で状況をコントロールしようと「決断」せず、成り行きに任せているからです。これでは自分のやりたいことをする余地はなくなり、すべてが「やらされ仕事」になってしまいます。
3. 「自分で決める」と成長が加速する理由
同じ経験をしても成長に差が生まれるのは、まさにこの「自分で決めたか」どうかの違いです。
特に若手の頃は、「〇〇さんに言われたので、こうしました」と言いたくなる気持ちも分かります。しかし、この言葉は「自分には責任がない」と主張しているように聞こえ、「言われたことをやっているだけで、何も考えていない人」という評価につながりかねません。これは、判断を間違えること以上に信頼を失うことにつながります。
自分で決めて挑戦した失敗であれば、周囲は「何が違ったのか」を教え、力を貸してくれます。 成功した時の充実感も、失敗から学び次善策を考える行動力も、すべては「自分で決めた」という当事者意識から生まれます。失敗を単なるミスではなく、成功までの「過程」に変える力が、ここにはあります。
②「決断」するための具体的な思考法
では、どうすれば「自分で決める」ことができるようになるのでしょうか。その鍵は、思考を「言葉化」し、「判断」と「決断」、そして「検討」と「確認」を明確に区別することにあります。
1. まずは自分の思考を「言葉」にする
問題意識を持つだけでは、人の行動や思考はなかなか変わりません。具体的な変化のためには、目指す方向性をきちんと言葉で定義し、固定しておく必要があります。
人間は誰でも、目的を明確に固定しないと、無意識のうちに自分の関心があるものに逸れてしまうものです。それを前提に、「言葉にして目的を固定する」ことが有効になります。
言葉にしておけば、無意識のうちにその言葉に沿って思考するようになり、道に迷いにくくなります。また、うまくいかなかった場合にも「言葉にした定義のどこを改善すれば良いか」を客観的に考えることができるようになります。
2. 「判断」と「決断」、そして「検討」と「確認」を区別する
思考の指針として、まず「判断」と「決断」という2つの言葉を明確に区別することです。
- 判断:情報を十分に検討し、論理的に正しい答えを導き出すプロセス。
- 決断:判断の結果を踏まえて、どの道を選ぶかを(意志を持って)決める行為。
「決断」は立場のある人や責任者がするもの、というイメージが強いかもしれません。しかし、「判断」は誰もができることだし、誰でもやるべきことです。「決断」を委ねる前には自分の「判断」を伝える必要があります。「決断」を委ねているつもりが「判断」ごと丸投げしていることになっていないでしょうか?
そして、この「判断」の質とスピードを上げる鍵が、「検討」と「確認」の区別にあります。 自分なりの仮説(あたり)を持たずに作業を始めると、それは五月雨式の「検討」となり、非常に時間がかかります。一方で、「こうなるはずだ」という仮説を持ち、「これを確かめる」という目的意識で臨めば、作業はスピーディーな「確認」に変わります。
構造設計における多くの業務は、過去の知見や類似物件の経験から仮説を立て、この「確認作業」に落とし込めます。
③構造設計者が陥る罠:「決断」を電算に委ねてはいけない
この思考法は、構造計算プログラム(電算)を多用する構造設計者にとって、特に重要です。
電算プログラムがやってくれるのは、あくまで「判断」の補助、つまり高速な「確認作業」です。入力された条件に基づき、膨大な計算を行って合理的な答えを導き出してくれます。しかし、その結果をどう採用し、最終的にどのような設計にするのかを「決断」するのは、電算ではなく設計者自身です。
電算の出力結果を鵜呑みにし、そのまま「決断」までさせてしまう。それは、設計者が電算に「使われている」状態に他なりません。
マニュアルや基準書を読み込み、プログラムの特性を理解し、「決断」できるだけの十分な「判断」材料を揃える。この準備を徹底することで、電算は最高のパートナーになります。
「判断」は電算に任せても良い。しかし、最後の「決断」は必ず自分で行う。 この区別を意識するだけで、設計者としての仕事への向き合い方は大きく変わるはずです。
はじめは小さなことからでも構いません。「自分で決める」という感覚を常に意識して、仕事の質と自身の成長を加速させていきましょう。
参考:余力をどのように設定する?過剰思考になっていない?
参考:構造計算プログラムの結果が正しいとは限らない
まとめ:設計者の価値は、主体的な「決断」から生まれる
最後に、本記事の要点を振り返ります。
- 「やらされ仕事」から脱却する: 「〇〇さんに言われたから」ではなく、すべての業務に当事者意識を持ち、自ら決める姿勢が成長の鍵です。
- 思考を4つに区別する: 成果を出すためには、「判断」と「決断」、そして「検討」と「確認」を明確に使い分ける必要があります。
- 仮説を持って「確認」する: 多くの「検討」は、仮説を持つことでスピーディーな「確認」作業に変えられます。
- 電算は「判断」のパートナー: 電算はあくまで高速な「確認」と「判断」を助けるツールです。最後の「決断」は、必ず設計者自身が行わなければなりません。
AI(電算)がより高度な「判断」を担うこれからの時代、設計者の真の価値は、背景を深く理解し、主体的な「決断」にこそあります。
まずは小さな業務からでも、「これは確認か、検討か?」「自分の判断は何か?」と自問することから始めてみませんか。そこから行動や成果が大きくかわります。