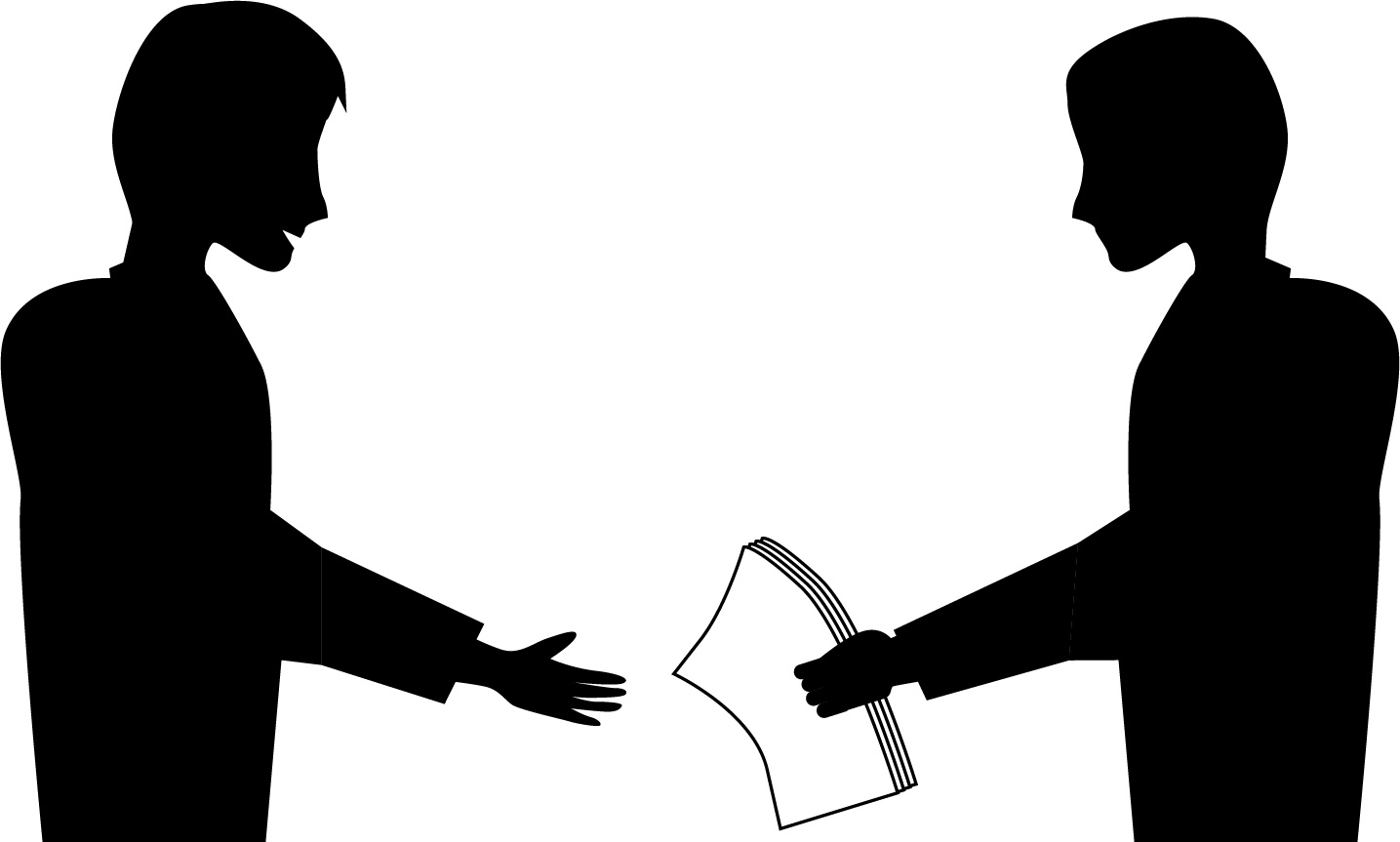過去の記事では、地震被害を受けた法改正の歴史と、それを踏まえた技術的な視点について書いてきました。今回は同じく法改正をテーマに、少し視点を変えて、制定された「意図」と、実際の「運用」の間に横たわる課題について考えてみたいと思います。
①増え続ける「準拠規定」というジレンマ
現在の建築基準法は、前身ともいえる市街地建築物法(1919年制定)を含めると、約100年の間に、変貌を遂げながら現在まで運営されてきました。その間、改正のたびに準拠すべき規定は増え続けています。
私自身、構造設計を実務として始めて10年余りですが、その短い期間でさえ規定は増え続けています。
規定を拠り所に設計荷重やクライテリアを設定するところから始まり、構造体のモデル化から応力計算、部材の検定方法と、その適否の判断にいたるまで細部まで規定され、それに適合させることが義務付けられています。
これだけを聞くと、構造設計者の判断は基準と照らし合わせるだけなのかと思われてしまいそうな印象を受けます。また、日々設計の多様化や技術革新などの変化が起こっていく中で、あまりに規定に縛られすぎると、それらの変化を柔軟に取り入れることも困難になります。
多くの規定があることを当たり前と感じてしまう世代ですが、構造設計の礎を築いてこられた先達からすれば、現在の状況は、設計の自由度を奪い、設計者が本来考えるべき領域を狭めていると感じられるのかもしれません。
②「基準適合」は設計の本質ではない
本来、建築の性能は発注者と設計者が対話を通じて決めていくべきものです。もちろん、建築は公共に影響を与えるため最低限のルールは必要ですが、構造安全性を「どう」確保するかは、本来、発注者と設計者が決められるはずです。
それを実現するのが、「仕様設計(規定への適合)」から「性能設計(目指す性能から逆算する設計)」への移行です。
しかし、多くの設計者がその重要性を理解しつつも、性能設計が普及しない。その理由は、法や基準以外の「言葉」で安全性を説明し、発注者と合意形成する難しさにあるのではないでしょうか。
基準適合に慣れきってしまうと、性能から考えるという発想すら生まれなくなり、発注者に説明するための「言葉」を磨く努力から、ますます遠ざかってしまいます。
③意図とは逆に行ってしまった基準運用
建築基準法を制定した当初は技術もない中でたくさん建物を作る必要があったため厳格に基準を設定したという大きな社会背景があります。
基準法を作った側の意識としても徐々に緩和していくつもりだったそうですがそうはなりませんでした。
より最近の例を挙げると、2000年の法改正は、10年後には見直す前提の内容でしたが、実際には何の改正も行われませんでした。
これには、基準を作る側だけでなく、私たち設計者側にも課題があります。いつしか設計者の思考が「規定ありき」となり、むしろ自ら細かな数値を求めるようになってしまいました。
例えばDs値については幅を持たせた設定していたつもりが、明確に決めてくれないと使用できないといった意見が多く出たので厳格化することになったようです。
ほかにも、適判制度が本来の趣旨から外れてしまっている例もあります。当初は「2人の検査官が2時間で審査する」ことを前提に制度設計されていたものが、今や適判機関が国からの査定を気にするあまり、設計の本質的でない些末な部分のチェックに多大な時間を費やしているのが現実です。
しかし、この点については設計者側の力量の低下や設計期間の短期化などで大量の不整合などの品質低下も関係しています。
法や基準といった形になっているものだけでなく、背後の思いを引き継いでいくことが今後設計をしていく上では重要なことです。
どんな仕組みも完璧に作った人の意図通りに、永遠に運用されていくということはありません。またそれに対して、問題指摘をすることは簡単だけれども、それでは何も変わりません。
この2つは世の中の原理としては普遍なことだと思っています。
だからこそ、これまでの構造設計界をきちんと受け止めて今後もできるだけ広めていく中で、少しでも構造設計という役割を魅力的なものにしていきたいと思います。
まとめ:基準の背後にある「思い」を引き継ぐために
法や基準という形になったものだけを追うのではなく、その背後にある「思い」や「制定意図」を引き継いでいくことが、これからの設計者には不可欠です。
どんな仕組みも、作った人の意図通りに永遠に運用されることはありません。そして、それに対して問題指摘をするだけでは、何も変わりません。この2点は、世の中の普遍的な原理だと思います。
だからこそ、これまでの構造設計界が抱える課題を真正面から受け止め、その上で構造設計という役割の魅力を少しでも多くの人に伝えていくことが重要になります。