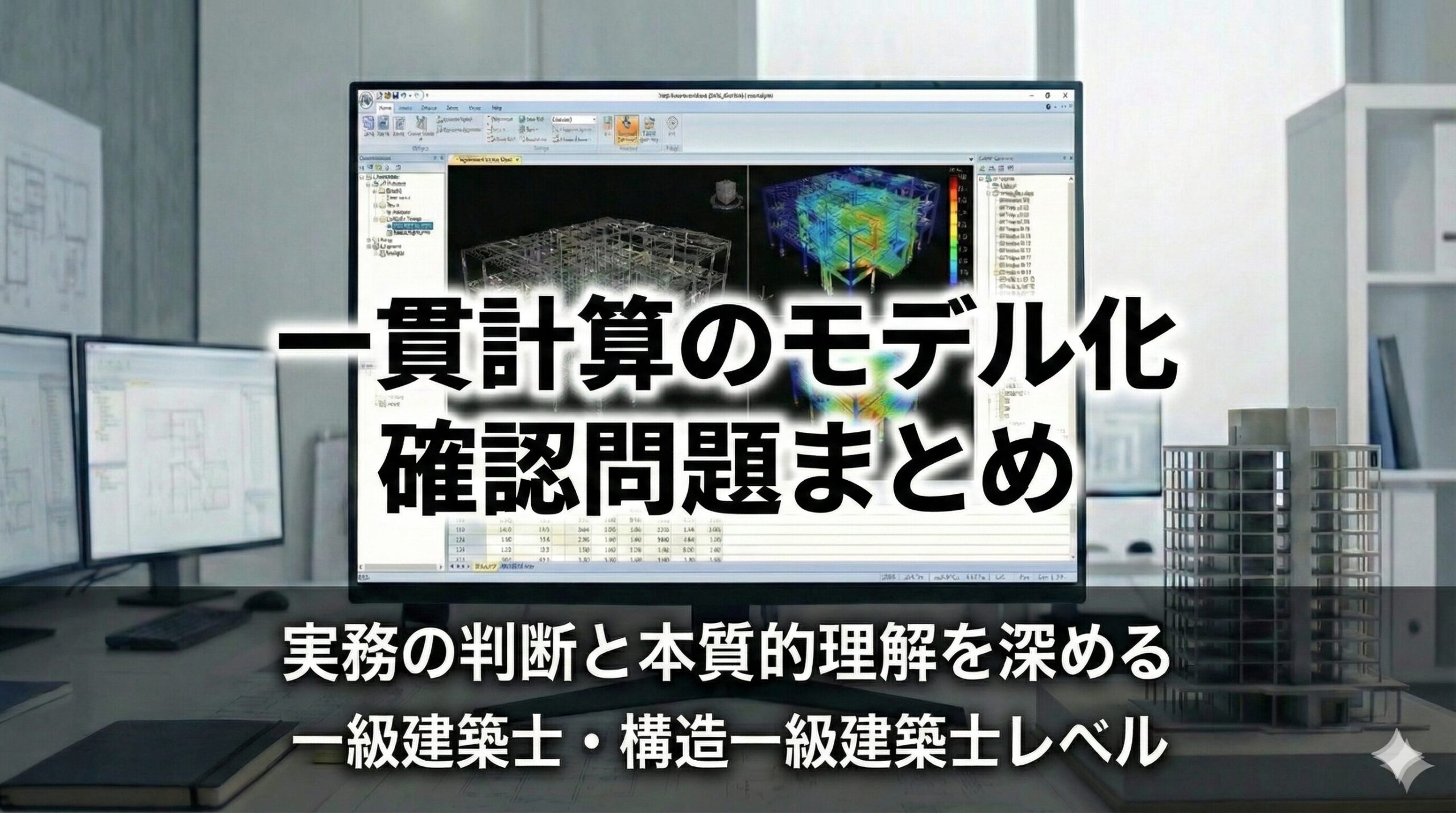一貫計算のモデル化に関する記事での確認問題のまとめになります。問題のレベルとしては一級建築士と構造一級建築士の間くらいだと思いますが、実務の判断をベースに本質的な部分を深められるようにしています。
解答できなかった部分を改めて記事に目を通してみてください。
①モデル化シリーズ
1. 線材モデル:すべての基本となる「骨格」への置き換え
問題1 構造設計における「モデル化」の主たる目的は、実際の建物と全く同じ挙動を再現するために、細かい部材や開口などの全ての条件を可能な限り詳細に入力し、現実を完全にコピーすることである。
解答1 :× 解説: モデル化の本質は「簡略化」です。影響の小さい雑多な条件まで全て盛り込むと、計算が複雑になりすぎて本質的な挙動やエラーの原因を見失うことになります。重要な要素を抽出し、検証可能な形に単純化することが正しいモデル化です。
問題2 線材モデルを用いた一貫計算において、柱と梁が交差する部分は部材のボリューム(厚み)があるため、接合部付近を変形しない領域として扱う「剛域(ごういき)」を設定して解析を行うのが一般的である。
解答2 :〇 解説: 線材モデルは「線」で計算しますが、実際の部材には幅や成(せい)があります。特に柱と梁が重なる接合部は極めて剛性が高いため、計算上変形しないとみなす「剛域」を設定し、より実態に近い応力状態を再現します。
問題3 最新の一貫計算ソフトで作成された3Dモデルは、形状が視覚的に正確であれば構造モデルとしても最適化されているため、設計者はそのモデルの結果のみを信頼すればよく、簡易モデル等での検証や複数のモデル比較を行う必要はない。
解答3 :× 解説: 誤りです。パッと見の形状が正しくても、剛性の評価や境界条件の設定が適切とは限りません。一つのモデルの結果を鵜呑みにせず、手計算レベルの簡易モデルで妥当性をチェックしたり、境界条件を変えた複数のモデルで感度解析を行ったりして、安全性の「幅」を確認する姿勢が重要です。
2. 剛床仮定:なぜ剛床仮定を採用するのか
問題1 剛床仮定とは、各階の床が極めて硬く、水平力に対して一体となって移動(平行移動や回転)するものの、床自体は伸縮やせん断変形を起こさないものとして扱うモデル化のことである。
解答1:〇 解説: 剛床仮定では、同じフロアにある節点同士の距離は変わらない(=床が変形しない)とみなします。これにより、全ての節点が同じように水平移動・回転移動するモデルとなります。
問題2 一貫計算ソフトなどで剛床仮定を採用する主なメリットの一つは、各節点の水平変位を個別に計算する必要がなくなり、層ごとの代表値として扱えるため、マトリックス変位法における未知数が減少し、計算負荷が軽減される点にある。
解答2:〇 解説: 剛床仮定を用いることで、節点ごとの水平変位を独立した未知数として扱う必要がなくなり、各階の水平変位などに集約できます。これにより連立方程式の数が大幅に減り、計算効率が向上します。
問題3 山形ラーメンのような勾配屋根の架構を設計する場合、屋根面には水平構面としての剛性が期待できるため、スラスト(開く力)を抑え込む意味でも、基本的には「剛床仮定」として計算を行うのが望ましい。
解答3:× 解説: 山形ラーメンでは、屋根の自重等により「スラスト(脚元が開こうとする力、梁が伸びようとする力)」が発生します。 ここで剛床仮定(=伸び縮みしない)を適用してしまうと、この「開こうとする変形」が計算上で拘束されてしまい、実際には発生するはずのスラストや梁の軸力が正しく算出されなくなります。このような架構では必ず「非剛床(剛床解除)」として、水平変位や軸力を正しく評価する必要があります。
3. 支点条件:建物の「足元」をどう仮定するのか
問題1 構造計算における支点のモデル化は、「固定」「ピン」「ローラー」の3種類のみで表現され、それらの中間的な状態(回転ばねや水平ばね等)を考慮することは、計算が複雑になるため一般的には行われない。
解答1 :× 解説: 基本は3種類ですが、実務ではその間を埋めるモデル化も重要です。例えば、基礎の根入れ深さが異なる場合の「水平ばね」による剛性調整や、露出柱脚の「回転ばね」、杭の鉛直挙動を表す「鉛直ばね」など、状況に応じてこれらを使い分けることで、より実態に近い応力解析が可能になります。
問題2 一貫計算において一般的に最下層の支点条件を「ピン支点(回転拘束なし)」とする背景には、地盤のばね定数を正確に設定することが困難であることや、基礎梁が十分な剛性と耐力を持ち、上部構造からの力を適切に分配・処理できるという前提がある。
解答2 :〇 解説: 地盤の性状を完全に把握するのは難しいため、告示や解説書においても、基礎梁等が弾性範囲内(剛強)であれば、支点を固定しない「ピン」として扱うことが一般的とされています。逆に言えば、基礎梁が降伏してしまうとこの前提が崩れるため注意が必要です。
問題3 耐震壁の脚部など、地震時に大きな引抜力が発生する箇所において、計算上で杭の引抜耐力を超える(浮き上がる)ような場合であっても、基礎梁の剛性が高ければ力は再配分されるため、支点条件を「ピン」としたままの検討だけで十分であり、浮き上がり(ばね)を考慮した検証は不要である。
解答3 :× 解説: 引抜力が大きく支点が浮き上がる可能性がある場合は、ピン支点(浮き上がらない仮定)だけの検討では不十分です。支点が浮き上がると、その負担分が周辺の杭や基礎梁に再配分され、応力が大きく変化します。そのため、浮き上がりを考慮したモデル(鉛直ばねの解除など)でも解析を行い、両方のケースで安全性を確認する必要があります。
4. 剛性評価:絶対値よりも「相対的なバランス」が重要な理由
問題1 一次設計(許容応力度計算)において、RC部材の剛性は原則としてひび割れによる剛性低下を考慮しない「弾性剛性」で評価するが、これによって耐震壁の剛性が高く評価されると、並列する柱や梁に流れる力が実態よりも小さく計算され、架構部材にとっては危険側の評価になることがある。
解答1:〇 解説: 一次設計では弾性剛性が基本ですが、RCの耐震壁は実際にはひび割れ等で剛性が低下しやすい部材です。計算上で壁を「硬いまま」評価すると、地震力の大半を壁が負担してしまい、本来もっと力を負担するはずの柱や梁(架構)への応力が小さく算出されてしまう恐れがあります。そのため、壁量が多い場合などの応力割増規定が存在します。
問題2 柱や梁のモデル化において設定する「剛域(接合部などの変形しない領域)」の長さは、部材の水平剛性に影響を与えるが、その影響度は部材長さの「1乗」に比例するため、剛域の設定を多少誤っても全体への影響は軽微である。
解答2:× 解説: 部材の水平剛性は、部材長さの「3乗」に反比例します。 剛域を長く設定すると、変形する部分(内法長さ)が短くなるため、剛性は急激に高くなります。剛域の設定ミスは、3乗で効いてくるため、応力や変形に多大な影響を与える「感度の高い」パラメータです。
問題3 応力解析において、全部材の剛性を実態よりも一律に「2倍」の硬さで過大評価してモデル化した場合、部材間の剛性比(バランス)が変わらなければ「応力分布」も大きく変わらないため、建物の「変形量(層間変形角)」の確認においても同様に正しい結果が得られると考えてよい。
解答3:× 解説: 確かに剛性比(バランス)が変わらなければ、力の分配(応力図)は大きく変わりません。しかし、「変形量」は剛性の絶対値に依存します。 剛性を一律に2倍(硬く)評価してしまうと、計算上の変形量は実態の半分しか出ません。これでは層間変形角などの検討において、実際にはもっと揺れるのに「変形が小さい」と誤認する危険側の検討となってしまいます。
5. 柱梁接合部:地震に耐えるための「要」、その歴史とモデル化
問題1 一般的な一貫計算プログラムにおいて、柱梁接合部を「剛域(変形しない領域)」としてモデル化する理由の一つは、接合部の変形を無視することで柱や梁などの部材に生じる応力が小さく計算され、経済的な(断面を小さくできる)設計が可能になるためである。
解答1 :× 解説: 接合部を「剛(変形しない)」と仮定すると、地震などによる建物の変形をすべて柱や梁が負担することになります。その結果、柱や梁に生じる応力は「大きめ」に計算される傾向にあります。これは、部材断面が大きくなりやすいため経済的とは言えませんが、構造設計としては「安全側」の評価になるため、このモデル化が一般的に採用されています。
問題2 RC造の柱梁接合部の検討において、接合部パネルの「せん断耐力」を計算上向上させるためには、接合部内に入れるフープ筋(帯筋)の量を増やすことが最も直接的で効果的な対策である。
解答2 :× 解説: ここは勘違いしやすいポイントです。現在の耐力式(靭性指針など)において、接合部のせん断耐力は主に「コンクリート強度」「接合部の形状(体積)」「直交梁の有無」などで決まります。 フープ筋には0.2%や0.3%といった「最小鉄筋量」の規定はあり、拘束効果として必須ですが、計算式上はフープ筋を増やしてもせん断耐力の数値自体は上がりません。耐力が不足する場合は、コンクリート強度を上げるか、柱断面を大きくする等の対策が必要です。
問題3 1995年の阪神・淡路大震災では、鉄骨造の梁端部の溶接作業用に設けられた「スカラップ(溶接孔)」に応力が集中し、そこを起点とした脆性破壊が多発したため、現在ではスカラップを設けない「ノンスカラップ工法」が標準となっている。
解答3 :〇 解説: かつては現場溶接の作業性を良くするためにスカラップ(切り欠き)を設けていましたが、震災時にそこが破壊の弱点(起点)となることが判明しました。その教訓から、現在は応力集中を避けるためにスカラップを設けない「ノンスカラップ工法」とし、完全溶込み溶接を行うことが一般的です。
6. 断面算定:解析結果を「正しく翻訳」する最終工程
問題1 構造計算における断面算定位置(応力を採用する位置)は、建築基準法および関連告示によって「長期荷重時は節点位置、短期荷重時は部材面位置としなければならない」と明確に義務付けられている。
解答1:× 解説: 建築基準法などの法令には、断面算定位置に関する明確な規定はありません。現在の一般的な手法(長期=節点、短期=フェイス)は、日本建築学会のRC規準などの工学的知見や慣例に基づいた「工学的判断」によるものです。法令で決まっていないからこそ、設計者がその根拠を理解しておく必要があります。
問題2 一般的な一貫計算プログラムのデフォルト設定や多くの設計実務において、地震時などの「短期荷重」に対する断面算定位置は、部材の接合部(節点)ではなく、柱面や梁面(フェイス位置)の応力を採用するのが一般的である。
解答2:〇 解説: 地震時などの大きな力がかかる短期荷重時は、部材端部が塑性化(降伏)することを考慮し、実際の部材の危険断面となる「柱面・梁面(フェイス)」の位置で評価するのが一般的です。一方、長期荷重時は部材全体の状態を代表させる意味で「節点位置」を採用することが多いです。
問題3 大きな袖壁が取り付く梁の検討において、袖壁の影響で剛性が高くなり計算上の応力が大きくなった場合、安全側(保守的)な設計とするためには、袖壁の存在による剛域を考慮せず、最も応力が大きい「節点位置」での応力を採用して断面算定を行うのが、構造設計として最も合理的で推奨される方法である。
解答3:× 解説: 袖壁等の影響で剛性が上がると、節点位置の応力は非常に大きくなります。これをそのまま採用すると、過剰な鉄筋量が必要になるなど「非合理的(不経済)」な設計になります。 実際には袖壁と梁が一体化して抵抗するため、危険断面は節点ではなく壁の端部付近になります。実状に合わせて剛域端や壁面位置での応力を採用することが、適切かつ合理的な設計判断となります。
②一貫計算設定シリーズ
骨組みの解析手法|最適な手法を選ぶための基礎知識
問題1 現在、一貫構造計算ソフトなどのコンピュータ解析で主流となっている手法は、節点の移動量や回転角を未知数として連立方程式を解く「マトリックス変位法」である。
解答1 :〇 解説: コンピュータは行列(マトリックス)計算が得意であり、部材の剛性をマトリックス化してシステマチックに解ける「マトリックス変位法」が現在の解析ソフトの標準となっています。
問題2 「D値法」や「固定モーメント法」といった略算法は、コンピュータが発達する前の手計算時代の手法であり、現在の高度な構造設計の実務においては、計算精度の観点から使用する意義はほとんどなくなっている。
解答2 :× 解説: 略算法は、計算結果のオーダー(桁)が合っているか、力の流れがおかしくないかを瞬時に検証(検算)するための強力なツールです。ブラックボックス化しやすいソフトの結果を鵜呑みにしないために、現在でも非常に重要な技術です。
問題3 構造解析において、建物の全体的な挙動(層間変形角や剛性率など)を把握するためには「線材モデル解析」が適しているが、壁式構造の開口周りや鉄骨接合部の詳細な応力集中などを検討したい場合は、構造物をメッシュに分割して解析する「有限要素解析(FEM)」を選択するのが適切である。
解答3 :〇 解説: 解析手法は目的に応じて使い分けます。建物全体の大枠をつかむには計算負荷の軽い「線材モデル」、局所的な詳細検討には情報量の多い「FEM解析」が適しています。
その設定、本当に合ってる? 一貫計算の精度を上げるモデル化の思考法
問題1 現在の一貫計算ソフトは3Dモデルの作成機能が優れており、斜めの壁やR形状の壁なども入力可能であるため、構造解析モデルにおいても可能な限り意匠図の形状を忠実に再現し、細かく部材を分割して入力することが、精度の高い解析を行うための最善の方法である。
解答1:× 解説: 意匠形状を忠実に再現しようとして、無闇に細かく部材を分割すると、不要な節点が増えて計算が不安定になったり、微小部材による局所的な応力集中で本来OKな箇所がNGになったりします。 構造モデルの目的は「力の流れを正しく模擬すること」です。意匠的な見た目よりも、構造的な役割(骨格としての挙動)を適切に単純化して表現することが重要です。
問題2 複雑な形状の建物をモデル化する場合、意匠図の通り芯やレベルだけでは構造的な力の流れを適切に表現できないことがあるため、ソフトに入力する前に、計算用の補助的な通り芯や節点の設定を含めた「計算モデルの設計図」をあらかじめ検討しておくことが、手戻りを防ぎ適切なモデルを作るコツである。
解答2:〇 解説: 複雑な架構では、意匠図通りのグリッドだけでは部材が繋がらなかったり、応力がスムーズに伝わらないことがあります。いきなり入力するのではなく、どこで力を伝えるか、どの節点とどの節点をつなぐかといった戦略(計算モデルの設計図)を事前に練ることで、意図通りの解析モデルを効率的に作成できます。
問題3 中間層(スキップフロア等)の入力機能や、複数の節点を一つにまとめる「節点同一化」などの便利なコマンドを使用した際、モデルの見た目が正しくつながっていれば、応力や剛性、地震力の算定などはソフトが自動的に適切に処理してくれるため、設計者が個別の設定や計算結果の詳細(応力図など)を確認する必要はない。
解答3:× 解説: 「見た目がつながっている」ことと「正しく計算されている」ことは別物です。 中間層であれば地震力の負担方法や剛床解除の設定、節点同一化であれば応力のベクトルや保有耐力の集計方法など、設計者が意図して設定・確認しなければならない項目が多々あります。自動計算任せにせず、応力図を見て不自然な挙動がないか必ず検証する必要があります。
モデルの基本構成と剛性・応力計算条件
問題1 断面2次モーメント(剛性)の計算において、雑壁やスラブの影響を考慮する方法として「精算法」や「略算法」があるが、これらは計算精度の違いこそあれ、最終的な数値のオーダー(桁)が変わるほどの大きな差が出ることはないため、初期設定のまま進めても問題ない。
解答1:× 解説: 計算方法(精算法・略算法の選択)によって、断面2次モーメントの数値は2倍以上のオーダーで変わることがあります。これは応力分布や固有周期に多大な影響を与えるため、「とりあえずデフォルト」ではなく、建物の特性に合わせて初期段階で明確な方針を決めておく必要があります。
問題2 スキップフロアなどをモデル化するために「ダミー層」を設定した場合、その層にある節点は自動的に通常の剛床(水平変位が同一)として扱われる設定になっていることが多いため、柱の中間に節点がある場合などは、意図しない応力発生を防ぐために剛床仮定を解除する等の検討が必要である。
解答2:〇 解説: ダミー層を設定すると、ソフトによってはデフォルトでそのレベルに剛床が設定されます。柱の途中に節点があり、そこが剛床で拘束されると、地震時にその節点が無理やり水平移動させられ、柱に巨大なせん断力が発生するなどのエラー要因となります。実態に合わせて剛床解除(非剛床)の設定が必要です。
問題3 一貫計算における立体解析では、柱の「軸変形(縮み)」を考慮することができるが、これは建物完成後に一括で荷重がかかるモデルであり、施工中に徐々に荷重がかかる現実とは異なる場合があるため、特に高層建物などでは「考慮する」「考慮しない」の両方を比較検討することが望ましい。
解答3:〇 解説: 解析上は「瞬時に全荷重が載る」ため、上層階ほど柱の縮みによる累積変形の影響が出やすくなります。しかし、実際には下層階が固まってから上層階を作るため、解析ほどの変形差が出ないこともあります。このギャップを理解し、安全側になるよう両方のケースを確認するのが実務的な対応です。
二次壁の利用と構造スリットの評価と留意点
問題1 1968年の十勝沖地震で多発したRC造の「短柱破壊(せん断破壊)」は、柱に腰壁や垂れ壁が剛接合されたことで柱の内法高さが短くなり、想定以上に剛性が高まった柱に地震力が集中したことが主な原因であり、これを防ぐために構造スリットによって雑壁と構造体の縁を切る手法が定着した。
解答1 :〇 解説: 雑壁が柱に付くと、柱が短く固くなり(短柱化)、粘りのある曲げ破壊ではなく、脆性的な「せん断破壊」を起こしやすくなります。スリットは、壁と柱を構造的に切り離すことで、柱本来の性能を発揮させるために不可欠です。
問題2 JSCAの『構造スリット設計指針』に準拠した一貫構造計算ソフトでは、梁に取り付く垂れ壁の背が高いほど剛性増大率(φ)は比例して無限に大きくなる設定となっているため、背の高い壁がある場合は手計算で数値を頭打ちにする補正入力が必須である。
解答2 :× 解説: JSCA指針では、壁による剛性増大効果はある程度の高さ(約1m程度)で「頭打ち」になるとされています。現在の一貫計算ソフト(SS7など)のデフォルト設定では、この指針に沿って自動的に頭打ちの処理が行われるため、基本的には手計算による補正は不要です(ただし、計算条件の設定確認は必要です)。
問題3 バルコニーや厨房など防水が必要な箇所に水平スリットを設ける場合、実際には防水立ち上がり(コンクリートパラペット等)が必要となるため、スリット位置を床上(SL+600mm程度)に上げるケースが多い。この場合、構造計算モデルにおいても、その立ち上がり分を考慮して梁の剛性増大や柱の剛域への影響を反映させる必要がある。
解答3 :〇 解説: 計算上は「梁上レベル」でスリットを入れていても、現実の納まりでは防水アゴなどでコンクリートが一体化していることがあります。この「計算と現場のズレ」が、想定外の剛性増加や短柱化を招く恐れがあるため、実際の納まりに合わせてモデル(剛性増大率や剛域)を修正するのが正しい設計です。
「非剛床」設定の基本と3つの留意点
問題1 一貫計算において「剛床仮定」を解除して「非剛床」として扱うべきケースは、金属折板屋根のような面内剛性が低い床の場合に限られ、RC造のスラブであっても大きな吹き抜けがある場合や、トラス梁のような軸変形を考慮すべき架構においては、剛床仮定のままで計算して問題ない。
解答1 :× 解説: 金属屋根などの「剛性が低い」場合だけでなく、吹き抜けによって「床が分断されている」場合や、トラス梁や山形ラーメンのように「部材が伸縮・変形する」ことで架構が成立する場合も、剛床仮定(変形拘束)をしてしまうと正しい応力が出ません。これらの場合も必ず非剛床(剛床解除)とする必要があります。
問題2 非剛床の設定を行った場合、計算上無視されていた梁の「軸方向」や「面外方向」の剛性が考慮されるようになるため、吹き抜けに面した片持ちスラブ付きの梁などでは、そのスラブによる剛性増大率を個別に設定したり、水平ブレースがある場合はその剛性をモデルに入力したりといった剛性評価が重要になる。
解答2 :〇 解説: 剛床仮定では無限大(変形しない)とされていた剛性が、非剛床では具体的な数値として評価されます。そのため、片持ちスラブによる剛性アップや、水平ブレースによる補強効果などは、設計者がパラメータとして入力しないと計算に反映されず、変形や応力が正しく評価されません。
問題3 現在の一貫計算ソフトでは、非剛床とした梁の「面外方向(床と垂直方向)」の応力についても計算されるが、二次設計(保有水平耐力計算など)の段階においても面外方向は「弾性剛性(硬いまま)」で計算されることが多く、現実とは異なる過大な応力が発生していても自動断面算定やワーニングメッセージが出ないことがあるため、設計者が目視で確認する必要がある。
解答3 :〇 解説: ここが技術的な落とし穴です。 主架構が塑性化して剛性が低下している中でも、面外方向だけ弾性解析のまま計算されると、梁端部に現実的ではない巨大な曲げモーメントが発生することがあります。ソフトはこれをエラーとして拾わないことが多いため、設計者が自ら応力図を確認し、配筋で持たせるか、ヒンジ化を許容するか等の工学的判断を下す必要があります。
偏心率~剛床仮定との関係
問題1 構造計算において「剛床仮定」が成立しないエリア(大きな吹き抜けや渡り廊下などの非剛床部分)であっても、一貫計算ソフト上で剛床としてモデル化して偏心率を計算すれば、床の面内変形を考慮した正確な剛心位置と偏心率を算出することが可能である。
解答1 :× 解説: 偏心率の計算自体が「剛床(床が変形しない)」ことを前提としています。非剛床部分を無理やり剛床として計算すると、床の変形(たわみ)が無視され、遠くの壁まで力が瞬時に伝わる計算になってしまうため、架空の剛心位置が算出され、実態とかけ離れた誤った結果となります。
問題2 非剛床エリアにある耐力壁を、誤って剛床の一部として計算に含めてしまった場合、その壁は剛心から距離が離れているほど「ねじり剛性」への寄与が大きく計算されてしまうため、実際には床が変形して力が伝わらないにもかかわらず、計算上の偏心率は小さく(良好に)評価されてしまう危険性がある。
解答2 :〇 解説: ねじり剛性は「剛性×距離の2乗」で効いてくるため、遠くにある壁ほど数値上の寄与が大きくなります。 実際には床が柔らかくて力が伝わらない(効かない)のに、計算上は「遠くに強い壁があるからねじれにくい」と判断され、偏心率が見かけ上良くなってしまうという、最も危険側(過小評価)の間違いにつながります。
問題3 建物の偏心率を検討する際、剛床仮定が成立する本体部分と、剛床とならない局所的な部分(キャットウォークや独立した付属フレームなど)は、挙動の質が異なるため、非剛床部分は偏心率の計算対象から除外し、個別のフレームとして安全性を確認する等のモデル化の工夫が必要である。
解答3 :〇 解説: 全体がねじれる挙動(剛床)と、その部分だけが揺れる局所的な挙動(非剛床)は分けて考える必要があります。無理に混ぜて評価せず、非剛床部分は節点重量のみを考慮して偏心率計算からは切り離し、別途その部分の応力や変形を個別検討するのが正しい設計手法です。
地下階特有の外力と構造計算・設計上の留意点
問題1 建築基準法上の定義で「地下階(天井高の1/3以上が地盤面下にある階)」に該当する階であれば、構造計算においても無条件で「地下階」として扱うことができ、地上の階よりも小さな層せん断力係数(地震力)を採用して設計してよい。
解答1:× 解説: 建築基準法の定義と、構造計算上の定義は異なります。構造計算で地下階(地震力が低減される階)として扱うには、一般的に「階高の2/3以上が地盤に接している」等の振動性状に基づく判断が必要です。傾斜地などで片側が完全に露出している場合などは、法的に地下でも構造計算上は地上階として扱う必要があります。
問題2 地下階を設ける場合、地下外壁等が地盤から受ける受動土圧や側面摩擦抵抗を期待することができるため、これらを適切に評価すれば、杭が負担すべき地震時の設計用水平力を低減させ、経済的な設計を行うことが可能である。
解答2:〇 解説: 地下階の躯体は地盤に囲まれているため、地震時に地盤からの抵抗(受動土圧など)を受けます。この抵抗分を建物全体に作用する地震力から差し引くことで、杭頭にかかる水平力を小さく評価できます。ただし、地下階の重量分だけ地震時の慣性力自体は増えるため、トータルでのバランス検討が必要です。
問題3 地下外壁(土圧壁)の設計において、壁の上部に強力な大梁と床スラブが取り付いている場合と、ドライエリア等で上部が開放されている(スラブがない)場合とでは、壁頭の境界条件(固定度)が異なるため、それぞれに応じた応力検討を行う必要がある。
解答3:〇 解説: 土圧を受ける壁の応力は「どこで支えられているか(境界条件)」で大きく変わります。スラブがあれば「上端固定(またはピン)」として荷重を床に流せますが、スラブがない場合は「上端自由(片持ち)」に近い挙動となり、壁や柱に生じるモーメントが跳ね上がります。標準図を盲信せず、個別の境界条件を確認することが重要です。
部分地下・片土圧の設計での留意点
問題1 部分地下の建物においては、片土圧による水平変位が発生するため、直接土圧を受けている外壁だけでなく、土圧に接していない内部の柱や梁などの部材においても応力が発生することを考慮して長期荷重時の検討を行う必要がある。
回答1 :〇 解説: 片土圧を受けると、床(剛床)を介して建物全体が水平に押されて変形します。そのため、直接土に触れていない内部のフレーム(柱・梁)にも曲げやせん断などの応力が発生するため、これを見込んで設計する必要があります。
問題2 斜面地などの部分地下において、土圧を受ける側に剛性の高い壁が集中して偏心率が大きく悪化してしまう場合、設計上の有効な解決策の一つとして、土圧側にドライエリアを設けて土圧壁を主架構から分離する手法が挙げられる。
回答2 :〇 解説: 建物の片側だけが土圧壁(非常に硬い壁)、反対側が開口部となると、重心と剛心が大きくズレて極端な偏心を生みます。ドライエリア(空堀)を設けて土圧を受ける擁壁を建物本体と別の構造にすることで、主架構のバランスを良好に保つことができます。
問題3 部分地下の設計において、地震力と土圧力を組み合わせて検討する際、両者はともに水平力であるため全く同じ性質の外力として扱い、すべての応力を外周部の特定の部材のみに集中して負担させることで、経済的かつ安全な設計となる。
回答3 :× 解説: 地震力(動的で往復する力)と土圧力(静的で常に押し続ける力)は外力としての性質が異なります。これらを重ね合わせて1つの部材で効率よく抵抗させることも経済設計には繋がりますが、特定の部材に応力を集中させすぎると危険です。それぞれの部材の「役割を明確にしていく」意識を持って検討することが重要です。
③許容応力度等設計関連
層間変形角~変形と損傷の関係と建物の継続利用をどう考えるか
問題1 建築基準法において、中地震時(一次設計)における層間変形角の制限値(原則1/200以下)が設けられた主な背景には、過去の震災において、耐力不足だけでなく「変形能力の不足」による脆性的な破壊や倒壊が多く発生したという教訓がある。
解答1 :〇 解説: 十勝沖地震や宮城県沖地震での被害分析から、建物には「強さ(耐力)」だけでなく「粘り強さ(変形能力)」が必要であることが明らかになりました。過大な変形による脆性破壊やP-Δ効果による倒壊を防ぐため、層間変形角の制限が法制化されました。
問題2 保有水平耐力計算(二次設計)において、大地震時の建物の安全性を確認するために設定する層間変形角(例:1/100)は、建築基準法によって厳密に定められた数値であり、実際の地震時に建物がその変形角を超えて変形することは法的に許容されていない。
解答2 :× 解説: 保有水平耐力計算で用いる層間変形角(1/100など)は、設計者が耐力を算出するために仮定した「解析終了時点の変形状態」であり、法的な上限値ではありません。実際の巨大地震では、この設定値を超えて変形する可能性がありますが、それでも倒壊しないだけのエネルギー吸収能力(保有耐力)があるかを確認するのがこの計算の目的です。
問題3 建物の変形を評価する指標として、各階の「絶対変位(地面からの移動量)」ではなく、上下階の変位差を階高で割った「層間変形角」を用いる理由は、階高が異なる場合でも、部材の損傷度合い(歪みの大きさ)を統一的な尺度で評価できるためである。
解答3 :〇 解説: 同じ「2cmのズレ」でも、階高が高い階と低い階では、柱の傾き(歪み)角度が異なります。部材の損傷は歪みの角度に比例するため、階高の影響を取り除いた「層間変形角(ラジアン)」で評価することで、建物のどの階が危険な状態にあるかを正しく把握できます。
偏心率~立体解析との関係
問題1 建築基準法における「偏心率」の規定は、1981年の新耐震設計法の導入時に定められたものであるが、その数値基準や評価方法は、当時の主流であった「手計算による平面解析」を前提として設定されたものである。
解答1 :〇 解説: 偏心率の規定は、コンピュータによる立体解析が一般的ではなかった時代に作られました。当時の平面解析では「ねじれ」を直接計算できなかったため、係数を用いて割り増し評価するために導入されたという歴史的背景があります。
問題2 現在の一貫計算ソフトの主流である「三次元立体解析」を用いて応力解析を行う場合、重心と剛心のズレによる「ねじれ応力」は解析結果(各部材の応力)に既に反映されているため、保有水平耐力計算において形状係数(Fes)を用いて必要保有水平耐力を割り増すことは、偏心の影響を「二重に」考慮していることになる。
解答2 :〇 解説: 立体解析では、ねじれによって部材に生じる付加応力が計算されています。しかし、現行法規ではさらに偏心率に応じた割増係数(Fes)を乗じて必要耐力を算出することが求められるため、実質的に偏心の影響を二重にカウント(過剰に安全側へ評価)しているという矛盾が生じています。
問題3 偏心率が規定値(0.15など)を超えてしまった場合、建物のねじれを解消するために、剛心が偏っている側の耐震壁をあえて「削除」または「スリットを入れて剛性を下げる」ことで偏心率を改善する手法は、建物全体の剛性は低下するものの、バランスが良くなるため、耐震工学的に最も推奨される安全な設計方針である。
解答3 :× 解説: 数値を合わせるために壁を減らすのは本末転倒です。過去の震災被害を見ても、偏心していても壁量が多く剛性が高い建物は倒壊を免れています。 壁を減らしてバランスだけ良くした「柔らくて弱い建物」よりも、偏心していても「硬くて強い(ねじれ変形量自体が小さい)建物」の方が耐震性は高くなります。安易な壁の削除は避けるべきです。
偏心率~剛床仮定との関係
問題1 構造計算において「剛床仮定」が成立しないエリア(大きな吹き抜けや渡り廊下などの非剛床部分)であっても、一貫計算ソフト上で剛床としてモデル化して偏心率を計算すれば、床の面内変形を考慮した正確な剛心位置と偏心率を算出することが可能である。
解答1 :× 解説: 偏心率の計算自体が「剛床(床が変形しない)」ことを前提としています。非剛床部分を無理やり剛床として計算すると、床の変形(たわみ)が無視され、遠くの壁まで力が瞬時に伝わる計算になってしまうため、架空の剛心位置が算出され、実態とかけ離れた誤った結果となります。
問題2 非剛床エリアにある耐力壁を、誤って剛床の一部として計算に含めてしまった場合、その壁は剛心から距離が離れているほど「ねじり剛性」への寄与が大きく計算されてしまうため、実際には床が変形して力が伝わらないにもかかわらず、計算上の偏心率は小さく(良好に)評価されてしまう危険性がある。
解答2 :〇 解説: ねじり剛性は「剛性×距離の2乗」で効いてくるため、遠くにある壁ほど数値上の寄与が大きくなります。 実際には床が柔らかくて力が伝わらない(効かない)のに、計算上は「遠くに強い壁があるからねじれにくい」と判断され、偏心率が見かけ上良くなってしまうという、最も危険側(過小評価)の間違いにつながります。
問題3 建物の偏心率を検討する際、剛床仮定が成立する本体部分と、剛床とならない局所的な部分(キャットウォークや独立した付属フレームなど)は、挙動の質が異なるため、非剛床部分は偏心率の計算対象から除外し、個別のフレームとして安全性を確認する等のモデル化の工夫が必要である。
解答3 :〇 解説: 全体がねじれる挙動(剛床)と、その部分だけが揺れる局所的な挙動(非剛床)は分けて考える必要があります。無理に混ぜて評価せず、非剛床部分は節点重量のみを考慮して偏心率計算からは切り離し、別途その部分の応力や変形を個別検討するのが正しい設計手法です。
剛性率~剛性率が生まれた理由から規準値の背景、実務での着眼点
問題1 建築基準法における「剛性率」の規定は、主に平面的な剛性の偏り(重心と剛心のズレ)を評価し、地震時の建物の「ねじれ振動」による被害を防ぐことを主目的として導入されたものである。
解答1 :× 解説:「ねじれ」を評価するのは「偏心率」です。 「剛性率」は、立面(高さ)方向の剛性バランスを評価する指標です。1968年の十勝沖地震などで見られた、ピロティ階などの「特定の階(柔らかい階)」に変形が集中して潰れる「層崩壊」を防ぐことを主目的として導入されました。
問題2 剛性率が0.6未満となる場合、特定階への変形集中による損傷リスクを補うために必要保有水平耐力を割り増す係数(Fs)を用いるが、このFsの最大値は、1995年の阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえた法改正により、当初の「1.5」から現在は「2.0」に引き上げられている。
解答2 :〇 解説: 剛性率が低い(柔らかい階がある)と、そこに被害が集中します。そのリスクをカバーするために耐力を割り増すのがFs(剛性率に応じた割増係数)です。 当初の上限は1.5でしたが、阪神・淡路大震災で剛性率の低い建物の被害が甚大だった教訓から、より安全性を高めるために最大値が2.0へと強化されました。
問題3 剛性率は一般的に一次設計時の「弾性剛性」に基づいて算出される指標であるが、実際に層崩壊などの被害が問題となるのは大地震時の「塑性化(剛性低下)」が進んだ段階であるため、弾性時の剛性率が良いからといって、必ずしも大地震時の変形集中がないとは限らない点に留意する必要がある。
解答3 :〇 解説: 剛性率はあくまで初期の「硬さ(弾性剛性)」の比率です。 しかし、大地震時には部材がひび割れたり降伏したりして、剛性が刻々と変化(低下)します。弾性段階ではバランスが良くても、塑性化した途端に特定の階だけ急激に剛性が落ちて変形が集中するケースもあるため、弾塑性解析などを通じて崩壊メカニズムを確認する視点が重要です。