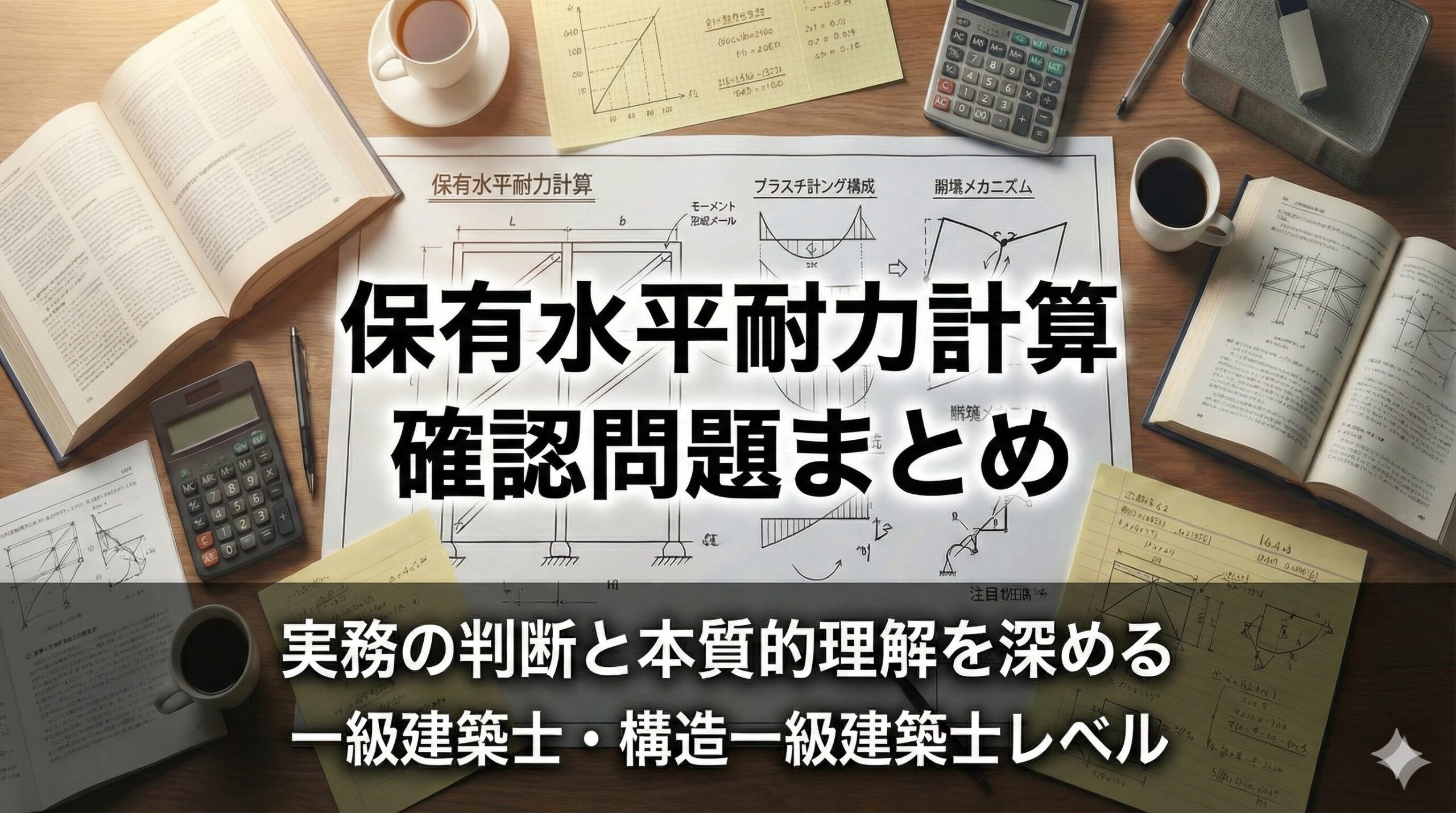保有水平耐力計算に関する記事での確認問題のまとめになります。問題のレベルとしては一級建築士と構造一級建築士の間くらいだと思いますが、実務の判断をベースに本質的な部分を深められるようにしています。
解答できなかった部分を改めて記事に目を通してみてください。
①保有水平耐力計算導入
保有水平耐力計算とは~計算体系を整理
問題1 保有水平耐力計算は、最終的に「保有水平耐力(Qu)」が「必要保有水平耐力(Qun)」を上回っていることを確認するだけの計算ではなく、「Ds判定(崩壊形の確認)」や「保証設計(部材の余裕度確認)」を含めた総合的な検討プロセスである。
解答1 :〇 解説: 単に耐力が足りているかだけでなく、「どのようなメカニズムで壊れるか(Ds判定)」を確認して係数を決め、その上で計算の前提が崩れないよう「脆性破壊に対する余裕があるか(保証設計)」を確認するまでがセットになっています。これら全てが整合して初めて安全性が担保されます。
問題2 保有水平耐力(Qu)の値は、その階にある全ての柱・梁・耐震壁などの部材がそれぞれ発揮できる「最大耐力」を単純に合計した値として定義される。
解説2 :× 解説: 部材によって最大耐力を発揮するタイミング(変形角)は異なります。例えば、硬い耐震壁は早い段階で最大耐力に達しますが、柔らかい柱はもっと変形してから最大耐力になります。 保有水平耐力は、ある特定の変形時点(設計者が設定した時点)において、各部材が「その瞬間に負担している力」の合計値となります。
問題3 保有水平耐力を算出する際に、解析を終了させるクライテリアとして設定した「層間変形角(例:1/100)」は、実際に大地震が発生した際にその建物に生じる「最大変形量」と等しいものとして扱ってよい。
解説3 :× 解説: 保有水平耐力計算における変形角は、あくまで「耐力を評価するために便宜的に設定した状態」です。 特にDs値を小さく設定した(=塑性変形能力を期待する)建物の場合、実際の地震時には、計算で設定した変形角(例:1/100)を超えて変形する可能性があります。この計算は「耐力の評価」が主目的であり、「変形の予測」ではない点に注意が必要です。
②外力と増分解析
Ai分布と必要保有水平耐力分布の使い分けと注意点
問題1 保有水平耐力計算において「必要保有水平耐力の分布」を外力分布として採用するためには、原則として増分解析の結果、架構が「全体崩壊形」となることが条件であるが、部分崩壊形であっても、崩壊する階以外の部分で塑性ヒンジが生じるなど、告示で定められた特定の条件を満たせば採用が可能である。
解答1:〇 解説: 基本原則は、エネルギー吸収能力の高い「全体崩壊形」であることです。しかし、告示(平19国交告第594号)により、部分崩壊形や局部崩壊形であっても、崩壊していない他の階でも梁端部などに塑性ヒンジが発生し、建物全体として水平力に耐えられなくなる状態が確認できれば、採用が認められています。
問題2 建物全体の各階における構造特性係数(Ds値)や形状係数(Fes値)がすべて同じ数値である場合、「必要保有水平耐力の分布」を採用すると、「Ai分布」を採用した場合と比較して、外力分布の形状が大きく変わり、より経済的な設計が可能になる。
解答2:× 解説: Ds値やFes値が全階で同じであれば、必要保有水平耐力(Qun)の分布形状は、基本的にAi分布の形状と相似形(ほぼ同じ)になります。 「必要保有水平耐力の分布」を採用するメリットが最大限に発揮されるのは、階によってDs値が異なり、Ai分布のままでは最も厳しい階の係数に全体が引っ張られて不経済になってしまうようなケースです。
問題3 ピロティ形式(1階が柔らかい)や、下層がRC造で上層が鉄骨造といった剛性・耐力に極端な差がある建物において、「必要保有水平耐力の分布」を採用することは、各階の必要耐力を忠実に反映しているため、Ai分布を用いるよりも常に安全側の設計となる。
解答3:× 解説: 剛性や耐力が低い層(弱層)は、計算上の「必要保有水平耐力」も小さくなります。これをそのまま外力分布として採用すると、その弱層にかかる地震力が小さく見積もられてしまう恐れがあります。 実際の地震では弱層に変形が集中しやすいため、こうしたケースではAi分布(より一般的な分布)を採用するか、弱層の耐力を意図的に割り増すなどの配慮が必要となり、必要保有水平耐力分布が必ずしも安全側とは限りません。
増分解析と復元力特性の基本を解説
問題1 保有水平耐力を算出する手法として「増分解析」が主流となっている大きな理由は、他の簡便法(節点振分け法など)とは異なり、部材の塑性化する順番を追跡できるため、途中で脆性破壊する部材がある場合でも、その時点での耐力を特定・評価できるからである。
解答1:〇 解説: 増分解析の最大のメリットは「プロセスの可視化」です。荷重を少しずつ増やしていくことで、「どの部材が最初に降伏するか」「脆性部材がいつ破壊するか」をステップごとに追跡できます。これにより、特定の部材が壊れた時点を崩壊とみなすなど、柔軟かつ精度の高い評価が可能になります。
問題2 復元力特性のモデル化において、一般的に「鉄骨造(S造)」の部材は、コンクリートのひび割れによる剛性低下を表現するために、3つの直線で構成される「トリリニアモデル」が用いられることが多い。
解答2:× 解説: 鉄骨造(S造)は、降伏点が明確で粘り強い挙動を示すため、通常は2つの直線で構成される「バイリニアモデル」が用いられます。 一方、設問にある「トリリニアモデル」は、コンクリートのひび割れと鉄筋の降伏という2段階の剛性低下が発生する「鉄筋コンクリート造(RC造)」などで主に使用されます。
問題3 保有水平耐力計算で行う「増分解析」は、建物に少しずつ力を加えていく解析手法であるため、実際の地震時に発生する「繰り返し荷重による剛性劣化(武田モデルのような挙動)」や「大変形時のP⊿効果」といった動的な現象も、標準的な計算設定の中ですべて自動的に考慮されている。
解答3:× 解説: 増分解析は基本的に「一方向への静的な加力」を行う解析です。 そのため、地震のような「行って戻って」の繰り返しによる剛性の劣化や、揺れている最中の二次的な応力(P⊿効果)などは、標準的な静的解析では考慮されません。計算結果はあくまで静的な耐力評価であることを理解し、動的な影響は設計者の知識で安全側に見込む等の判断が必要です。
増分解析におけるモデル化の変化を解説
問題1 増分解析において、ある部材が降伏して「塑性ヒンジ」が発生したと判定されると、計算上その部材は強度(耐力)を失ったものとして扱われ、それまで負担していた全ての応力が解放されて周囲の部材へ再配分される。
解答1 :× 解説: 「強度(耐力)」を失うのではありません。塑性ヒンジ化すると、「曲げ剛性」が大きく低下(計算上は極小化)します。これは「今の耐力は維持するが、これ以上荷重が増えても新たなモーメントは負担できない(回転変形だけが進む)」状態を意味します。再配分されるのは、ヒンジ化以降に加わった「増分」の荷重です。
問題2 解析中に「支点の浮き上がり(引張力が抵抗力を超える)」が発生した場合、その影響は浮き上がった柱を含む構面内(地震力を受けている方向)だけでなく、直交方向の梁やフレームの損傷要因になることもあるため、直交方向のチェックも必要である。
解答2 :〇 解説: 浮き上がりが発生すると、その柱につながる直交方向の梁が、浮き上がり変位を無理やり抑え込もうとして抵抗します(剛性が効いてきます)。その結果、直交方向の梁に予期せぬ大きな力がかかり、曲げヒンジやせん断破壊が発生して崩壊形の決定要因になることがあるため、注意が必要です。
問題3 脆性破壊(せん断破壊など)する部材が建物内に存在する場合、解析がそこでストップ(収束しない)して部分崩壊となるか、解析が継続するかは、プログラムが構造的な安定性を自動計算して決定するものであり、設計者が設定でコントロールすることはできない。
解答3 :× 解説: 解析がストップするか継続するかは、設計者の「モデル化の設定」に大きく依存します。設計者がその脆性部材について「軸力保持を考慮する」設定にしていれば解析は継続([B]パターン)し、「考慮しない」設定にしていれば解析はストップ([A]パターン)します。自動判定任せにするのではなく、実態に合わせて設計者が適切に設定する必要があります。
③ヒンジ図
崩壊形とヒンジ図のチェックの視点
問題1 保有水平耐力計算において、Ds値(構造特性係数)は一貫計算ソフトが自動的に算出してくれるため、設計者はその数値をそのまま採用し、最終的な保有水平耐力が足りているかどうかの数値確認のみに注力すればよい。
解答1 :× 解説: Ds値の決定を一貫計算ソフト任せにしてはいけません。設計において重要なのは、計算結果に一喜一憂することではなく、設計者が「どのような崩壊形(壊れ方)にするか」を主体的に想定し、その通りになるように調整することです。意図した崩壊形に合わせてDs値を設定する必要があります。
問題2 「全体崩壊形」を目指す場合、原則として柱よりも梁が先に降伏する「梁降伏先行型」とする。これは、軸力を支える柱が先に壊れると建物全体の崩壊につながるリスクが高いためである。
解答2 :〇 解説: 柱は建物の重量(軸力)を支える重要な部材です。柱が梁よりも先に降伏して損傷すると、層崩壊や建物全体の倒壊につながる恐れがあります。そのため、梁を先に降伏させてエネルギーを吸収させる「全体崩壊形(梁降伏先行型)」を目指すのが基本です。
問題3 ヒンジ図の確認において、耐震壁の脚部などが「浮き上がらない(引抜き力が作用しても拘束される)」設定とすることは、耐震壁が多くの水平力を負担することになるため、常に「安全側(過小評価)」の設計となる。
解答3 :× 解説: 支点の「浮き上がり」を考慮することで、解析上、耐震壁のせん断破壊の発生が遅いステップまで先送りされてしまうことがあります。その結果、せん断破壊が起きるまでの耐力が積算され続け、最終的な保有水平耐力(Qu)が実態よりも「高め(危険側)」に算出されてしまう恐れがあります。 浮き上がりの有無が結果にどう影響するかはケースバイケースであるため、両方のパターンを検討して、耐力が過大評価されていないかを確認することが重要です。
「塑性ヒンジ」の概念と保有水平耐力計算における役割を解説
問題1 保有水平耐力計算(増分解析)において、ある部材端に「塑性ヒンジ」が形成されたと判定された場合、計算モデル上ではその節点は「完全なピン接合(回転剛性ゼロ)」となり、それ以上は曲げモーメントを一切負担しないものとして扱われる。
解説1 :× 解説: 塑性ヒンジは「完全なピン」ではありません。計算上は、全塑性モーメント(降伏耐力)に達した後も、その耐力を維持したまま回転変形が進む「回転剛性が低下したバネ(弾性剛性の数%程度)」として扱われます。これにより、その部材でエネルギーを吸収しつつ、負担しきれない余剰な力を他の部材へ再配分させることができます。
問題2 梁の塑性ヒンジ領域(塑性化する範囲)の長さを、一般的に「梁せい(梁の高さ)」と同程度と仮定して設計を行う理由は、複雑な理論式によって厳密に算出された結果、すべての梁において物理的に必ず梁せいと一致することが証明されているからである。
解説2 :× 解説: 「塑性ヒンジ領域=梁せい」という仮定は、理論式だけで導かれたものではなく、数多くの実験結果や研究に基づいた「経験的な判断(工学的判断)」によるものです。厳密には鉄筋量や軸力で変化しますが、実務上の安全側かつ簡便な指標として広く採用されています。
問題3 大地震時にRC造の梁に塑性ヒンジが形成された場合、現実の現象としては、引張側の鉄筋が降伏して伸び、圧縮側のコンクリートが圧壊するなどの目に見える損傷が発生するが、すぐに破断するわけではなく、粘り強く変形することで地震エネルギーを吸収している状態といえる。
解説3 :〇 解説: 塑性ヒンジは計算上の概念であると同時に、現実には「部材の損傷」を伴います。しかし、それは「崩壊」ではありません。鉄筋が粘り強く伸び、コアコンクリートが踏ん張ることで、建物全体が倒れるのを防ぎながら地震の衝撃を受け止めている、いわば「意図された損傷」の状態です。
④部材ランク
RC部材種別の判定基準の物理的意味を解説
問題1 RC造の柱の部材種別を判定する際、最も重要な指標の一つである「せん断スパン比 ho/D」が「2.0以下」となるようなずんぐりとした柱は、地震時に曲げ破壊よりも先に脆性的なせん断破壊を起こすリスクが極めて高いため、靭性が低い部材(FC~FDランク相当)として厳しく評価される。
解答1:〇 解説: 正解です。 せん断スパン比ho/Dが小さい(2.0以下など)柱は「短柱(たんちゅう)」と呼ばれます。短柱は曲げ変形能力が低く、地震力を受けると粘り強く変形する前に斜めにひび割れてせん断破壊する可能性が非常に高いため、最も注意すべき脆性部材として扱われます。
問題2 柱にかかる長期軸力が大きい場合(軸力比 $\sigma_0/Fc$ が大きい場合)、コンクリートは常に強く圧縮された状態となり、曲げに対する抵抗力が増すだけでなく、大地震時の変形性能(靭性)も向上するため、FAランクなどの高いランクに判定されやすくなる。
解答2:× 解説: 誤りです。 軸力が大きすぎると、コンクリートの余裕がなくなり、限界を超えると一気に押しつぶされる「圧壊」を起こしやすくなります。圧壊は脆性的な破壊であり、靭性が著しく低下するため、軸力比が大きい部材はランクが低く(FC等に)判定されます。実験的にも軸力比が0.33(1/3)を超えると靭性が急激に低下することが分かっています。
問題3 部材種別における「FAランク」とは、大地震時に部材が降伏しない(弾性範囲に留まる)強度を持った部材のことを指し、逆に「FC・FDランク」とは、早期に降伏して大きく変形することでエネルギーを吸収する部材のことを指す。
解答3:× 解説: 誤りです。 定義が逆です。 FAランクは「大きく変形しても(降伏しても)耐力を維持し続ける、非常に粘り強い(靭性が高い)」部材を指します。 一方、FDランクなどは「変形能力が乏しく、すぐにせん断破壊して耐力を失う(脆い)」部材です。耐震設計では、FAランクのような粘り強い部材を多く使うことで、建物全体のエネルギー吸収能力を高めることを目指します。
鉄骨造の基本を知る~架構用部材ランクと変形性能
問題1 部材ランク(FA~FD)を決定する「幅厚比(幅/厚さ)」の制限値は、使用する鋼材の強度(基準強度F値)が高いほど、部材が大きな力に耐えられるようになるため、制限は「緩やか(薄い板厚でもOK)」になる。
解答1 :× 解説:鋼材の強度が高いほど、降伏点(部材が塑性化する応力)が高くなります。つまり、より大きな圧縮力がかかるまで頑張れる分、その大きな力によって座屈しやすくなってしまいます。その座屈を防ぐために、高強度の材料ほど幅厚比の制限は「厳しく(板を厚く)」設定されています。
問題2 FAランクの部材は、塑性変形倍率が約4倍程度あり、層間変形角でいうと1/50程度まで粘り強く変形できる性能を持っているため、保有水平耐力計算におけるDs値(構造特性係数)は最も小さい「0.25」を採用することができる。
解答2 :〇 解説:FAランクは最も靭性(粘り強さ)が高い部材です。 ・FAランク:Ds=0.25(層間変形角1/50程度、塑性率4) ・FBランク:Ds=0.30(層間変形角1/100程度、塑性率2) ・FCランク:Ds=0.35(弾性限度、層間変形角1/150~1/200) ・FDランク:Ds=0.40(弾性範囲内) という関係性をイメージしておくと設計方針が立てやすくなります。
問題3 鉄骨造の部材ランクを確保するためには、部材自体の「幅厚比」の条件さえ満足していればよく、柱梁の継手・仕口の接合方法や、梁の横座屈に対する補剛条件などは、部材ランクの決定には影響しない。
解答3 :× 解説: 幅厚比は重要な要素ですが、それだけではありません。部材がその性能(ランク)をフルに発揮するためには、接合部が先に壊れないこと(保有耐力接合)や、H形鋼などの横座屈しやすい部材が適切に補剛されていることが前提条件となります。これらが満たされない場合、幅厚比が良くてもランクは下がってしまいます。
構造特性係数Dsの数値の意味
問題1 構造特性係数Dsは、1981年の新耐震基準導入時に定められたものであり、大地震時において建物が弾性範囲を超えて塑性化(粘り強く変形)することで地震エネルギーを吸収する能力(靭性)を評価するための係数である。
解答1:〇 解説: 大地震に対して、建物を無損傷(弾性範囲)で設計しようとすると、非常に太い柱や梁が必要になり現実的ではありません。そこで、建物が壊れずに粘る能力(靭性)を考慮して、必要とされる耐力を低減させるために導入されたのがDs値です。
問題2 Ds値と建物の変形能力(靭性)の関係において、一般的にDs値を「小さく(例:0.25)」設定できる建物は、Ds値を「大きく(例:0.50)」設定しなければならない建物と比較して、地震時に要求される塑性変形能力(層塑性率)は「小さく」て済む。
解答2:× 解説: 関係が逆です。 Ds値を「小さく」できるということは、それだけ耐力(強さ)に頼らず、変形能力(粘り)で地震に抵抗することを意味します。したがって、Ds値が小さい建物ほど、地震時には「より大きな塑性変形(高い層塑性率)」が要求されます。逆にDs値が大きい建物は、あまり変形できないため、強度で抵抗する必要があります。
問題3 保有水平耐力計算において、靭性の高い架構として低いDs値(例:Ds=0.3)を採用し、必要保有水平耐力を満足していることが確認できた場合、それは大地震時において建物が弾性範囲内(無損傷に近い状態)に留まり、安全であることを示している。
解答3:× 解説: 低いDs値(0.3など)を採用するということは、大地震時に建物が大きく塑性変形し、エネルギーを吸収することを前提としています。 計算上、保有水平耐力が足りていても、それは「倒壊しない」ことを確認しているだけであり、実際にはコンクリートのひび割れや鉄筋の降伏といった「損傷」が発生する変形域(1/100を超える変形など)に達している可能性が高いことを理解しておく必要があります。
減衰定数とは~定量的評価が難しい減衰要素
問題1 建築基準法で想定されている地表面加速度(400~500Gal程度)を超える地震動が観測された場合、現在の耐震基準で設計された建物は、計算上の耐震性能の上限を超えるため、理論上はすべての建物が倒壊することになる。
解答1:× 解説: 実際の地震では想定を超える加速度が観測されることがありますが、すべての建物が倒壊するわけではありません。これは、建物自体が持つ「余力」や、今回のテーマである計算に含まれない「減衰効果(摩擦や地盤へのエネルギー逸散)」が複合的に作用し、損傷を抑えているためと考えられます。
問題2 構造計算の運動方程式において、建物の揺れを抑える「減衰力」は、一般的に「速度」に比例して大きくなる力(粘性減衰)としてモデル化されるが、これはあらゆる減衰現象が物理的に速度比例であることが証明されているためである。
解答2:×解説:計算上は「速度に比例する」として扱いますが、これは解析と実測の整合性を取るための便宜的な仮定です。実際には摩擦減衰(振幅依存)や履歴減衰(変位依存)など、速度に単純比例しない減衰メカニズムも多く含まれています。計算モデルが自然現象そのものではないことを理解しておく必要があります。
問題3 保有水平耐力計算で用いる「構造特性係数Ds」は、主に部材が塑性化してエネルギーを吸収する「塑性履歴減衰」を評価したものであるが、実際の建物にはそれ以外にも摩擦減衰や地盤への逸散減衰などが作用しており、これらが計算外の安全余裕として寄与していると考えられる。
解答3:〇 解説: 正解です。 Ds値は、部材が降伏して粘り強く変形する能力(塑性履歴減衰)を係数化したものです。しかし、記事にあるように、実際の変形(層塑性率)がDs値の想定よりも小さく済むケースがあるのは、Ds値では評価していない他の減衰要素(内装材の摩擦や、揺れが地盤へ逃げる効果など)が働いているためと推測されます。
⑤保証設計
保証設計~「安全な壊れ方」を設計するRC・S造の検討項目
問題1 保有水平耐力計算における「保証設計」とは、大地震が発生しても建物が一切損傷しないこと(弾性範囲に留まること)を保証するために、部材の強度を割り増して設計する手法のことである。
解答1:× 解説: 保証設計が保証するのは「無損傷」ではなく、「安全な壊れ方(靭性的な崩壊メカニズム)」です。大地震時には部材の損傷(降伏)を許容しますが、その際に脆性的な破壊(せん断破壊など)が起きず、粘り強い曲げ破壊が先行するようにコントロールすることを目的としています。
問題2 RC造の保証設計において、柱や梁が曲げ降伏(靭性的な破壊)する前に、脆性的な「せん断破壊」が起こらないようにするため、計算上で想定される最大せん断力に対して、さらに材料強度のばらつき等を考慮した「割増係数」を乗じた力に対して安全であることを確認する。
解答2:〇 解説: 曲げ降伏はエネルギーを吸収する良い壊れ方ですが、せん断破壊は一瞬で耐力を失う危険な壊れ方です。「曲げ降伏した瞬間の力」よりも「せん断耐力」の方が確実に大きくなるように、割増係数を用いて余裕を持たせる検討を行います。
問題3 鉄骨造(S造)の露出柱脚において、柱本体が降伏する前にアンカーボルトが先に降伏・伸びてしまうような仕様(柱脚の破壊が先行する形式)となった場合、その柱は即座に靭性のない「FDランク(脆性部材)」として扱われ、保有水平耐力の計算において耐力を期待できなくなる。
解答3:× 解説: S造の露出柱脚において、柱脚(アンカーボルト等)が先行して降伏する場合、エネルギー吸収能力は低下しますが、即座にFDランク(耐力ゼロ等)になるわけではありません。 この場合はペナルティとして、必要保有水平耐力(Qun)を「0.05割り増し」することで安全性を確保する規定となっています。FDランクになる他の脆性破壊(部材の破断など)とは扱いが異なります。
付着割裂破壊の原理と対策(RC鉄筋の付着・基本編)
問題1 付着割裂破壊は、大地震時に鉄筋に過大な引張力が作用することで、鉄筋とコンクリート間の付着応力度が高まり、鉄筋に沿ってコンクリートが割裂(ひび割れ・剥落)する現象である。これが生じると、鉄筋が降伏してエネルギーを吸収する前に耐力が低下してしまうため、建物の靭性(粘り強さ)を著しく損なう脆性破壊となる。
解答1:〇 解説: 付着割裂破壊は、鉄筋がコンクリートを「内側から押し割る」ような破壊形式です。これが発生すると、鉄筋とコンクリートの一体性が失われ、鉄筋が降伏点まで引っ張られることなくスッポ抜けるような状態になるため、期待していた粘り強さ(靭性)が発揮できなくなります。
問題2 保有水平耐力計算(安全性の検討)において、大梁の付着割裂破壊を検討する場合、梁は地震時に塑性ヒンジ(曲げ降伏)を形成してエネルギーを吸収することが期待される部材であるため、解析で得られた「存在応力」ではなく、鉄筋が降伏するまで付着が健全であることを保証する「降伏強度」を用いて検討を行うのが基本である。
解答2:〇 解説: 梁のように「ヒンジ化させたい=鉄筋を降伏させたい」部材の場合、鉄筋が降伏する前にコンクリートが割れてしまっては意味がありません。そのため、計算上の応力(存在応力)が小さくても、鉄筋がフルパワー(降伏強度)を発揮しても耐えられるかどうかを確認し、靭性を保証する必要があります。逆に、基礎梁などヒンジ化させたくない部材では、存在応力での検討を選択する判断もあり得ます。
問題3 計算の結果、付着割裂破壊に対してNG(耐力不足)となった場合、主筋の断面積を変えずに耐力を向上させる対策として、主筋の径を太くして本数を減らすことは、鉄筋一本あたりの表面積が増えるため、付着に対して有利(安全側)な変更となる。
解答3:× 解説: 同じ断面積を確保する場合、「太い鉄筋を少なく」使うよりも、「細い鉄筋を多く」使う方が付着には有利です。 細い鉄筋の方が、断面積に対する周長(表面積)の比率が大きくなるため、付着応力度を分散させることができます。また、太い鉄筋はかぶりコンクリートを押し広げる力が強くなるため、付着割裂に対しては不利になります。
RC柱梁接合部がNGに!背景を踏まえた3つの実務的対応策
問題1 RC造の柱梁接合部のせん断耐力が不足(NG)した場合、接合部内の帯筋(フープ筋)の量を増やすことは、計算上のせん断耐力を直接向上させるための最も効果的な対策となる。
解答1 :× 解説: 現行の評価式において、帯筋(フープ筋)を増やしても接合部のせん断耐力数値は上昇しません。 帯筋は、ひび割れ発生後のコンクリートの拘束や、靭性を確保するために必須(0.2%〜0.3%以上)ですが、計算上のせん断耐力を上げる要因ではないことを覚えておきましょう。耐力を上げるには、コンクリート強度(Fc)や部材の断面サイズを大きくする必要があります。
問題2 保有水平耐力計算において接合部がNGとなった場合、接続する梁の主筋本数を(許容応力度計算が満足する範囲で)減らすことは、接合部に入力されるせん断力を低下させるため、有効な解決策の一つとなる。
解答2 :〇 解説: 接合部の検討には、梁などが降伏した時の力が用いられます。つまり、梁の鉄筋量をあえて減らすことで、のように梁が降伏する際の荷重(接合部への入力)を抑えることができ、結果として接合部の破壊を防ぐことができます。
問題3 接合部の検討でNGとなった場合、その接合部に取り付く部材は靭性の低い「FDランク(脆性部材)」として扱われることになるが、その場合でも構造特性係数(Ds値)を割り増して必要保有水平耐力を満足させれば、法的に適合した設計とすることができる。
解答3 :〇 解説: 接合部NG=即不適合、ではありません。 その部分が脆性的な挙動を示す(FDランク)ことを前提として、建物全体に必要な耐力(Ds値)を大きく設定し、それでも保有水平耐力が足りていれば設計として成立します。ただし、靭性型の建物(純ラーメンなど)ではDs値が大きくなりすぎるため現実的でないことが多く、強度型の建物向けの最終手段と言えます。
保有耐力接合とは?鉄骨造の原則「部材<接合部」
問題1 保有耐力接合の主たる目的は、大地震時に接合部(ボルトや溶接部など)が部材(柱・梁・ブレース)よりも先に破壊することで、接合部で地震エネルギーを効率的に吸収させることである。
解答1 :× 解説: 順序が逆です。保有耐力接合の目的は、「接合部が壊れる前に、部材が先に降伏する」ことです。接合部の破壊はエネルギー吸収の乏しい「脆性的な破壊」になりがちです。一方、部材がぐにゃりと曲がったり伸びたりする(塑性化する)ことで、粘り強く地震エネルギーを吸収(靭性を発揮)します。そのために接合部を部材よりも強くしておく必要があります。
問題2 保有耐力接合の設計において重要なのは「接合部が破壊しないこと」であるため、大地震時において接合部が完全に無変形(弾性状態)であることまでは必ずしも求められていない。
解答2 :〇 解説: 記事にあるように、「重要なのは、接合部が『破壊』しないことであり、必ずしも『無変形(弾性状態)』である必要はありません」。部材が降伏してエネルギーを吸収しきるまで、接合部が破断せずに持ちこたえる強さがあれば、保有耐力接合の目的は達成されます。
問題3 梁の継手や仕口の検討において、接合部の耐力が梁の「全塑性モーメント(降伏時の最大耐力)」と同等の数値であれば、梁は十分に塑性化できるため、それ以上の耐力を接合部に持たせる必要はない。
解答3 :× 解説: 梁などの鋼材は、降伏して全塑性モーメントに達した後も、変形が進むと「ひずみ硬化」によってさらに材料強度が上昇します。そのため、接合部の耐力が全塑性モーメントと「同等」では、ひずみ硬化時に接合部が負けて破壊してしまう恐れがあります。このひずみ硬化や材料強度のばらつきを考慮し、所定の安全率を乗じて、全塑性モーメントよりも高い耐力を接合部に持たせる必要があります。
柱脚仕様の使い分けと露出柱脚のチェックの視点
問題1 露出柱脚は、施工性や経済性に優れる一方で、構造的な固定度は「完全固定(Fix)」ではなく「半固定(回転ばね)」として扱われるため、設計時にはその回転剛性が建物全体の変形や応力に与える影響を考慮する必要がある。
解答1 :〇 解説: 露出柱脚は、根巻き柱脚や埋込柱脚のようにコンクリートで拘束されていないため、完全には固定されず、ある程度回転します。これを「半固定(回転ばね)」としてモデル化します。回転剛性の設定次第で、柱の応力や建物の揺れ方が変わるため、コストとのバランスを見ながら適切な製品を選定する必要があります。
問題2 建築基準法の告示(平12建告第1456号)において、露出柱脚のアンカーボルトのコンクリートへの定着長さは、抜け出し防止の観点から「ボルト径の10倍(10d)以上」と定められている。
解答2 :× 解説: 「10倍」ではなく「20倍(20d)」です。 告示では、アンカーボルトの定着長さは「径の20倍以上」と明確に数値で定められています。この「20d」という数値は、鉄骨造の柱脚に限らず、RC造などの定着検討でも目安として使われる重要な基準値ですので、必ず覚えておきましょう。
問題3 露出柱脚の選定において、大地震時に柱が梁よりも先に降伏しないようにする「保有耐力接合(保有水平耐力接合)タイプ」への適合は義務であるため、アンカーボルト側が先に降伏・伸びてしまうような仕様(非適合)を採用することは構造設計上認められていない。
解答3 :× 解説: 基本的には柱を先に降伏させる(保有耐力接合タイプにする)ことが望ましいですが、意匠的な制約やコスト、基礎への負担などを考慮し、あえてアンカーボルト側でエネルギーを吸収させる(非適合とする)選択も可能です。 ただし、その場合はDs値(構造特性係数)の割増しが必要になるなど、設計ルートや崩壊形の想定に整合させる必要があります。「意図を持って選ぶ」ことが重要です。