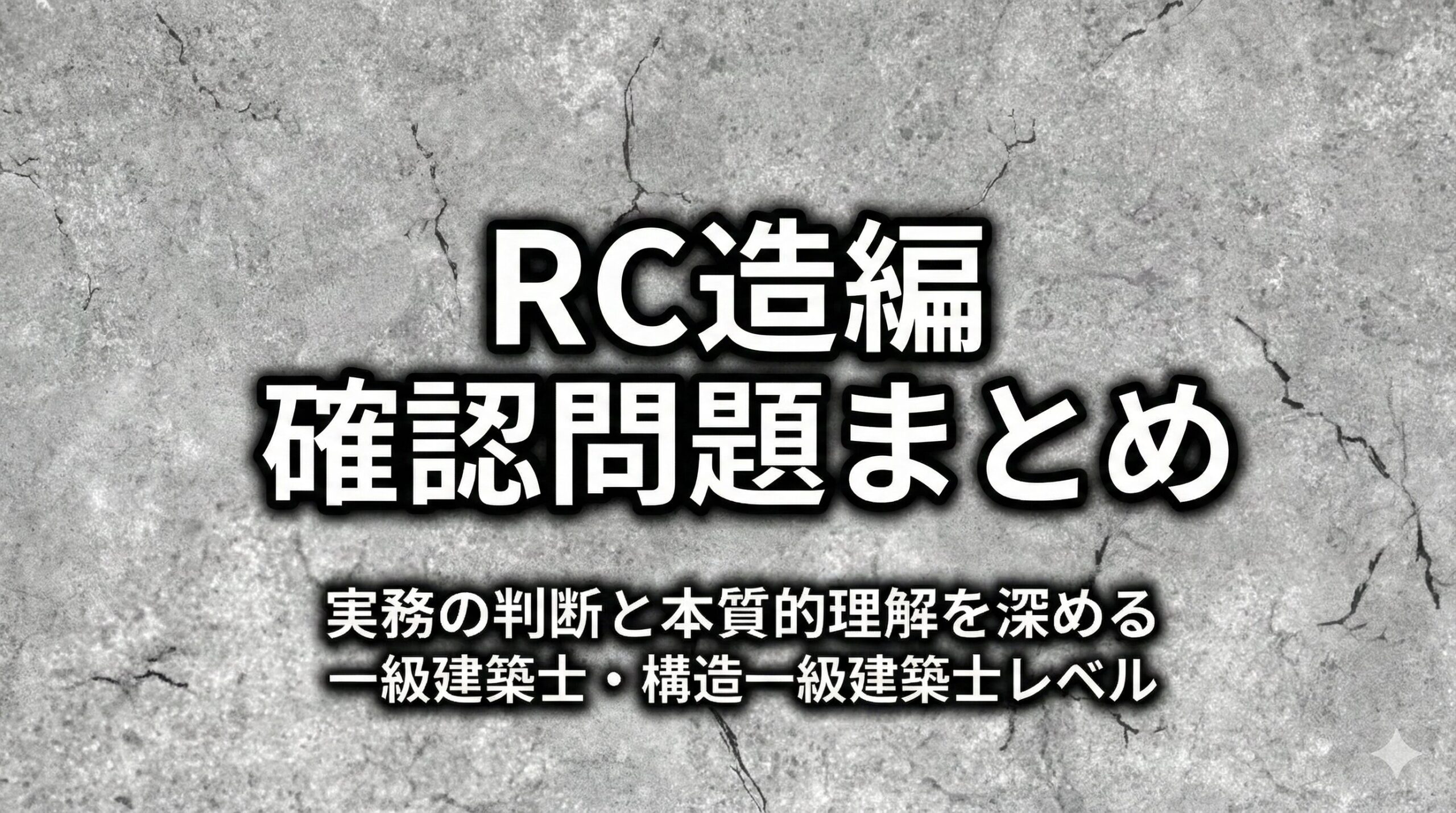RC造に関する記事での確認問題のまとめになります。問題のレベルとしては一級建築士と構造一級建築士の間くらいだと思いますが、実務の判断をベースに本質的な部分を深められるようにしています。
解答できなかった部分を改めて記事に目を通してみてください。
①一般事項
RC造設計の本質を知る/材料特性から耐震設計の勘所まで
問題1 鉄筋コンクリート(RC)造が成立する最大の理由は、コンクリートの圧縮への強さと鉄筋の引張への強さを組み合わせたことにあるが、それに加えて両者の「線膨張係数(温度による膨張・収縮の割合)」がほぼ同じ値であり、温度変化による剥離や破壊が起きにくいという特性が重要である。
解答1 :〇 解説: コンクリートと鉄筋は、温度変化に対する伸び縮みの割合(線膨張係数)がほぼ等しいため、気温の変化があっても内部で応力が生じたり剥離したりせず、一体として挙動することができます。
問題2 一次設計(許容応力度計算)において、耐震壁が地震力の大部分(50%以上など)を負担している場合、耐震壁の設計さえ安全であれば、その他の柱や梁(フレーム)にかかる負担は小さくなるため、フレーム部分の検討は特段の割増などを行わなくても安全側の設計となる。
解答2 :× 解説: 計算上、剛性の高い耐震壁に力が集まるのは正しいですが、実際には地震時に壁がひび割れて剛性が低下すると、負担しきれなくなった力が柱や梁(フレーム)に流れていきます。 計算上で壁に負担させすぎていると、この「再配分された力」に対してフレームが耐力不足になる恐れがあるため、告示(594号)ではフレームの設計用応力を割り増す規定が設けられています。
問題3 建物全体の終局耐力(保有水平耐力など)を算出する際、耐震壁と柱・梁フレームが混在する建物においては、それぞれの部材が持つ「最大耐力」を単純に合計することで、建物全体が発揮できる最大の強さを正確に評価することができる。
解答3 :× 解説: 部材によって最大耐力を発揮する「変形角(タイミング)」が異なります。 耐震壁は変形が小さい段階(1/500程度)で最大耐力に達し壊れ始めますが、柱や梁はもっと変形が進んでから(1/150~)本領を発揮します。ピークがズレているため、単純な足し算ではなく、ある瞬間の変形状態における各部材の耐力を合計して評価する必要があります。
②設計方針と使用材料
RC造の材料強度の背景
問題1 コンクリートの長期許容圧縮応力度を設計基準強度(Fc)の「1/3」に制限している主な理由は、長期荷重に対してコンクリートが圧縮破壊しないように、強度に対して3倍の安全率を見込んで破壊を防止するためである。
解答1:× 解説: 長期の1/3という制限は、即時の破壊防止というよりも、「クリープ変形(時間の経過とともに変形が進む現象)」を進行させないための限界値としての意味合いが強いです。この応力レベルであれば、コンクリートにはほとんどひび割れが生じず、健全な状態が保たれます。
問題2 コンクリートのせん断許容応力度において、短期荷重時の値を長期荷重時の「2倍」ではなく「1.5倍」としている理由は、せん断破壊がひび割れ発生後の粘り強さに乏しい「脆性破壊」であるため、他の応力状態よりも高い安全率を確保するためである。
解答2:〇 解説: 圧縮や曲げは粘り強い挙動を示しますが、せん断は一度ひび割れると急激に耐力を失う危険な壊れ方(脆性破壊)をします。そのため、短期時であっても長期の1.5倍に留め、十分な余裕を持たせています。また、この数値は最低限のせん断補強筋(0.2%)があることを前提としています。
問題3 RC梁の引張鉄筋としてSD390などの高強度鉄筋を使用する場合、長期許容引張応力度については、鉄筋の材料強度(降伏点)が高いため、SD295やSD345を使用する場合よりも大きな値を採用して設計することが可能である。
解答3:× 解説: 鉄筋自体の強度は高くても、コンクリートと組み合わせる以上、鉄筋が大きく伸びるとコンクリートのひび割れ幅が大きくなってしまいます。 ひび割れ幅を0.3mm程度以下に抑えるために、鉄筋のひずみを制限する必要があり、高強度鉄筋であっても長期許容応力度は上限値(約215N/mm²、太径はさらに低減)で頭打ちとなります。
③荷重・外力
すべての基本「荷重表」と力の流れの始点「RCスラブ」編
問題1 機械室などに重量のある設備機器を設置する場合、荷重表を作成する際には、機器の総重量をその部屋全体の面積で割って「平米荷重(kN/m²)」として均した数値を算出し、その数値のみを用いてスラブや小梁の断面算定(局部検討)を行うのが最も合理的で安全な設計手法である。
解答1 :× 解説: 部屋全体で均した荷重は、建物全体の重量(地震力算定用など)としては正しいですが、スラブや小梁の「局部検討」に使うと危険です。 実際には機器のない場所にも荷重が分散される計算になり、機器直下のスラブにかかる大きな力が過小評価されてしまうためです。局部検討では、機器の重量をその足元や支持梁に直接作用させて検討する必要があります。
問題2 RCスラブの配筋において、計算上の必要鉄筋量を満たしていれば、施工時(コンクリート打設前)に作業員が配筋の上を歩くことによるたわみ等の影響は考慮する必要がなく、細径の鉄筋(D10など)を使用してもかぶり厚さの確保等の品質管理上問題はない。
解答2 :× 解説: 計算上はD10で足りていても、施工時には作業員が上端筋の上を歩きます。細いD10では人の重みでたわんでしまい、配筋位置が下がって上端筋が十分に機能しなかったり、必要な「かぶり厚さ」が確保できなくなる恐れがあります。そのため、施工時の剛性を確保するために、上端筋にはD13以上を使用するなどの配慮が実務上推奨されます。
問題3 片持ちスラブ(バルコニーなど)の設計においては、長期荷重に対する許容応力度設計(断面算定)を行うだけでなく、コンクリートにひび割れが発生すると剛性が低下してたわみが急増するリスクがあるため、設計用曲げモーメントが「ひび割れ発生モーメント」を超えないかを確認する等の検討を行うことが重要である。
解答3 :〇 解説: 片持ちスラブは「静定構造物」であり、支えが一つしかないため、損傷が即座に大変形や崩壊につながるリスクがあります。特にコンクリートのひび割れは剛性を著しく低下させ、過大なたわみの原因となるため、許容応力度だけでなく「ひび割れ耐力」に対する余裕度を確認することが極めて重要です。
④応力解析
RC造構造設計の基本~耐震壁のモデル化とは?開口部の扱いまで解説
問題1 RC造の耐震壁は、柱や梁で構成されるラーメン架構と比較して、地震力(水平力)を受けた際の変形性状が異なり、ラーメン架構が主に「曲げ変形」するのに対し、耐震壁は主に「せん断変形」が支配的となるため、一般的に極めて高い水平剛性を持つ。
解答1 :〇 解説: ラーメン架構は建物全体が弓なりに曲がるイメージ(曲げ変形)ですが、耐震壁は箱がズレるような変形(せん断変形)が支配的です。この変形モードの違いにより、耐震壁は非常に硬く(剛性が高く)、地震力の大部分を負担する特性を持っています。
問題2 耐震壁に開口を設ける際、建築基準法等の規定にある「開口周比が0.4以下」という数値基準さえ満たしていれば、開口の位置が柱や梁に近接していたとしても、構造計算上は無条件に健全な「耐震壁」としてモデル化して問題ない。
解答2 :× 解説: 数値基準(0.4以下)は重要ですが、それだけでは不十分です。 開口が柱や梁に近接していると、壁としての力の伝達機構(圧縮ストラット)が形成されにくかったり、柱への応力集中を招いたりします。力の流れを阻害する場合は、耐震壁ではなく「袖壁付きラーメン」として評価するなど、実状に合わせたモデル化の判断が必要です。
問題3 一貫構造計算ソフトにおいて耐震壁として入力した場合、その周囲にある柱や梁(枠部材)の断面算定(曲げ・せん断の検定)は計算対象外となることが一般的であるため、スリーブなどの開口が柱際にあり局部的に「短柱・短梁」となるような場合でも、ソフト上でエラーが出なければ特段の配慮は不要である。
解答3 :× 解説: ソフトが計算対象外(検定省略)にしているからといって、物理的に安全なわけではありません。 特に柱際や梁際の開口は、その部分の部材長さを短くし(短柱・短梁化)、脆性的なせん断破壊を引き起こすリスクがあります。計算結果に表れなくとも、設計者の判断でせん断補強筋(あばら筋・帯筋)を増やすなどの配慮が不可欠です。
耐震壁と雑壁、どう扱う?モデル化の基本と注意点
問題1 線材モデルにおける「壁エレメント置換法」では、壁の両側にある「付帯柱」は、通常の柱と同様に曲げモーメントやせん断力を負担する剛接合部材としてモデル化され、壁全体の水平剛性に大きく寄与する設定となっている。
解答1 :× 解説: 壁エレメント置換法において、付帯柱の役割は主に「軸剛性(鉛直方向の突っ張り)」を表現することです。一般的に柱頭・柱脚は「ピン(回転自由)」として扱われるため、付帯柱自体は曲げやせん断剛性には寄与しません(壁エレメントそのものがせん断剛性を負担します)。 逆に、付帯梁(壁上下の梁)については、壁と一体化して変形しないことを表現するため「剛域(変形しない)」としてモデル化されます。
問題2 耐震壁を、長期荷重(鉛直荷重)を支える梁のように利用する場合、水平力用に設定された解析モデル(壁エレメント)をそのまま用いると、鉛直方向の剛性が実態よりも高く(硬く)評価され、たわみが過小に算出される危険性があるため、剛性の補正や別途検討が必要である。
解答2 :〇 解説: 壁エレメント置換はあくまで「水平力(地震力)」に対する挙動(せん断変形)を再現することに特化したモデルです。 そのまま長期荷重を載せると、鉛直方向の曲げやせん断剛性が数百倍に評価されてしまうことがあり、計算上「ほとんどたわまない」という誤った結果になりがちです。長期荷重を支える場合は、剛床解除や倍率補正を行い、1層分の梁として手計算等でたわみをチェックする必要があります。
問題3 一貫計算において、開口が大きい壁などを軸を追加して無理やり「耐震壁」としてモデル化することは、計算上の保有水平耐力(Qu)が向上するため、常に「安全側」の設計判断といえる。
解答3 :× 解説: 「耐力が上がる=安全」とは限りません。 無理に耐震壁として評価することで、剛性バランス(偏心率・剛性率)が悪化したり、増分解析においてその壁が早期にせん断破壊(脆性破壊)を起こし、建物全体のDs値(必要とされる耐力)が跳ね上がってしまうことがあります。結果として、要求性能が高くなり、かえって設計のハードルが上がったり、危険側の設計になることもあるため、適切なモデル化の判断が必要です。
柱梁接合部の本質 -歴史的背景とモデル化の理論
問題1 一般的な一貫計算プログラムにおいて、柱梁接合部を「剛域(変形しない領域)」としてモデル化する理由の一つは、接合部の変形を無視することで柱や梁などの部材に生じる応力が小さく計算され、経済的な(断面を小さくできる)設計が可能になるためである。
解答1 :× 解説: 接合部を「剛(変形しない)」と仮定すると、地震などによる建物の変形をすべて柱や梁が負担することになります。その結果、柱や梁に生じる応力は「大きめ」に計算される傾向にあります。これは、部材断面が大きくなりやすいため経済的とは言えませんが、構造設計としては「安全側」の評価になるため、このモデル化が一般的に採用されています。
問題2 RC造の柱梁接合部の検討において、接合部パネルの「せん断耐力」を計算上向上させるためには、接合部内に入れるフープ筋(帯筋)の量を増やすことが最も直接的で効果的な対策である。
解答2 :× 解説: ここは勘違いしやすいポイントです。現在の耐力式(靭性指針など)において、接合部のせん断耐力は主に「コンクリート強度」「接合部の形状(体積)」「直交梁の有無」などで決まります。 フープ筋には0.2%や0.3%といった「最小鉄筋量」の規定はあり、拘束効果として必須ですが、計算式上はフープ筋を増やしてもせん断耐力の数値自体は上がりません。耐力が不足する場合は、コンクリート強度を上げるか、柱断面を大きくする等の対策が必要です。
問題3 1995年の阪神・淡路大震災では、鉄骨造の梁端部の溶接作業用に設けられた「スカラップ(溶接孔)」に応力が集中し、そこを起点とした脆性破壊が多発したため、現在ではスカラップを設けない「ノンスカラップ工法」が標準となっている。
解答3 :〇 解説: かつては現場溶接の作業性を良くするためにスカラップ(切り欠き)を設けていましたが、震災時にそこが破壊の弱点(起点)となることが判明しました。その教訓から、現在は応力集中を避けるためにスカラップを設けない「ノンスカラップ工法」とし、完全溶込み溶接を行うことが一般的です。
⑤断面検定
RC造の柱・梁・接合部の『最小値』とその意図
問題1 RC造の柱において、主筋の断面積の合計は柱断面積の「0.8%以上」とする規定があるが、これは主に長期荷重に対する耐力を確保するためだけでなく、乾燥収縮によるひび割れの抑制や、大地震時にコンクリートが塑性化した後も急激な耐力低下を防ぎ、建物の粘り強さ(靭性)を確保する目的がある。
解答1 :〇 解説: 最低主筋量(0.8%)は、単に重さを支えるだけでなく、コンクリートの収縮ひび割れを防いだり、大地震時にコンクリートが損傷しても柱がバラバラにならずに耐え続ける(靭性を発揮する)ために必要な量として定められています。
問題2 柱の帯筋(フープ)の間隔について、建築基準法施工令では「柱の端部(仕口から柱径の2倍以内の距離)」においては密に配置(10cm以下)することが求められているが、それ以外の中央部においては間隔を広げてもよいという緩和規定があるため、施工ミスを防ぐ目的よりもコストダウンを優先し、実務においても中央部のピッチを広げる設計が一般的である。
解答2 :× 解説: 法令上は中央部のピッチを広げる緩和規定(15cm以下かつ主筋径の15倍以下)がありますが、実務では「配筋ミス(ピッチの切り替え位置の間違い)」を防ぐため、あるいは全域での高い靭性を確保するために、全長にわたって100mmピッチ(またはそれ以下)で統一することが一般的です。
問題3 柱梁接合部の設計において、接合部内は柱や梁と異なりコンクリートが四方から拘束されているため、大地震時においてもせん断破壊などの脆性的な破壊が生じるリスクは低く、接合部内の帯筋比(フープ量)を柱本体と同等(0.2%〜0.3%以上)に確保する必要はない。
解答3 :× 解説: 接合部は地震時に柱と梁からの力が集中し、巨大なせん断力がかかります。ここが破壊すると建物全体が崩壊する危険があるため、柱と同様に帯筋を配置してせん断補強を行い、主筋の抜け出し防止とコンクリートの拘束を確保する必要があります。一般的に柱の帯筋量(0.2%〜0.3%以上)をそのまま接合部内にも通す設計が基本となります。
RC造大梁の特殊な条件での設計
問題1 大地震時に大梁が安定してエネルギーを吸収(塑性変形)するためには、曲げ降伏する前にせん断破壊しないことが前提となる。特に内法スパンが短い「短スパン梁」においては、せん断力が支配的になりやすいため、両端に降伏ヒンジが発生するメカニズムを成立させるには、理論上、梁せいの2倍以上の内法スパンが必要とされている。
解答1 :〇 解説: 短スパン梁は、曲げモーメントが小さくてもせん断力が非常に大きくなるため、脆性的な「せん断破壊」を起こすリスクが高い部材です。曲げヒンジを形成して粘り強く壊れるためには、ある程度のスパン長さ(理論上は梁せいの2倍以上)が必要です。極端に短い場合はX配筋などの対策も検討します。
問題2 大梁に作用する「ねじれ応力」の検討が必要となるのは、平面的に梁が「くの字」に折れ曲がっている場合に限られるため、直線状の大梁で、かつ片側にしかスラブが取り付かない(片持ちスラブを支持する)ようなケースであっても、梁自体が直線であればねじれモーメントの検討は不要である。
解答2 :× 解説: 梁が直線であっても、片持ちスラブ(バルコニー等)を支持し、反対側にスラブがない(キャンチレバーの回転を抑えるバックストッパーがない)場合、スラブの固定モーメントがそのまま梁をねじ切る力として作用します。外周部の梁では特に注意が必要な検討項目です。
問題3 耐震壁に隣接する「境界梁」の設計において、中地震時(一次設計・弾性解析)の検討では、コンクリートのひび割れによる剛性低下を考慮しないことが一般的であるため、耐震壁の高い剛性に引きずられて梁端部に過大な応力が算出されることがあるが、実態としてはひび割れ等により応力が緩和される可能性があることを理解しておく必要がある。
解答3 :〇 解説: 一次設計(弾性解析)では、RC部材のひび割れによる剛性低下を見込まないため、硬い壁に繋がる梁には計算上、非常に大きな力が集中します。 一方、保有水平耐力計算(増分解析)では、ひび割れによる剛性低下(剛性率の低下)を考慮するため、より実態に近い応力分布となります。この解析フェーズによる剛性評価の違いを理解しておくことが重要です。
鉄筋の「定着長さ」とは?カットオフ筋の留意点
問題1 定着長さは「鉄筋の引張力」と「コンクリートの付着力」の釣り合いで決まるため、使用する鉄筋の強度(降伏点)を高くする(例:SD345からSD390へ変更する)ほど、必要な定着長さは短くなる。
解答1 :× 解説: 鉄筋の強度(降伏点)が高くなると、鉄筋が負担できる(=引っ張られる)力が大きくなります。その大きな力に耐えうるようコンクリートにしっかり握らせる必要があるため、鉄筋強度が高いほど定着長さは「長く」必要になります。逆に、コンクリート強度(Fc)を高くした場合は、付着力が強まるため定着長さは短くなります。
問題2 カットオフ筋の長さを決定する際、M図(曲げモーメント図)上で計算上鉄筋が不要となる「理論的カットオフ点」で鉄筋を止めてしまうと、定着不足やM図のズレによる危険性が生じるため、必ず「余長」を確保する必要がある。
解答2 :〇 解説: M図はあくまで仮定であり、地震時や積載荷重の偏りによって応力状態は変化(M図のズレ)します。また、カットオフ点においても鉄筋が有効に働くためには定着が必要です。そのため、理論点に「余長(梁内法スパンの1/4+15dなど)」を足した長さにする必要があります。
問題3 コスト削減を目的とする場合、カットオフ筋は部材長さに関わらず有効であるため、スパンが短い梁(短スパン)であっても積極的に採用することが推奨される。
解答3 :× 解説: 短スパンでカットオフ筋を採用しても、実際に減らせる鉄筋量はわずかです。逆に、配筋が混雑して現場の作業手間を増やしてしまったり、応力伝達が不連続になり「せん断破壊」などの弱点を引き起こすリスクが高まります。短スパンでは通し配筋とするのが一般的です。
⑥保有水平耐力
RC部材種別の判定基準の物理的意味を解説
問題1 RC造の柱の部材種別を判定する際、最も重要な指標の一つである「せん断スパン比 (h/D)」が「2.0以下」となるようなずんぐりとした柱は、地震時に曲げ破壊よりも先に脆性的なせん断破壊を起こすリスクが極めて高いため、靭性が低い部材(FC~FDランク相当)として厳しく評価される。
解答1:〇 解説: 正解です。 $h_0/D$ が小さい(2.0以下など)柱は「短柱(たんちゅう)」と呼ばれます。短柱は曲げ変形能力が低く、地震力を受けると粘り強く変形する前に斜めにひび割れてせん断破壊する可能性が非常に高いため、最も注意すべき脆性部材として扱われます。
問題2 柱にかかる長期軸力が大きい場合(軸力比 $\sigma_0/Fc$ が大きい場合)、コンクリートは常に強く圧縮された状態となり、曲げに対する抵抗力が増すだけでなく、大地震時の変形性能(靭性)も向上するため、FAランクなどの高いランクに判定されやすくなる。
解答2:× 解説: 誤りです。 軸力が大きすぎると、コンクリートの余裕がなくなり、限界を超えると一気に押しつぶされる「圧壊」を起こしやすくなります。圧壊は脆性的な破壊であり、靭性が著しく低下するため、軸力比が大きい部材はランクが低く(FC等に)判定されます。実験的にも軸力比が0.33(1/3)を超えると靭性が急激に低下することが分かっています。
問題3 部材種別における「FAランク」とは、大地震時に部材が降伏しない(弾性範囲に留まる)強度を持った部材のことを指し、逆に「FC・FDランク」とは、早期に降伏して大きく変形することでエネルギーを吸収する部材のことを指す。
解答3:× 解説: 誤りです。 定義が逆です。 FAランクは「大きく変形しても(降伏しても)耐力を維持し続ける、非常に粘り強い(靭性が高い)」部材を指します。 一方、FDランクなどは「変形能力が乏しく、すぐにせん断破壊して耐力を失う(脆い)」部材です。耐震設計では、FAランクのような粘り強い部材を多く使うことで、建物全体のエネルギー吸収能力を高めることを目指します。
保証設計~「安全な壊れ方」を設計するRC・S造の検討項目
問題1 保有水平耐力計算における「保証設計」とは、大地震が発生しても建物が一切損傷しないこと(弾性範囲に留まること)を保証するために、部材の強度を割り増して設計する手法のことである。
解答1:× 解説: 保証設計が保証するのは「無損傷」ではなく、「安全な壊れ方(靭性的な崩壊メカニズム)」です。大地震時には部材の損傷(降伏)を許容しますが、その際に脆性的な破壊(せん断破壊など)が起きず、粘り強い曲げ破壊が先行するようにコントロールすることを目的としています。
問題2 RC造の保証設計において、柱や梁が曲げ降伏(靭性的な破壊)する前に、脆性的な「せん断破壊」が起こらないようにするため、計算上で想定される最大せん断力に対して、さらに材料強度のばらつき等を考慮した「割増係数」を乗じた力に対して安全であることを確認する。
解答2:〇 解説: 曲げ降伏はエネルギーを吸収する良い壊れ方ですが、せん断破壊は一瞬で耐力を失う危険な壊れ方です。「曲げ降伏した瞬間の力」よりも「せん断耐力」の方が確実に大きくなるように、割増係数を用いて余裕を持たせる検討を行います。
問題3 鉄骨造(S造)の露出柱脚において、柱本体が降伏する前にアンカーボルトが先に降伏・伸びてしまうような仕様(柱脚の破壊が先行する形式)となった場合、その柱は即座に靭性のない「FDランク(脆性部材)」として扱われ、保有水平耐力の計算において耐力を期待できなくなる。
解答3:× 解説: S造の露出柱脚において、柱脚(アンカーボルト等)が先行して降伏する場合、エネルギー吸収能力は低下しますが、即座にFDランク(耐力ゼロ等)になるわけではありません。 この場合はペナルティとして、必要保有水平耐力(Qun)を「0.05割り増し」することで安全性を確保する規定となっています。FDランクになる他の脆性破壊(部材の破断など)とは扱いが異なります。
付着割裂破壊の原理と対策(RC鉄筋の付着・基本編)
問題1 付着割裂破壊は、大地震時に鉄筋に過大な引張力が作用することで、鉄筋とコンクリート間の付着応力度が高まり、鉄筋に沿ってコンクリートが割裂(ひび割れ・剥落)する現象である。これが生じると、鉄筋が降伏してエネルギーを吸収する前に耐力が低下してしまうため、建物の靭性(粘り強さ)を著しく損なう脆性破壊となる。
解答1:〇 解説: 付着割裂破壊は、鉄筋がコンクリートを「内側から押し割る」ような破壊形式です。これが発生すると、鉄筋とコンクリートの一体性が失われ、鉄筋が降伏点まで引っ張られることなくスッポ抜けるような状態になるため、期待していた粘り強さ(靭性)が発揮できなくなります。
問題2 保有水平耐力計算(安全性の検討)において、大梁の付着割裂破壊を検討する場合、梁は地震時に塑性ヒンジ(曲げ降伏)を形成してエネルギーを吸収することが期待される部材であるため、解析で得られた「存在応力」ではなく、鉄筋が降伏するまで付着が健全であることを保証する「降伏強度」を用いて検討を行うのが基本である。
解答2:〇 解説: 梁のように「ヒンジ化させたい=鉄筋を降伏させたい」部材の場合、鉄筋が降伏する前にコンクリートが割れてしまっては意味がありません。そのため、計算上の応力(存在応力)が小さくても、鉄筋がフルパワー(降伏強度)を発揮しても耐えられるかどうかを確認し、靭性を保証する必要があります。逆に、基礎梁などヒンジ化させたくない部材では、存在応力での検討を選択する判断もあり得ます。
問題3 計算の結果、付着割裂破壊に対してNG(耐力不足)となった場合、主筋の断面積を変えずに耐力を向上させる対策として、主筋の径を太くして本数を減らすことは、鉄筋一本あたりの表面積が増えるため、付着に対して有利(安全側)な変更となる。
解答3:× 解説: 同じ断面積を確保する場合、「太い鉄筋を少なく」使うよりも、「細い鉄筋を多く」使う方が付着には有利です。 細い鉄筋の方が、断面積に対する周長(表面積)の比率が大きくなるため、付着応力度を分散させることができます。また、太い鉄筋はかぶりコンクリートを押し広げる力が強くなるため、付着割裂に対しては不利になります。
RC柱梁接合部がNGに!背景を踏まえた3つの実務的対応策
問題1 RC造の柱梁接合部のせん断耐力が不足(NG)した場合、接合部内の帯筋(フープ筋)の量を増やすことは、計算上のせん断耐力を直接向上させるための最も効果的な対策となる。
解答1 :× 解説: 現行の評価式において、帯筋(フープ筋)を増やしても接合部のせん断耐力数値は上昇しません。 帯筋は、ひび割れ発生後のコンクリートの拘束や、靭性を確保するために必須(0.2%〜0.3%以上)ですが、計算上のせん断耐力を上げる要因ではないことを覚えておきましょう。耐力を上げるには、コンクリート強度(Fc)や部材の断面サイズを大きくする必要があります。
問題2 保有水平耐力計算において接合部がNGとなった場合、接続する梁の主筋本数を(許容応力度計算が満足する範囲で)減らすことは、接合部に入力されるせん断力を低下させるため、有効な解決策の一つとなる。
解答2 :〇 解説: 接合部の検討には、梁などが降伏した時の力が用いられます。つまり、梁の鉄筋量をあえて減らすことで、のように梁が降伏する際の荷重(接合部への入力)を抑えることができ、結果として接合部の破壊を防ぐことができます。
問題3 接合部の検討でNGとなった場合、その接合部に取り付く部材は靭性の低い「FDランク(脆性部材)」として扱われることになるが、その場合でも構造特性係数(Ds値)を割り増して必要保有水平耐力を満足させれば、法的に適合した設計とすることができる。
解答3 :〇 解説: 接合部NG=即不適合、ではありません。 その部分が脆性的な挙動を示す(FDランク)ことを前提として、建物全体に必要な耐力(Ds値)を大きく設定し、それでも保有水平耐力が足りていれば設計として成立します。ただし、靭性型の建物(純ラーメンなど)ではDs値が大きくなりすぎるため現実的でないことが多く、強度型の建物向けの最終手段と言えます。
⑦現場(監理・施工)
RC梁の開口補強~既製品スリーブの計算チェックと図面での注意点
問題1 RC梁に複数の貫通孔を設ける場合、それぞれの孔による応力集中が干渉し合わないようにするため、孔の中心間距離は「孔径(平均径)の2.5倍以上」を確保することが構造設計上の原則とされている。
解答1 :× 解説: 孔の中心間距離は、原則として「孔径の平均の3倍以上」確保する必要があります。 また、孔径のサイズ制限(梁せいの1/3以下)などを確認する際は、スリーブの「呼び径(75φなど)」ではなく、実際に埋め込む管の「外径(ボイド管やスリーブ管の実寸)」で判断する必要がある点も注意が必要です。
問題2 既製開口補強金物の選定において、確保すべき耐力(有孔梁せん断終局強度)は、原則として「穴が開いていない状態の梁(無孔梁)が本来持っているせん断耐力」、もしくは「梁が両端で曲げ降伏した時に生じるせん断力」のいずれか小さい方の値を上回るように設計する。
解答2 :〇 解説: 開口補強の目的は、孔を開けることによって「梁が弱くならないようにする(無孔梁と同等以上)」か、あるいは「梁が曲げ降伏するまでせん断破壊しない(脆性破壊を防ぐ)」ことを保証することです。これらを比較し、設計目標となる耐力を設定します。
問題3 既製品の開口補強金物を使用する場合、メーカーの認定計算書で「OK(適合)」の判定が出ていれば、その耐力は保証されているため、柱際などの「ヒンジ領域(梁端から梁せいDの範囲)」に開口を設ける場合であっても、構造設計者が個別に配置の是非を検討したり、在来補強への変更を検討したりする必要はない。
解答3 :× 解説: メーカーの計算書はあくまで「その位置でその金物を使った場合の耐力」を示しているに過ぎません。 構造設計の原則として、塑性化が予想される「ヒンジ領域(梁端D範囲)」への開口設置は避けるべきです。やむを得ず設置する場合は、既製品計算の結果に関わらず、設計者がリスクを判断し、開口位置をずらすか、靭性を確保できる在来補強(ダイヤレンなど)を検討する必要があります。
配筋検査の役割とは?施工管理との違いと見るべきポイント解説
問題1 設計監理者が行う配筋検査の主たる目的は、施工者が行う自主検査と同様に、現場にある全ての鉄筋の本数やピッチを一つ一つ実測し、施工図通りに組まれているかを網羅的にチェックして施工ミスをゼロにすることである。
解答1 :× 解説: 全ての鉄筋を網羅的にチェックするのは「施工者(品質管理)」の役割です。 設計監理者の役割は、施工者が正しく検査を行っているかを確認した上で、設計図書(意匠・構造図)と照合し、「設計意図」が反映されているかを確認することです。全てを数えるのではなく、構造的に重要なポイントを重点的に確認する視点が必要です。
問題2 現場で配筋検査を行う際、メジャーで寸法を測る前に、まず全体を眺めて配筋の「整然さ」や「パターンの乱れ(相対的な違和感)」を探すことは、施工者の管理レベルを把握し、重点的に確認すべき箇所を効率的に見つけるための有効な手法である。
解答2 :〇 解説:人間の目は、絶対的な寸法よりも「並びの乱れ」に敏感です。全体を俯瞰し、整然と並んでいるか、不自然にピッチが広い箇所はないかといった「違和感」を最初に見つけることで、限られた時間の中で効率的かつ効果的な検査が可能になります。
問題3 大梁の主筋などの重要な鉄筋を確認する際は、断面での本数確認だけでなく、その鉄筋一本を選び、「どこから始まって、どこで継がれて、どこで終わっているか(定着)」という「線」としての連続性を追跡することで、設計した力の伝達経路が確保されているかを確認することが重要である。
解答3 :〇 解説: 鉄筋は「点(断面)」ではなく「線」で機能します。 継手の位置が応力の小さい箇所にあるか、端部の定着長さが確保されているかなど、一本の鉄筋を始点から終点まで目で追いかけることで、図面上の「力の流れ」が現場で実現できているかを検証することができます。
コンクリート管理の基本~押さえるべき数値とその背景
問題1 コンクリートの圧縮強度試験に用いる供試体は、1回の試験(打込み工区ごと等)につき原則として「3本」採取することとされているが、これは予備を含めた数ではなく、3本すべての結果を用いて平均値を出すなど、コンクリートの不均質さによる強度のばらつきを統計的に処理し、信頼性を確保するためである。
解答1 :〇 解説: コンクリートは不均質な材料であるため、1本の供試体だけでは偶然その部分が強かったり弱かったりする可能性があります。3本採取して試験を行うことで、極端なデータの偏りを防ぎ、そのロットの代表的な強度として信頼性を確保することができます。
問題2 コンクリートの「単位水量」の上限値(原則185kg/m³以下)が定められている主な理由は、水が多すぎるとコストがかさむという経済的な理由によるものであり、強度やひび割れ抵抗性といったコンクリートの品質自体には直接的な悪影響は及ぼさない。
解答2 :× 解説: 単位水量の制限は「品質確保」のためです。水が多すぎると(水セメント比が大きくなると)、硬化後に余分な水分が抜けた空隙が増え、強度が低下するだけでなく、乾燥収縮によるひび割れが増加したり、中性化しやすくなったりして耐久性が著しく低下します。
問題3 寒冷地以外であってもコンクリートに「空気量(標準4.5%)」を持たせる主な理由は、微細な気泡を連行することでコンクリートのワーカビリティ(施工性)を改善する効果に加えて、将来的な気象変動等による凍結融解作用に対する抵抗性を確保し、コンクリートの耐久性を高めるためである。
解答3 :〇 解説: AE剤によって連行された微細な空気泡は、コンクリート内部の水分が凍結した際の膨張圧を吸収するクッションの役割を果たします。これにより、コンクリートがボロボロになる凍害を防ぐことができます。また、ボールベアリングのような働きで流動性を高める効果もあります。
⑧PC設計の基本
PC設計の基本~「PCは高い」は本当?PC設計の基本と可能性
問題1 プレストレストコンクリート(PC)構造の基本原理は、コンクリートの「圧縮には弱いが引張には強い」という材料特性を補うため、あらかじめPC鋼材によって部材に強力な「引張力」を与えておくことで、ひび割れを防ぐ技術である。
解答1 :× 解説: コンクリートは「圧縮に強く、引張に弱い」材料です。 PC技術は、あらかじめ部材に強力な「圧縮力(プレストレス)」を与えておくことで、荷重によって生じる引張応力を打ち消し、コンクリートが引張られない(ひび割れない)状態を維持する技術です。
問題2 PC構造の設計手法の一つである「フルプレストレスト構造」は、常時の荷重状態において、コンクリート断面内に引張応力が一切発生しないように十分なプレストレスを与える手法であり、水密性が求められる水槽や原子力施設などで採用される。
解答2 :〇 解説: フルプレストレストは最も理想的な状態ですが、導入するプレストレス量が大きくなるためコストもかかります。そのため、一般的な建築物では、ある程度の引張応力やひび割れを許容する「パーシャルプレストレスト構造」や「PRC構造」を選択することで、性能と経済性のバランスを取るのが一般的です。
問題3 PC構造は、大地震時に大きな変形が生じても、高強度のPC鋼材が広い弾性範囲を持っているため、地震力が除かれると元の位置に戻ろうとする「原点指向型」の復元特性を示し、一般的なRC造やS造に比べて残留変形が小さくなる傾向がある。
解答3 :〇 解説: PC鋼材は降伏点が高く、バネのように強い復元力を持っています。この力により、地震で建物が傾いても、揺れが収まれば元の位置に戻ろうとする力が働き、残留変形(傾いたままになること)を小さく抑えることができます。これは震災後の継続使用において非常に大きなメリットとなります。
PC設計の基本②~現場緊張PC梁の検討手順と一貫計算の連携方法
問題1 PCメーカーに梁の検討を依頼する際、最低限必要な情報(応力図や断面サイズなど)さえ提供すれば、メーカー側で最適なPC鋼線の配置を決定してくれるため、取り付く柱の配筋情報や、直交する大梁の鉄筋情報までを初期段階で共有する必要はない。
解答1 :× 解説: 計算上は成立しても、現場で「定着具が柱筋に当たって入らない」「シース管が直交梁とぶつかる」といった問題が頻発します。初期段階で周辺の配筋情報を共有することで、これらを回避した現実的な配置計画が可能になり、手戻りを防げます。
問題2 PC梁にプレストレスを導入することで発生する二次応力(不静定応力)を一貫計算モデルに反映させる際、PC梁のスパン途中に直交する大梁が接続しているような架構では、PC梁の変形(上向きの反り)を忠実に再現するために、節点荷重ではなく「部材荷重(等価外力)」として入力する手法が適している。
解答2 :〇 解説: PC梁の変形(反り)を考慮しない「節点荷重」方式だと、接続する直交梁が一緒に持ち上げられる変位が無視され、直交梁に現実とは異なる過大な応力が計算されてしまうリスクがあります。スパン途中に接続がある場合は、変形を再現できる「部材荷重」方式が必須です。
問題3 納まりの不具合などでPCメーカーに再検討を依頼するために、一貫計算ソフトから再度応力データを出力して送付する場合、前回メーカーから提示された「応力補正用の特殊荷重」がモデルに入力されたままの状態(二次応力込みの応力)でデータを渡すのが、情報の整合性を保つ上で正しい手順である。
解答3 :× 解説: 特殊荷重(二次応力)が入ったままのデータを渡すと、メーカー側でさらにその応力に対してプレストレスを計算することになり、二次応力が二重計上されてしまいます。再検討依頼時は、必ず特殊荷重を削除した「プレストレスなし(素の状態)」の応力データを渡す必要があります。