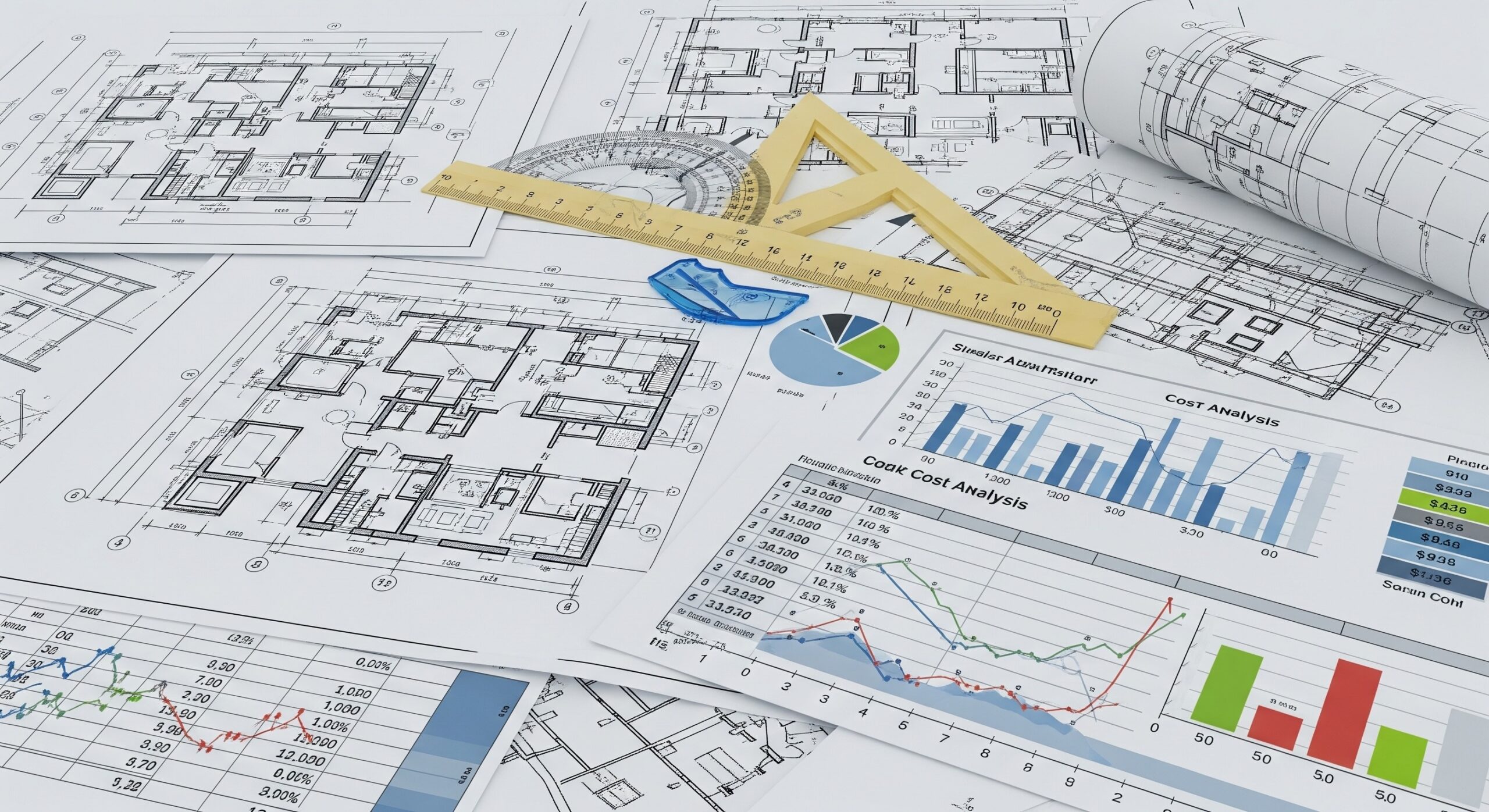近年は物価上昇や労務不足による工事費高騰によってプロジェクトの中止や縮小といった事象が非常に多くなっています。建築を実現するためのコストコントロールの重要性は日々高まっています。。
設計内容とコストは常に一体に考えていく必要があります。
今回の記事ではコストと密接な関係にある積算について書いていきます。
①積算とは~官庁工事積算と民間工事積算の違い
積算は官庁工事と民間工事で役割が違ってきます。まずはその役割の違いを整理します。
・官庁工事積算
設計業務の中で行う積算業務というのは主に官庁工事になります。こちらの業務で作成した内訳書というのは、工事費を決定するためというよりも工事費の予算を決定するための根拠資料となります。もう少し言うと税金の使い方の妥当性を示す根拠となります。
なので積算の方法は積算基準で定められた方法になります。単価についても、まずは各自治体で設定している単価を使用することになります。
次に優先されるのが以下のような公表されている物価本と言われるものに掲載されている単価が採用されます。
材料系:建設物価、積算資料
施工系:コスト情報、施工単価
以上のもので一般的な資材費、労務費は単価を決めることができますが、特殊なものになると専門業者(メーカーなど)から見積もりを出してもらうことになります。ここでも公平性が必要になるので数社(基本は3社)から見積もりを取得します。
この見積もりは、一般的に掛け率という係数を掛けてNET価格(実勢価格)に補正して使用します。これは、設計価格が、実際に施工者と契約する価格よりもやや高く設定されることを想定しているためです。
経費率についても積算基準で算出方法が決められており、工事規模や工期を変数として算出することができます。
このように根拠が重要になってくるので、工事項目ごとの内訳書の他に別紙明細、代価表、見積り比較表といった単価の根拠を作ったページが付いてきます。
積算を行う図面に対しての価格の根拠となるので図面の仕様や数量との整合が大事になります。そのため設計者で図面との整合を確認することになります。
・民間工事積算
こちらは施工者が入札するための金額を決めるために行う積算のことを示します。基本的な数量の拾い方(図面から数量を算出する作業を『拾い』と呼びます)は官庁と同様ではありますが、厳密には規定されません。また単価についても会社によって調達力も異なるので、当然単価も異なってきます。
会社の調達力を踏まえて単価を決定すればよいし、見積もりを取得する業者の数についても特に規定はありません。
官庁案件への入札の場合には、内訳書の単価部分は除かれた数量内訳というものが公開されるので、その場合には単価だけを決めれば内訳書を完成させることができます。
経費率についても工事の条件や会社としての利益も踏まえて自由に決定できます。
このように官庁積算の内訳書とは役割も違ってくるのでチェックをするときに視点も変わってきます。項目の抜け漏れがないことの確認は同じですが、単価の妥当性についてもチェックする必要があります。
②積算を知れば図面も書ける
図面を書き始めた時にほとんどの人がぶつかる壁が、何をどこまで書けばよいのかという壁だと思います。
その1つの目安になるのが、積算ができる図面になっているかどうかです。きちんと数量が明確にわかるような寸法が書かれているのか?単価を決めるための情報となる仕様が書いてあるのか?ということを考えると図面に必要な情報というのが見えてきます。
内訳書がどのように作られているのかがわかっていると、上記のことも考えることができるので図面に必要な情報を盛り込んでいくことができます。
最低限の図面を作るとき、締め切りに追い詰められたときに拾える情報、積算できる情報を優先的に表現するように言ったりもします。それくらいにコストに関わる内容を表現することは重要ということです。
積算が図面にコストに関する情報を要求するのと同様に、構造計算も図面に特定の情報(寸法、仕様、部材数など)が記載されていることを求められます。このように、積算と構造計算は、どちらも図面に記載すべき内容を決定する上で重要な役割を担っています。
③積算情報を概算に活かす
コスト感覚を身に着けていくためにも、内訳書を分析して情報をストックしていくことが不可欠です。
あくまでも概算では実施図が揃っているわけではないので、積算のようにすべてを細かく拾って、単価を設定するわけではありません。序盤からそのような積み上げから入ると抜け漏れが出て失敗する可能性が高くなります。
過去の面積等を基準とした歩掛りを使って、特殊要因分だけを補正することで大きく乖離しません。
ただし公表されている単価について最新情報を常に意識しておく必要があります。刊行物や積算基準は時差が生じるので、実勢価格と必ずしも一致しているとは限りません。
数量については最近では過去の歩掛りだけに限らず、一貫計算モデルを入力すれば積算機能で数量を把握することもできます。ただし、そこでも細かなところまでは入力しないので、計算モデルでの数量と、最終的な積算での数量が何割程度多くなるのかを把握しておくと概算が楽になります。
また細かな項目については、主要数量に対する単価をある程度割り増して見込んでしまった方が手間も少なく精度も高くなります。
ここに書いた内容は一例でしかないので、使いやすい歩掛り、ある程度普遍性がありそうな歩掛りを試行してみることがコスト感覚を身に着けるためにも大切かもしれません。