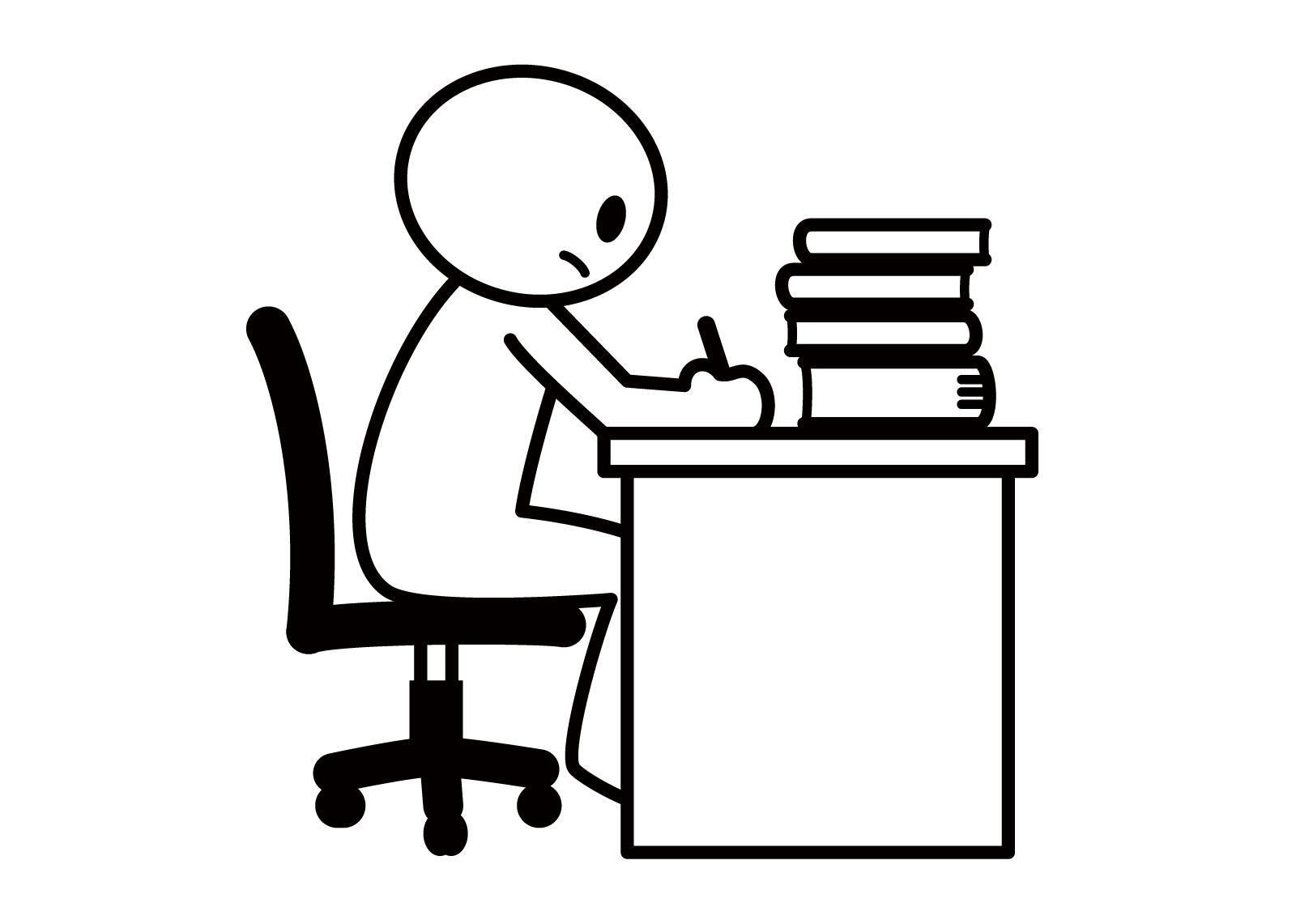どんな仕事でも、「調べる」という行為に多くの時間を費やします。特に専門職である建築構造設計では、無数の法的基準や学会指針、過去の事例など、膨大な情報と向き合わなければなりません。
これらをすべて暗記するのは不可能です。
ここで重要になるのが、学校の勉強と仕事の決定的な違いを理解し、「暗記」から脱却することです。仕事で求められるのは、テストで点を取ることではなく、必要な情報を素早く見つけ出し、概要を掴み、次のアクションに移るスピード感です。
この不可欠な「調べる力」を身につければ、あなたの仕事の成果は確実に向上します。今回は、そのための具体的な3つのポイントをご紹介します。
①仮説を立て、検索を「作業」から「検証」に変える
仕事で直面する課題は、試験勉強のように答えがそのまま書いてあることは稀です。教科書のように範囲が限定されているわけでもなく、情報の海の中から答えの糸口を探し出さなくてはなりません。
ここで意識すべきなのが、「仮説を持って調べる」ことです。
仮説がないまま検索を始めると、情報に溺れてしまい、「時間をかけたのに、結局何も分からなかった」という事態に陥ります。
仕事ができる人、課題解決が上手い人は、未知の課題に遭遇した時、まず「おそらくこうではないか?」という仮説を立て、それを検証するために情報を探しにいきます。
言われれば当たり前のことではあるので、仮説を持ってそれを検証する意識で情報を調べていくということを繰り返していけば割りと簡単に身に付くのですが、逆にやらないことにはいつまで経っても身に付かないで、差が付きやすいポイントでもあります。
②点ではなく「面」で捉え、周辺知識を蓄える
何かを考えるにも、思考の起点となる知識や情報が必要です。
世の中に存在する「全く新しいもの」はごく僅かで、そのほとんどは既存の知識の「組み合わせ」や「応用」です。この引き出しがなければ、ゼロから考えても時間ばかりが過ぎてしまいます。
多くの人は「考える」こと自体に重きを置きがちですが、本当に深く思考すべきタイミングは、ある程度の情報(材料)が揃ってからです。
「調べる」ことを習慣にすると、一つの事柄を調べているうちに、別の課題のヒントを発見するなど、点と点がつながり、知識が「面」として広がっていく感覚が得られます。
調べることが習慣になってくると、他の課題で気になっていたことのヒントになるものを見つけるなど、知りたいと思っていたこと以上の成果が得られるようになってきます。
そうなれば、全体的に答えを出すスピードも成長のスピードも速くなっていきます。
③「自分で答えに辿り着ける」という自信と武器を得る
「調べる力」が身につくと、仕事で手が止まる時間がほとんどなくなります。人に確認しないと進めない事柄が、ごく一部の高度な判断だけになるからです。
そして何より、出典のある書物や事例から自分で得た知識は、社外にも通用する強力な「武器」になります。人から「聞いただけの話」は、根拠が曖昧で、対外的な説明には使えません。
特に専門的な技術内容は、一度出典元のある「書き言葉」でインプットし直さない限り、理解が浅いままになりがちです。これでは、応用も効かず、相手に伝わる説明はできません。
最初は、人に聞いてしまう方が早いと感じるでしょう。何事においても中々一度で覚えることは難しいので何度か振り返ることになりますが、人に何度も同じことを聞くことはできませんが、書いてあることは何度でも反復できます。
「自分で答えに辿り着ける」という感覚と成功体験を積み重ねることが、どんな課題にも臆せず立ち向かえる自信を育むみます。
まとめ 若手を育てる立場の方へ
最後に、人材育成の観点から。 若手に仕事を教える際、つい「答え」や「考え方」そのものを与えてしまいがちです。しかし、本当に相手の成長を願うのであれば、「答えの探し方」「調べ方の勘所」を伝え、本人が自力で答えに辿り着けるようサポートすることが、独り立ちへの一番の近道になります。