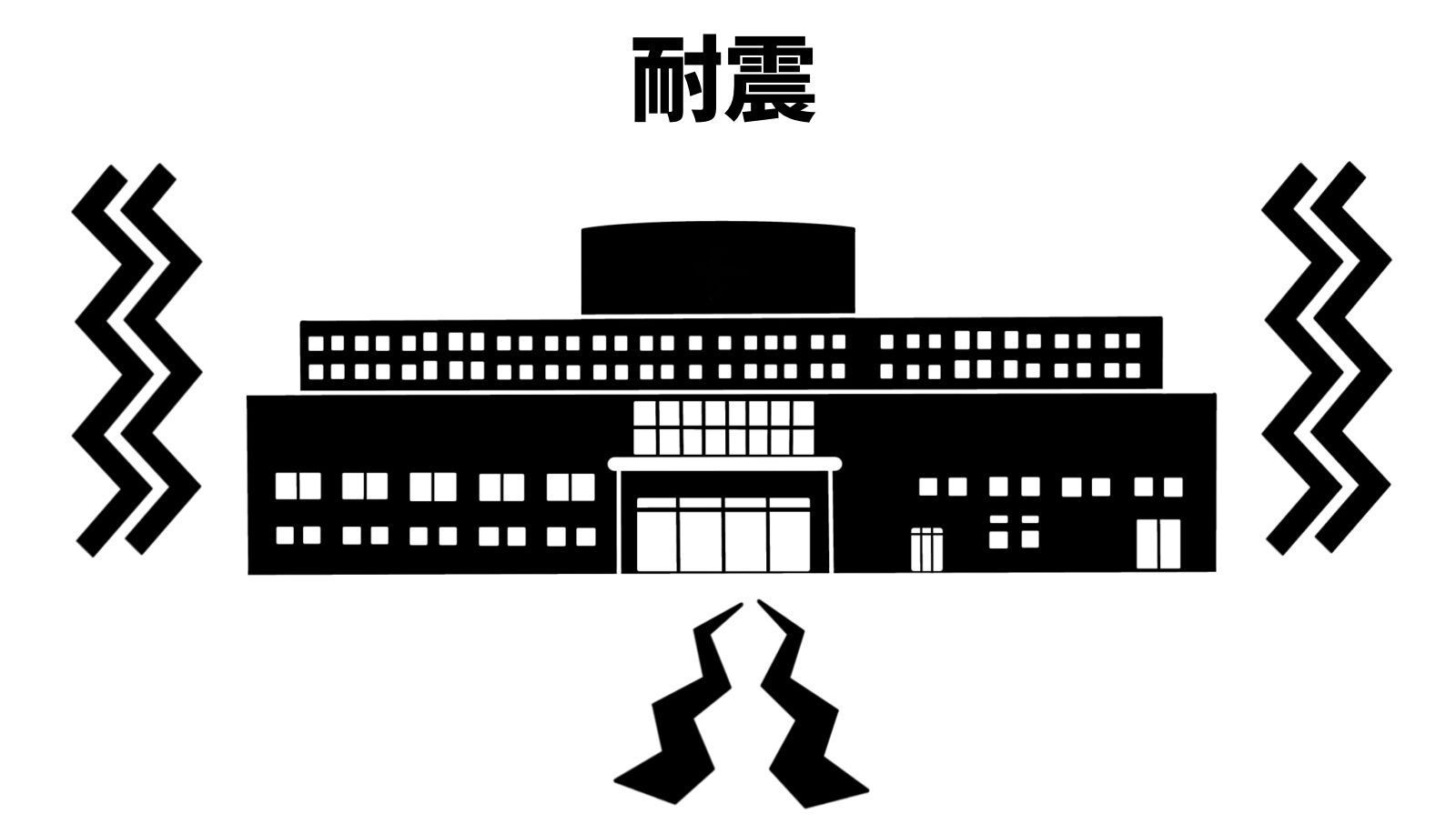建築の構造設計者はエンジニアの中でも法的制約を強く受ける方だと思います。
法の意図を踏まえつつ、技術的にも問題ないという最適解を出す必要があります。
法を守ることばかりを考えていると、本当に実現したいものから離れていってしまったり、逆に技術的なことばかりを考えていると申請が通らないといったことになってしまうため、両方の趣旨に沿ってバランスよく設計をしていくことが求められます。
法適合と耐震性能はイコールではないので、本質を理解して法と技術を繋ぐことが設計者の役割と言えます。今回は法と技術を繋ぐための基本認識を書いていきます。
①各種基準の階層を把握する
構造計算をする上でも、色々な基準があります。
基準といっても、建築基準法、施行令、告示といった法的拘束性があるものから、建築学会関連の基準といった基本的には守る必要がありますが法的拘束性のないものといった形で幅があります。
法についてもただし書きに適用させれば、他の解釈が適用できるといったものもあります。こういった色々な階層があるものの大きな体系を頭でイメージしているかどうかで、課題の捉え方の深さが大きく変わってきます。
よくやりがちなこととしては、都合の良いところや理解できたところのつまみ食い状態になっていて解釈に抜けが合ったり、思い込みで都合の良い方に解釈することです。
法や基準は一見、複雑に見えますが、ルールがしっかりしている分、そのルールを最初に理解すれば強い武器になります。根拠が明確になるので自信を持った発言や判断ができるようになってきます。
②やみくもに適用させようとしていないか!?
この体系を理解しないとどの内容にもやみくもに適合させようとしてしまうということがあります。特に構造計算プログラムを使っているときにその問題は起こります。
参考:構造計算プログラムに使われない付き合い方
当然ではありますが、すべての法や基準を完全にマスターした上で、構造計算プログラムを使い始めるわけではないので、使用者が理解できていない基準に対しても満足しているのかを検討してくれます。
適合していないときには①に示したような階層に丁寧に分類をしてくれるわけではないので、結果として“適合していないということ”だけをワーニングメッセージとして伝えてくれます。
なので、計算を満足させることばかりに夢中になってしまい、法や基準での位置づけを把握しようとしないと、適合させる必要のないことに対して部材を変更して満足させたりするなど実現したい建築から遠ざかるような変更をすることが起こってしまいます。
③構造設計ルートの目的は何か
耐震基準は、1978年の宮城県沖地震をきっかけに大きく改正され、新しい耐震基準は1981年6月1日に施行されました。その際に構造設計ルートが始まりました。
実務をしているとこの構造設計ルートにどうしても思考が寄っていってしまっているということに気づく必要があります。
構造設計ルートは簡単に言うと審査や設計を誰でも簡単にできるようにして、社会活動を円滑に動かしていけるためのものだと考えると内容の理解が早まると思います。
構造計算の細かな中身を確認(理解)していなくても、限られた項目を確認することで耐震性能が確保されていると判断できるようになっています。
※ここでいう耐震性能とは建築基準法を満足しているということであって本当の耐震性能はそんなに簡単に示せるものではないということの理解が重要になります。
④実際の被害状況と重ね合わせることが重要
構造設計ルートに示されている項目はこれまでの地震被害状況から、損傷が少なかった建物(例えば、RC造であれば壁が多い、S造であれば規模が小さいなど)と被害が大きかった建物(例えば、変形が大きい、剛性のバランスが悪いなど、脆性破壊がしやすい仕様がある)の特徴を数値化して条件化しています。
なので、これを満足していれば安全というところで思考が止まってしまうことは問題ですが、実際の被害から導き出された項目なので、耐震性を考える上で重要な要素ではあるということは認識する必要はあります。
いきなり細かい数値を全部覚えることよりもまずは設計ルートで示されている項目がどのように変化すると安全側なのか、危険側なのかを判断できるようになるという視点で見ると、理解が早まります。概要さえ理解できていれば必要な時に詳細の内容は調べて使うことができます。
⑤構造設計ルートありきの設計者になってはいけない
建築工事を着工するためには建築基準法に満足していることを審査機関に確認してもらって確認済証を発行してもらう必要があります。
設計実務を経験したことがある方には痛いほどわかることですが、着工の直前までに済証が発行されないととてもドキドキします。
その高い圧力の前では、構造設計ルートに沿って構造設計をすることが当たり前になり、思考の方向性がいつの間にか構造設計ルートに適合することが目的になり、構造設計ルートに適合する=耐震性が十分な建物という認識に変わっていくことになります。
そうなってしまうと前述したようにやみくもに法適合することに陥ってしまいます。
法適合と十分な耐震性は完全なイコールではありません。
耐震性について深い理解があってから、この構造設計ルートに対峙すれば法の趣旨も理解しつつ実現したいことをどのように実現できるかを、法と技術の間のちょうどよい落としどころを見つけていくことになります。
しかし、ほとんど耐震設計について知らない若手がいきなり対峙することで誤解が生まれます。こういった構造設計の背景を伝えた上でどのように構造設計ルートと付き合っていくかを示していくことが人材育成上はとても重要になってきます。
⑥法も技術も統合することが設計者の役目
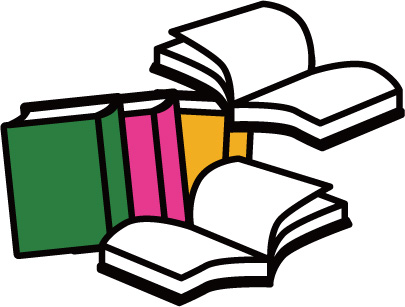
法と技術的な見解が完全に相反するわけではありませんが、どちらも完全ではないので、一品生産の建築設計をしていく中では多少折り合いが上手くいかないことがありますが、それを解決することが、構造設計者の腕の見せ所でもあります。
あまり言い方がよくないかもしれませんが、構造設計者として本当に安全性のあるものを提供できるのであれば、法的に完全に黒でないのであれば、白と判断できる根拠を作ることに妥協をしてはいけません。
法の趣旨も理解しつつ、技術的な根拠も相手にわかりやすく整理できるくらいの理解があって初めて実現に近づくことができます。両者の関係を十分に理解して本当の安全性については、法に適合しているから大丈夫以外の言葉で語れるようになっていきましょう。