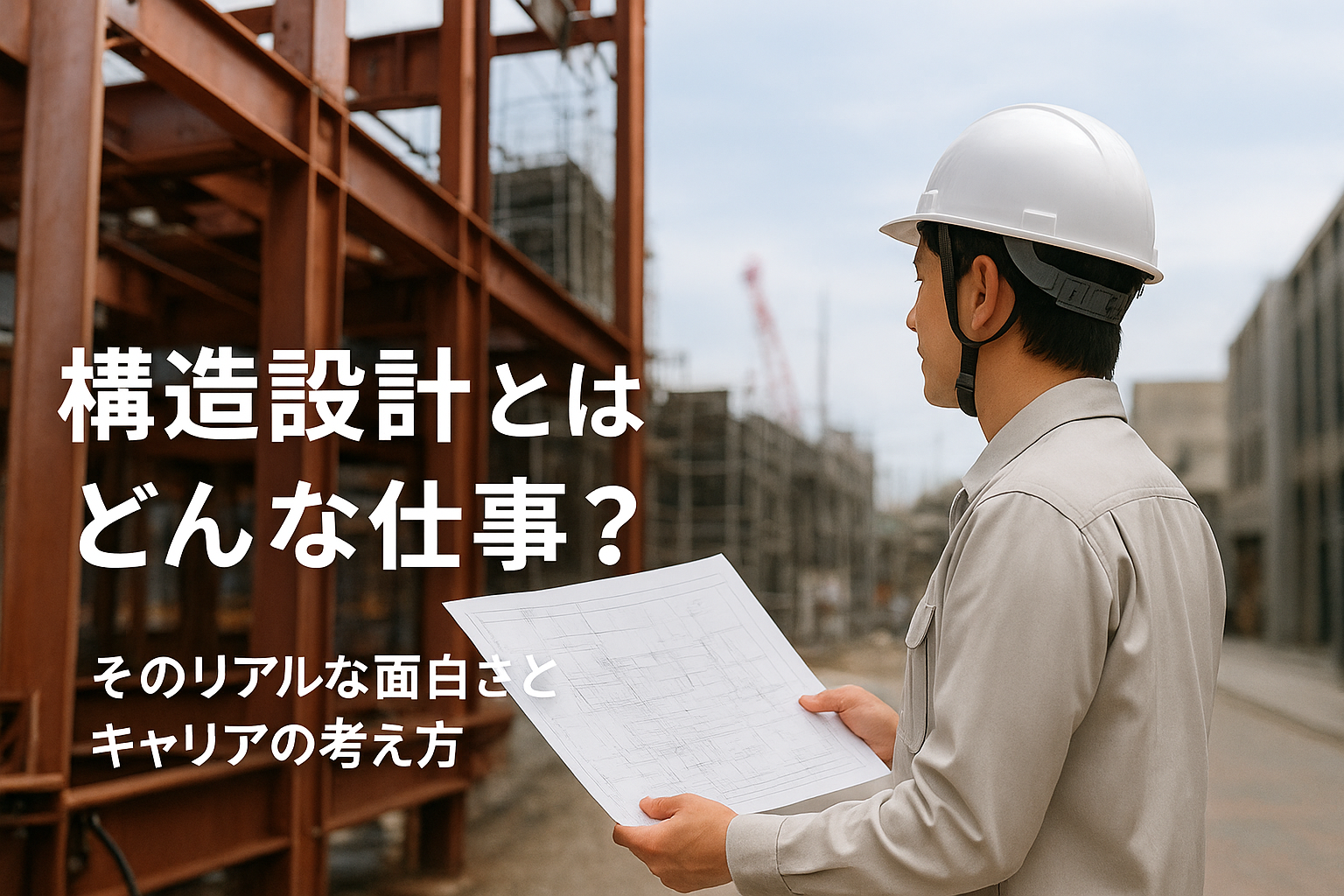夏のインターンシップも終わり、本格的に建築設計業界への就職活動を意識し始める季節になります。
「構造設計って、どんな仕事なんだろう?」 「自分に向いているのかな?」
そんな疑問を持つ皆さんに向け、今回は構造設計という仕事について、表面的な解説だけでなく、その本質的な面白さやキャリアの考え方まで、できるだけリアルな視点でお話ししたいと思います。この記事が、皆さんが構造設計という世界に挑戦するきっかけになれば嬉しいです。
①構造設計は計算だけ?構造デザインも小さなところから
構造設計の仕事のイメージとして意匠が決めた内容を成立させるために計算するだけ、と言われることもありますが、そんなことはありません。必ず構造からの提案や工夫は不可欠になります。
現在評価される建築というのは意匠・構造・設備(環境)の統合度の高さが不可欠です。意匠性を決定するに当たっても漠然とデザインするのではなく、構造の合理性や、モジュールなどの決定要因が必要になります。それを決定するための案を出すことが求められます。
「構造デザイン」というのは必ずしも構造が突出する必要はなく、よい建築をつくる、プロジェクトに見合った普遍的な技術を組合せて応用することが提案となりそれが構造デザインになります。
始めのうちは小梁の掛け方や間柱のピッチといった小さなところでも、こうすればもっと良くなるといったことを提案していくことも立派な構造デザインだと思います。
構造設計は計算を通して 決まった答えが出ると思われるかもしれませんが、そんなことはありません。複雑で未知の自然現象(風や地震など)を相手にする仕事です。答えらしいものは出てきますが、本当に抜けている視点はないかということを常に考え学ぶことが不可欠な工学です。
構造計算というのも、 未知の自然現象を「モデル化(簡略化)」という手法で定量的に扱えるようにしているに過ぎないので、細かなことにこだわる以前に大きな考え方を理解する必要があります。ちょっとした前提条件を変えれば答えも変わってくるし、その前提条件から組み立てていくことが構造計算になります。
1つの答えを出すというよりも、あらゆる答え、考え方がある中で 最も確からしい根拠をもって建物の安全性を説明する仕事、と言えるでしょう。
また構造設計は、建築設計の中では最もモノづくりらしい職種だと思っています。 躯体工事は仕上げと異なり、規模が大きいのが特徴です。敷地条件や施工条件を踏まえて、作り方までを一緒に考える必要があります。施工条件から決まってくる、構造提案というのもよくあります。
構造設計はお施主さんの意向だけでなく、自然現象や敷地条件といった多くの対象について知り、それらを統合して最適な答えを出していくとてもやりがいのある仕事です。
参考:幅を持って安全性をデザインしていく~完璧な正解を求めない
参考:建築構造設計の世界を知る~自然の未知をどう掴むか
参考:施工計画の知識で設計が変わる!現場で役立つ実践的思考法
②永遠のテーマ 組織設計・ゼネコン・アトリエの違い
これは建築学生にとって永遠のテーマかもしれません。組織設計、ゼネコン、アトリエ…。客観的な優劣はなく、「あまりにも違いすぎて、簡単には説明できない」というのが正直なところです。
誰かの「あそこは良いらしいよ」という言葉を鵜呑みにするのではなく、自分なりの判断軸を持つことが不可欠です。仕事上、横の繋がりはありますが、判断の軸や働き方は思っている以上に違うなと感じています。
もし、あえて本質的な違いを一つ挙げるとするなら、それは「自身が持てる裁量権の範囲」だと思います。これは、組織形態だけでなく、企業の規模を選ぶ際にも重要な視点になります。
例えばゼネコンには設計以外にも多くの部署があるため、設計部が担うのは設計に特化した範囲になりやすいですが、設計事務所では概算や施工検討も担当することがあります。また、大きな案件が多い職場では、担当業務がさらに細かく分担される、といった違いもあります。こういった体制の違いから、設計者としての判断の仕方が違ってきます。
そこに正解はありません。ぜひ、自分自身の特性と向き合って考えてみてください。
構造設計と一言で言ってもその中にも色々な役割があります。アイディアを出すことが得意な人、計算が得意な人、チームをまとめるのが得意な人、トータルで統合することが得意な人と様々な特性のプロがいて設計が成り立ちます。
この役割の中にも優劣はありません。組織形態によって裁量権が変わると言いましたが、これも裁量権が多ければいいとは限りません。なんでも自由にしてもらった方が力を発揮できる人もいれば、ある程度範囲を絞ってもらった方が力が出せる人と色々といると思います。学生時代にも自由研究と言われると何をやってよいかわからないけど、テーマを決めてもらった方が、高い成果を出せるのに似ています。
表層的に違いを理解するのではなく、具体的に働くイメージと重ねて説明会などにも参加することと、目立つ仕事だけが全てではなくて色々な役割のプロがいて成立していることを理解することが大切です。
参考:判断と決断を分ける技術~仮説思考で“判断”の質を上げる
参考:積算の基本~積算の視点から学ぶ、コストと図面の関係
③やりたいことが分からないのは当たり前!
絶対に覚えておいてほしいことがあります。それは、「最初の就職先がすべてではない」ということです。終身雇用は過去のものとなり、働き方は多様化しています。
就職活動の中で「何をやりたいか考えよう」と言われ、「やりたいことが分からない…」と悩む人もいるでしょう。でも、それは当たり前です。普通に考えてやったこともない仕事の中から「これがやりたい!」と一つを選ぶのは不可能に近いことです。食べたことのない料理の中から、どれが一番おいしいか決めるようなものです。
現実と乖離した妄想を膨らませて、入社後のギャップに苦しむよりも、まずは「わからないなりに、目の前のことに一生懸命になってみる」ことの方が大事です。
本来「やりたいこと」とは、「成果が出たから、もっとやってみたくなる」という関係にあると考えています。だからこそ、興味のあることをまずは成果が出るまで一生懸命やってみる必要があります。モチベーションが上がらないから成果が出ないのではなく、成果が出ないとモチベーションも上がりません。
仕事を始めたばかりの頃は、すぐに成果が出なくて当たり前です。けれど、一生懸命に取り組むことは誰にでもできます。がむしゃらにやってみる中で、初めて次に見える景色があり、仕事の本当の面白さにも出会えます。
この「一生懸命」とは、ただ時間をかけることではありません。
- 「わかったつもり」にならず、常に謙虚であること。
- 質問する前に「自分ならこう考える」という仮説を持つこと。
- 失敗を恐れず、自ら「決断」する経験を積むこと。
まずはどんなことでも良いので、一度「全力の注ぎ方」を覚えてみてください。それができれば、この先どんなに難しい課題にぶつかっても、きっと乗り越えられます。 成功するまでやり続ければ、そこに失敗はなく、すべてが成功への過程に変わります。
▼こちらの記事も見ていただけると選択肢は広がると思います。
【建築学生向け構造設計コラム】構造設計を支える業種(ファブ・メーカー・審査機関)の仕事内容と魅力を解説