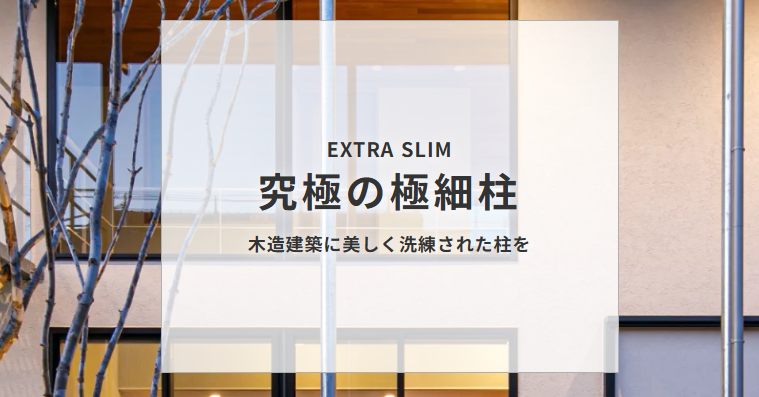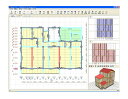今回の記事では、木造建築の構造設計に関する考え方を解説します。
詳しくは後述しますが、正直なところ私自身、木造の経験が豊富なわけではありません。
これまで基本的にはRC造やS造を中心に、時々混構造でSRC造の設計に携わってきました。そうした経験を積む中で、近年の木造普及の流れから数件の木造案件に取り組む機会がありました。
今後、木造の案件はさらに増えていくと思われます。そこで、RC造やS造である程度の構造設計を経験した方が、新たに木造に挑戦する際に戸惑うであろう「違い」や「留意点」について、自身の経験を基にまとめます。
①これまでの木造経験
まず、この記事を書いている人間の経験値をお伝えすることで、内容の信頼性を判断しやすくなるかと思います。
これまで木造の設計は4件経験しました。耐火構造、準耐火構造、そして耐火要件なしの全てのパターンです。建物規模はいずれも500~2000㎡程度でした。
構造計算ルートは、いずれも在来軸組工法のルート1またはルート2で、耐力壁や筋交いを設置して許容応力度計算を行うものが中心です。CLTは部分的に使用した程度に留まります。
ルート3(保有水平耐力計算)にも挑戦しようと検討しましたが、実現には至りませんでした。そのため、木造の保有水平耐力計算については、かじった程度の知識となります。
②中規模木造における設計思想(RC・S造との違い)
ここからは、RC造やS造の設計に慣れた方が特に意識すべき、木造特有の考え方や留意点を解説します。
数値のオーダー
・単位面積当たりの重量
RC造が12~16kN/m²(約1200~1600kg/m²)、S造が7~9kN/m²(約700~900kg/m²)程度であるのに対し、木造は3~5kN/m²(約300~500kg/m²)程度と非常に軽量です。
・地震時の変形
木造は耐力壁で耐震性を確保していても、地震時の変形量は大きくなります。目安として、中地震時に層間変形角1/150、大地震時には1/30近くに達することもあります。
エキスパンションジョイントのクリアランスを大地震時の変形量で設定すると過大になるため、中地震時の変形に対して決定することが一般的です。
特に準耐火構造等にする場合は、防火被覆の脱落を防ぐため、中地震時の層間変形角を1/150以下に抑える必要があり、注意が必要です。
参考:【違いに注意】層間変形角は2種類ある!【結論:準耐火構造等と構造計算】(いしいさんの建築基準法ブログ)
・壁の耐力(壁倍率)
片面で壁倍率が7倍(許容せん断耐力13.72kN/m)を超える壁は「高耐力壁」と呼ばれ、詳細な検討が求められます。通称「グレー本」では、この値を超えると適用範囲外となるため、設計者と確認審査機関の判断に基づき、耐力壁の周辺部材や接合部を適切に検討する必要があります。
『適用範囲外』とされていますが、グレー本には7倍を超える壁の仕様に関する詳細な計算方法も記載されています。
安全率の考え方
・柱の圧縮耐力
木造の柱は断面が小さいため、RC造やS造の感覚で階高を上げると、座屈による耐力低下が想定以上に大きくなるため注意が必要です。
・柱脚金物
既製品の集成材(105×210)柱脚金物の引抜き耐力は160kN程度が上限となるため、一つの耐力壁で確保できる壁倍率も自ずと制限されます。既製品の製材(120×240)柱脚金物の引抜き耐力は70kN程度が上限となります。連層耐力壁とする場合は、この点を踏まえた計画が不可欠です。
また、耐力壁の柱脚金物は、部材に生じる応力(存在応力)ではなく、壁自体の許容耐力によって設計します。これは、木造では耐力壁の性能を完全に発揮させることが最重要であり、柱脚金物が先行破壊するのを防ぐためです。
連層耐力壁の場合は、過剰な設計になる可能性があるので、上階の耐力壁によって生じる引抜き力は、検定比に応じて低減が可能です。
剛床仮定であるものの、RCスラブのような強固な面外剛性はないため、各耐力壁に想定以上の力が作用する可能性もあります。それらも踏まえ、存在応力ではなく壁の最大耐力で周辺部材を設計するという考え方は、木造設計の根幹と言えます。
製作金物を用いればより耐力を高める方法もありますが、壁倍率も同様なのですが、計算上は高い数値を算出することができても、実際にその耐力が確認できるのかを考える必要があります。実験ができれば確実ではありますが、それが難しい場合には申請がおりないということも考えられますが、それ以前に構造設計者として責任が持てるオーダーを事例などを参考に見極めましょう。
部材のサイズも金物のおさまりから考えて大きくする必要も出てきます。耐力を大きくしたい場合には柱を2列並べることで同じ耐力の構面を2つにするという方法もあります。
・冗長性(リダンダンシー)の考慮
在来軸組工法の構造計算では、梁はすべてピン接合、雑壁(構造計算に算入しない壁)は耐力ゼロとしてモデル化します。雑壁の耐力評価する方法は増えてはいますが、どこまで採用されているのかは把握しきれてはいません。単なる耐力の数値合わせではない判断が求められます。
実際にはピン接合と考えている部材も地震力を負担するため、その事実を踏まえて建物全体の安全性を判断する必要があります。梁の取り付き方によって引抜力の低減する係数はあります。
・接合部の設計(フェールセーフの思想)
長期荷重を支える部材の接合部は、経年による木材の乾燥収縮や荷重による変形で緩みが生じることを前提に接合部などを考える必要があります。。具体的には、ボルト等に頼るだけでなく部材を「乗せる」ような納まりにしたり、万が一の際に備えて複数の伝達経路を確保する「フェールセーフ」の考え方を取り入れたりします。
・面外方向への配慮
耐力壁間のスパンが長い場合、合板が取り付いている梁においても面外方向の応力への配慮が必要です。面外方向については風荷重の影響を受ける外壁部分が吹き抜けや階段に面している場合、柱や梁の断面が想定以上に大きくなることがあります。
参考:幅を持って安全性をデザインしていく
参考:余力をどのように設定する?過剰思考になっていない?
参考:剛床仮定とはなにか/非剛床の事例
参考:EXTRA SLIM(究極の極細柱)~木造建築に美しく洗練された柱を
③参考文献等
・木造軸組工法住宅の許容応力度設計(通称:グレー本)
木造設計のバイブル。確認審査の拠り所にもなります。まずこの本で調べ、記載がなければ他の文献を参考にするのが基本です。具体的な計算例と共に、計算方法や各種係数がまとめられています。
・中大規模木造建築物の構造設計の手引き(稲山正弘 著)
上記「グレー本」と一部内容が重複しますが、より詳細で専門的な内容が記載されています。
・集成材建築物設計の手引
集成材を用いた設計では必須の書籍です。構造設計だけでなく、集成材の基礎知識、防火・耐久設計についても網羅されています。
・JIS A 3301を用いた木造校舎に関する技術資料(文部科学省)
主に高耐力の柱脚金物に関する実験結果を確認するために使用しました。木造校舎の設計(構造・建築計画)、構造実験結果、モデルプランの設計例などが掲載されています。
・金物メーカーのカタログ
基本的な金物メーカーは、カナイ、タナカ、カネシンなど。納まり上、特殊な形状の金物を探す際には栗山百造も参考になります。また、接合に使うビスも重要で、様々な用途・耐力・長さの製品があるパネリード(シネジック)がよく使用されます。
いずれのメーカーもウェブサイトからカタログをダウンロードできます。