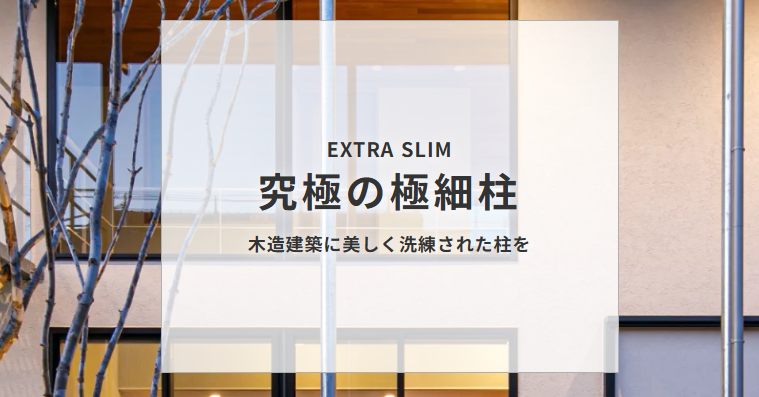構造設計をしていく中でも認定工法や技術評価を取得している工法を使用することはよくあると思います。使用する際に技術的な内容やコストについては調査・検討をすると思いますが、そういった工法ができるまでの背景を知る機会は中々ありません。
そこで今回の記事では構造設計をしつつ実際に技術評定を取得した製品を開発されている、アルキテック㈱代表取締役の大沼耕平さんにインタビューさせていただきました。
構造技術の習得に繋がる内容を中心に教えていただきました。
⓪プロフィール
アルキテック㈱ 代表取締役 大沼耕平

経歴
1978年 生まれ 長野県飯田市出身
2000年 株式会社構造工学研究所 入社
2008年 同 代表取締役
2016年 同 退社
2016年~ 合同会社構造設計アソシエイツ(現アルキテック) 設立 代表取締役
2021年~ 株式会社ハウジング・ソリューションズ 取締役
2023年7月~株式会社ガイアフィールド 取締役
2023年12月~フリードームデザイン株式会社 取締役
構造設計と並行して、鉄骨造柱梁接合部のノンブラケットRDJ工法、鉄骨造露出柱脚工法のフリーベース(SASST技術評価)、ベースプレート架台孔充填材の親子フィラー(SASST技術評価)、四号建築向け戸建て免震のM1式免震材料(法第37条大臣認定)などを開発。
①構造設計者として成長を実感した瞬間
Q1.構造設計者として力の流れが見えたきっかけは?
力の流れが見えるようになったきっかけというのはあまり意識した記憶がありませんが、構造設計を行う上では力の流れを意識することは非常に重要だと認識しています。
現在の計算プログラムは、モデル化から断面算定まで一気に処理してくれる便利さがありますが、断面算定だけを見て判断していると見落としが生じると思います。応力図をきちんと確認し、自分のイメージした力の流れと一致しているかを確かめることが、構造設計者としてとても重要だと感じています。
私も実体験として、応力図を見るだけで計算の誤りに気づくこともありますし、複雑な架構の場合は任意系プログラムでシンプル化した架構モデルを作って、応力を確認することがあります。そうすることで、モデル化の条件や荷重条件の根本的な誤りに気づくことができると思います。
Q2.独立したきっかけは?
最初に就職したのが小さな設計事務所で、所長も高齢だったので、仕事を覚えた後、転職をするか事務所を引き継ぐかという選択で悩みました。
私は当時30歳で経験も浅く、事務所の経営状態もあまり良くなかったのですが、若さゆえの自信とこれ以上は悪くなることはないだろうという楽観もあって、事務所の代表を受け継いだことが、独立の転機となりました。
今はその会社も譲り、新たに起業して現在に至っています。
②EXTRA SLIM(究極の極細柱)~木造建築に美しく洗練された柱を
Q3.技術評定のアイディアはどのようにして生まれる?
製品開発に重要なことは、使ってもらう人にとって便利なものをつくるということだと思います。会社の規模が小さいうちは、開発コストが抑えられ、かつニッチで模倣されにくいものだと更によいと思います。
極細柱EXTRA SLIMは、もともとは個別の物件で設計していた鉄骨柱ですが、鉄骨柱はプレカット工場では製作できないので、鉄工所に製作を依頼する必要があり、工務店にとっても手間のかかるものでした。
そこで、設計的に標準化し、製造まで弊社で担う仕組みを整えました。設計的に便利なのはもちろんですが、一本5万円程度からの価格なので、コスト面でもメリットを感じてもらえる製品になっていると思います。
Q4.技術評定を取得するために苦労したことと面白さとは?
個人的な思いとしては、技術評価は手間がかかるので、できればパスしたいものです。しかし、製品の信頼性を示す上では不可欠であり、他社との差別化としても重要だと考えています。その意味では技術的な面だけでなく、営業戦略上の必要性も大きいと感じています。
技術評価委員の先生方は当然ながらそれぞれ考え方や主義趣向が異なります。こちらの主張が技術的に正しいと思っていても、委員を納得させられる形で決着させる必要があります。
販売後に競争力のない商品を作る訳にはいかないので、販売戦略的に譲れる部分と譲れない部分を見極めることが重要だと感じています。
③今後挑戦していきたいこと
私自身の関心としては、設計の標準化が一つのテーマです。例えば鉄骨の継手はSCSS-H97によって大部分が統一化がされていますが、在来柱脚や柱梁接合部などは、設計者が試行錯誤しながらディテールを決めています。誰でも使える標準ディテールを提案し、自由に活用できるような形にしていくことに取り組みたいと考えています。
新しい開発についてもまだいくつかのアイデアを持っているので、会社の将来のためにも開発を進めていきたいと思っています。
構造設計業務については、社内に優秀な設計者が育ってきているので、任せられる体制を確立していきたいです。
AIの進化などで、構造設計も近い将来に大きな変革が来ると思っています。会社として時代の変化に柔軟に対応して行きたいです。