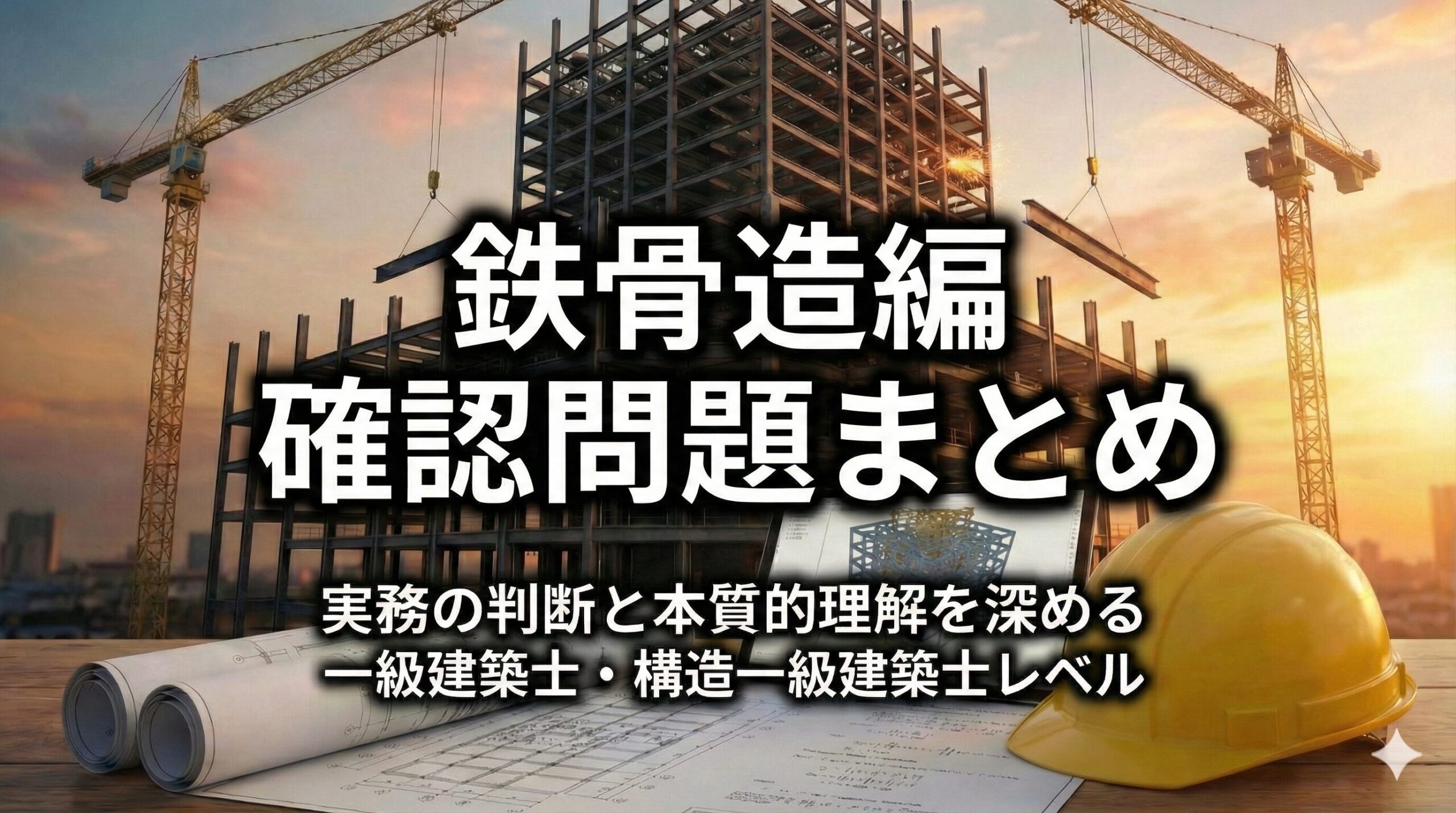鉄骨造に関する記事での確認問題のまとめになります。問題のレベルとしては一級建築士と構造一級建築士の間くらいだと思いますが、実務の判断をベースに本質的な部分を深められるようにしています。
解答できなかった部分を改めて記事に目を通してみてください。
①一般事項
材料の特徴/計算条件とディテールの整合
問題1 材料単体の比重(密度)を比較すると、鉄(約7.8)はコンクリート(約2.3)よりもはるかに重いため、建物全体の単位面積当たりの重量(kg/㎡)で比較しても、一般的にRC造より鉄骨造の方が重くなる。
解答1 :× 解説: 材料単体の比重は鉄の方が重いですが、鉄骨造はH形鋼のように「中身が詰まっていない形状」や「薄い板厚」で強度を発揮できるため、建物全体として見るとRC造よりも大幅に「軽く」なります。(RC造:約1200~1600kg/㎡ に対し、S造:約700~900kg/㎡)。この軽さが基礎や地盤への負担軽減につながります。
問題2 鉄骨部材は強度が高く、部材断面を細くできるメリットがあるが、その反面、圧縮力を受けた際に部材が横にはらみ出す「座屈」や、曲げモーメントを受けた際に圧縮側がねじれる「横座屈」が起きやすいため、それらを防ぐための補強(補剛)や部材配置の検討が重要である。
解答2 :〇 解説: 鉄骨造は「細くて強い」のが特徴ですが、細い部材に圧縮力がかかると、強度が限界に達する前にぐにゃりと曲がってしまう「座屈」のリスクがあります。これを防ぐために、スチフナ(補剛材)を入れたり、小梁で横変形を拘束したりする検討が重要になります。
問題3 構造計算において梁を「ピン接合(単純支持)」としてモデル化した場合であっても、実際のディテール(詳細)では脱落防止等の安全性を高めるために、ウェブだけでなくフランジも溶接してガッチリと固定(剛接合化)しておくことで安全率を高めることができる。
解答3 :× 解説: これは非常に危険な間違いです。計算で「ピン(回転自由)」としているのに、現場でフランジを溶接して「剛(回転拘束)」にしてしまうと、計算では想定していない「曲げモーメント」が接合部に発生してしまいます。 その結果、接合部が破断したり、取り付く相手の梁をねじ切ってしまったりする恐れがあります。設計と施工の整合性を取るためには、ピン計算ならピンのディテール(ウェブのみ接合など)を採用しなければなりません。
ダイアフラムの出寸法や開先角度、その「標準値」の意味を知る
問題1 冷間成形角形鋼管の通しダイアフラムの出寸法(一般的に25~30mm)について、溶接施工の余裕を持たせるために設計判断でこの寸法を「50mm~60mm」と大きく設定することは、母材への熱影響も避けられるため、品質確保の観点からは推奨される変更である。
解答1 :× 解説: 出寸法を必要以上に大きくすると、溶接熱によってダイアフラムの先端が波打つように変形する「かさ折れ」が発生しやすくなります。かさ折れが起きると梁フランジとの食い違いが生じ、その修正も困難になるため、マニュアル推奨値(25~30mm)を守るのが基本です。
問題2 通しダイアフラム形式において、ダイアフラムの板厚を梁フランジ厚よりも「2サイズアップ(厚く)」させる主な理由は、梁フランジからの応力を確実にダイアフラム内に伝達させるため、施工誤差による「食い違い」が生じても溶接がダイアフラムの厚み内に収まるようにするためである。
解答2 :〇 解説: 通しダイアフラムは梁フランジと直接突合せ溶接されるため、わずかなズレ(食い違い)が命取りになります。内ダイアフラム形式(1サイズアップが一般的)と異なり、柱を介さず直接応力を受けるため、より確実な溶接シロを確保するために「2サイズアップ」が基本とされています。
問題3 完全溶け込み溶接の開先角度を、従来の標準的な「35°」から「30°(狭開先)」に変更する場合、溶接金属の使用量が減りコストダウンや工期短縮につながるメリットがある一方で、施工の難易度が上がり厳密な品質管理が求められるため、事前にファブの施工実績や管理体制を確認する必要がある。
解答3 :〇 解説: 狭開先(30°)は溶接量が減るため経済的ですが、溶接ワイヤの狙い位置がシビアになったり、条件によっては高温割れのリスクが生じたりします。そのため、JASS6でも許容差が厳しく設定されており、採用にはファブの技量確認や施工試験などの慎重なプロセスが不可欠です。
②設計方針と使用材料
冷間成形角形鋼管(コラム柱)設計の留意点と計算ルート別解説
問題1 冷間成形角形鋼管は、製造過程で鋼板を常温で曲げ加工するため、特にコーナー部(角)は加工硬化によって強度が上昇する。STKR材(一般構造用角形鋼管)はこの硬化による強度上昇を積極的に利用しているため、BCP材やBCR材よりも耐震性能(靭性)に優れた材料として扱われる。
解答1 :× 解説: 逆です。冷間成形による加工硬化は、強度を上げますが、同時に「靭性(粘り強さ)」を低下させます。STKR材は一般構造用であり、建築構造用として塑性変形能力(靭性)が保証されたBCP材やBCR材に比べて耐震性能は劣ります。そのため、大規模な地震力が想定される建築物では、STKRの使用には厳しい制限や割増し検討が課せられます。
問題2 冷間成形角形鋼管(BCR/BCP)を使用した柱において、ルート2やルート3で「全体崩壊形(柱が梁より先に降伏しない)」であることを確認するための「柱・はり耐力比」の検討では、接合部における「柱の全塑性モーメントの和」が「梁の全塑性モーメントの和」をわずかでも上回っていること(比率が1.0以上であること)を確認すればよい。
解答2 :× 解説: 「1.0倍(柱>梁)」では不十分です。 冷間成形角形鋼管は、製造時の加工硬化などの影響や、地震時の挙動の不確定さを考慮し、より高い安全率を見込む必要があります。具体的には、当該接合部における「柱の全塑性モーメントの和」が、「梁の全塑性モーメントの和」の**「1.5倍以上」**(または接合部耐力の1.3倍以上)であることを確認する必要があります。
問題3 保有水平耐力計算(ルート3)において、柱梁耐力比の確認の結果、「部分崩壊形(柱が梁より先に降伏する可能性がある)」と判定された場合、その柱の保有耐力算出時の耐力は、材料に応じて「低減(0.75倍~0.8倍など)」させて評価しなければならない。
解答3 :〇 解説: 正解です。全体崩壊形(梁降伏型)にならず、柱が先に壊れる「部分崩壊形」となる場合、建物が脆性的に崩れるリスクがあります。そのため、安全側の評価として、計算上の柱の耐力をあえて「低減(BCRで0.75倍、BCPで0.8倍)」させた状態で、それでも保有水平耐力が必要量を満たしているかを確認する必要があります。
建物の強度を支える「溶接」の基本を解説
問題1 1995年の阪神・淡路大震災において、鉄骨造の建物が「柱や梁が十分に粘り強く変形する前に、接合部の溶接が脆性的に破断する」という被害が多く見られたことを教訓に、現在の設計では「溶接部は母材と同等以上の性能を持つ」ことが原則となっている。
解答1 :〇 解説: 阪神・淡路大震災では、溶接部が先行して破壊されることで、建物が本来の耐震性能(エネルギー吸収能力)を発揮できない事例が多発しました。これを受けて基準が厳格化され、現在の設計では、接合部(溶接部)が母材よりも先に壊れないようにすることが鉄骨造設計の絶対的なルールとなっています。
問題2 建物の主要な骨格であり、地震時に大きな力が集中する「柱と梁の接合部(仕口)」では、施工スピードを優先し、比較的容易に施工できる「隅肉溶接」を採用するのが一般的である。
解答2 :× 解説: 「柱と梁の接合部(仕口)」や「柱の継手」など、建物の骨格となり大きな力がかかる重要部分には、母材と一体化し同等の強度を発揮する「完全溶け込み溶接」が必須です。隅肉溶接は、小梁や補強材(スチフナ)など、二次的な部材の接合に主に使用されます。
問題3 隅肉溶接の強度計算において、溶接のサイズを示す「脚長(きゃくちょう)」がそのまま有効な厚さとして使われるため、脚長10mmの溶接であれば、計算上の厚さも10mmとして強度を算出する。
解答3 :× 解説: 隅肉溶接の強度計算に使われる有効な厚さは「のど厚」と呼ばれ、これは脚長の約0.7倍となります。例えば脚長が10mmの場合、計算上の有効厚さは約7mmとして評価します。脚長そのもので計算すると強度を過大評価してしまうため注意が必要です。
材料と形状の使い分け完全ガイド
問題1 鉄骨部材の選定において、最も安価で入手しやすい「SS400材(一般構造用圧延鋼材)」は、JIS規格で強度の下限値が規定されているため、コストダウンを最優先する場合、地震時に大きな変形(塑性化)が想定される大梁や柱などの主要構造部材であっても、強度計算さえ満たしていれば積極的に採用してよい。
解答1 :× 解説: SS材は引張強さの下限値こそ規定されていますが、耐震設計で最も重要な「塑性変形能力」や「溶接性」が保証されていません。主要構造部材に使うと、大地震時に粘り強さを発揮できず破断する恐れがあります。 主要構造部材には、それらが保証された「SN材(建築構造用圧延鋼材)」を使用するのが原則です。SS材は、塑性変形を期待しない間柱や小梁などの二次部材への使用に留めましょう。
問題2 角形鋼管の柱材を選定する際、BCR(冷間ロール成形)は製造可能な最大サイズ(一般的に□550程度)に限界があるため、それ以上の断面性能が必要となる大規模な建物においては、より大径かつ高強度の製品が製造可能な「BCP」が採用されることになる。
解答2 :〇 解説: BCRはコストと納期に優れますが、サイズや強度に限界があります。そのため、それ以上のスペックが求められる大規模建築では、より大径・高強度のラインナップがあるBCP(冷間プレス成形)を使用することになります。ただし、BCPは納期が長いため、早期の発注計画が重要です。
問題3 ダイアフラムや柱脚のベースプレートなど、板厚方向に強い引張力がかかる部位にSN材を使用する場合、鋼材が層状に剥がれてしまう「層状剥離(ラメラテア)」への抵抗性が保証された「C種(SN490Cなど)」を選定する必要がある。
解答3 :〇 解説: 厚板を溶接する際、板厚方向に引張力が作用すると、鋼材内部で剥離(層状剥離)が生じるリスクがあります。SN材の「C種」は、この板厚方向の性能(絞り値など)が保証されており、ダイアフラムやベースプレートなど、剥離のリスクが高い部位にはC種の使用が必須となります。
鋼材の寸法はなぜ中途半端?H形鋼・板厚・鋼管の理由を解説
問題1 鋼板(PL)の厚さとして一般的に使われる「9mm, 12mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm」といった一見不規則な寸法は、かつて主流だったヤード・ポンド法の「インチ規格(分数)」をメートル法(ミリメートル)に換算し、使いやすい数値に丸めたものが由来となっている。
解答1 :〇 解説: 例えば12mmは「1/2インチ(約12.7mm)」、19mmは「3/4インチ(約19.05mm)」、25mmは「1インチ(25.4mm)」が由来です。これらをメートル法で使いやすい数値に丸めたものがJIS規格として定着しています。
問題2 丸形鋼管(STKNなど)の外径寸法に「φ114.3mm」や「φ216.3mm」といった小数点以下の端数が含まれているのは、構造計算上で必要となる断面性能(断面積や断面二次モーメント)を、キリの良い整数値にするために逆算して決定された寸法だからである。
解答2 :× 解説: 計算結果から逆算したわけではありません。配管用として普及していた「インチ規格(呼び径)」のパイプを、そのままメートル法の「外径(mm)」に換算した結果、端数が生じています。(例:4インチ配管の外径≒114.3mm)
問題3 JIS規格におけるH形鋼の中幅系列(例:H-588×300など)の寸法が中途半端な数値になっている背景の一つには、製造時に使用する圧延機のロールを既存の「広幅系列」と共用できるように内法寸法を揃えたり、当時流通していた「I形鋼」の寸法や性能に整合させたという製造・規格上の合理的な理由がある。
解答3 :〇 解説: H形鋼はユニバーサル圧延機で作られますが、ロール(金型のようなもの)を共用してコストを下げるため、広幅系列と内法寸法(フランジ間の距離)を統一しました。また、I形鋼からの移行をスムーズにするため、それに近い寸法設定がなされた経緯があり、結果として「H-588」のような半端な寸法が生まれています。
柱脚仕様の使い分けと露出柱脚のチェックの視点
問題1 露出柱脚は、施工性や経済性に優れる一方で、構造的な固定度は「完全固定(Fix)」ではなく「半固定(回転ばね)」として扱われるため、設計時にはその回転剛性が建物全体の変形や応力に与える影響を考慮する必要がある。
解答1 :〇 解説: 露出柱脚は、根巻き柱脚や埋込柱脚のようにコンクリートで拘束されていないため、完全には固定されず、ある程度回転します。これを「半固定(回転ばね)」としてモデル化します。回転剛性の設定次第で、柱の応力や建物の揺れ方が変わるため、コストとのバランスを見ながら適切な製品を選定する必要があります。
問題2 建築基準法の告示(平12建告第1456号)において、露出柱脚のアンカーボルトのコンクリートへの定着長さは、抜け出し防止の観点から「ボルト径の10倍(10d)以上」と定められている。
解答2 :× 解説: 「10倍」ではなく「20倍(20d)」です。 告示では、アンカーボルトの定着長さは「径の20倍以上」と明確に数値で定められています。この「20d」という数値は、鉄骨造の柱脚に限らず、RC造などの定着検討でも目安として使われる重要な基準値ですので、必ず覚えておきましょう。
問題3 露出柱脚の選定において、大地震時に柱が梁よりも先に降伏しないようにする「保有耐力接合(保有水平耐力接合)タイプ」への適合は義務であるため、アンカーボルト側が先に降伏・伸びてしまうような仕様(非適合)を採用することは構造設計上認められていない。
解答3 :× 解説: 基本的には柱を先に降伏させる(保有耐力接合タイプにする)ことが望ましいですが、意匠的な制約やコスト、基礎への負担などを考慮し、あえてアンカーボルト側でエネルギーを吸収させる(非適合とする)選択も可能です。 ただし、その場合はDs値(構造特性係数)の割増しが必要になるなど、設計ルートや崩壊形の想定に整合させる必要があります。「意図を持って選ぶ」ことが重要です。
溶融亜鉛めっきの基本と設計で見落としてはいけないポイント
問題1 溶融亜鉛めっき処理は部材を約450℃の高温槽に浸漬させるため、鋼材の機械的性質が大きく変化するリスクがある。したがって、処理後の鋼材に対しては原則として改めて材料試験を行い、品質への影響がないかを確認しなければならない。
解説1 :× 解説: 建設省告示により、500℃以下の加熱であれば、鋼材の機械的性質などを加工後に確認する必要はないとされています。めっき槽の温度は約450℃であるため、品質への影響は考慮不要であり、再試験などは原則として不要です。
問題2 溶融亜鉛めっきを施した高力ボルト摩擦接合部(F8Tなどを使用)の検討において、接合面のすべり係数は、一般的な赤錆等の処理(F10T)の「0.45」よりも低い「0.40」を採用して計算する必要がある。
解説2 :〇 解説: 亜鉛皮膜によって接合面の摩擦抵抗(すべり係数)が低下します。そのため、溶融亜鉛めっき高力ボルト(F8T)を使用する場合のすべり係数は「0.40」として設計する必要があります。(一般的なF10Tの赤錆処理などは0.45)。この数値を間違えると耐力不足になるため注意が必要です。
問題3 剛接合(完全溶込み溶接)において裏当て金を使用する場合、裏当て金と母材の隙間はめっきが回りにくく、そこからさび汁が発生する原因となるため、「裏当て金の全線シール溶接」を行うか、「裏はつりを行う両面溶接(裏当て金なし)」とする等の対策が必要である。
解説3 :〇 解説: 一般的な裏当て金を用いた溶接では、裏当て金と母材の微細な隙間にめっきが入らず、空気や酸が残ってしまい、後から「さび汁」が垂れてくる不具合に繋がります。これを防ぐために、隙間を塞ぐ「シール溶接」を行うか、そもそも裏当て金を使わない「両面溶接」にするなどの詳細検討が不可欠です。
③荷重・外力
二次部材の設計の留意点~デッキスラブの種類と選び方
問題1 デッキプレートのカタログにある「許容スパン」を確認する際、単純支持よりも「連続支持(2スパン以上)」の方が飛ばせる長さが長くなるため、小梁を減らしてコストダウンを図るためにも、計算上は常に「連続支持」の値を採用して設計するべきである。
解答1 :× 解説: 計算上の数値だけで判断するのは危険です。「連続支持」とするためには、長尺のデッキ(例:9mなど)が必要になります。しかし、現場周辺の道路事情や荷揚げリフトのサイズによっては、そのような長い部材が搬入できない場合があります。 搬入限界により短いデッキしか使えない場合、物理的に「単純支持」扱いとなり、設計スパンが成立しなくなる恐れがあるため、必ず搬入経路とセットで検討する必要があります。
問題2 合成スラブ(合成デッキ)を採用する場合、デッキプレート自体が引張鉄筋の役割を果たすため、支点(梁)上部のコンクリート表面に配置する「ひび割れ防止筋(溶接金網やD10等)」は、耐力計算上不要であれば省略することができる。
解答2 :× 解説: 合成スラブであっても、梁の上部(支点)には負の曲げモーメントが発生し、コンクリート表面にひび割れが生じやすくなります。そのため、構造耐力上はデッキのみで成立していても、ひび割れ制御のためにトップ筋(ひび割れ拡大防止筋)の配置が必要です。特にかぶり厚さの確保にも注意しましょう。
問題3 設備配管などで床に開口が多くなることが予想されるエリアでは、現場での配筋手間を減らすために、あらかじめ鉄筋がセットされている「鉄筋トラス付きデッキ」を採用するのが最も施工性が良く合理的である。
解答3 :×解説: 鉄筋トラス付きデッキは、トラス筋の位置が決まっているため、不規則な開口位置に合わせて鉄筋を切断したり補強したりするのが困難な場合があります。開口が多く複雑な調整が必要な箇所については、現場での加工自由度が高い「フラットデッキ(捨て型枠)」を採用し、現場配筋で対応する方が納まりが良くなります。
見落としがちな鉄骨二次部材の荷重とモジュールの考え方
問題1 鉄骨造の外壁荷重(重量)の負担について、地震力を算定する際は一般的に上下階で半分ずつ負担するモデルで考えるが、個別の梁の断面算定(長期荷重)を行う際には、外装材の工法(縦張り・横張り・ロッキング機構など)によって、上階の梁のみ、あるいは柱のみが負担するケースがあるため、納まり図を確認して荷重モデルを決定する必要がある。
解答1 :〇 解説:地震力の算定(層せん断力)では重量を階で按分しますが、部材設計では「実際にどう留まっているか」が重要です。例えば、縦張りのECP(押出成形セメント板)などは、変形追従のために下部をスライドさせ、自重は上部の梁だけで受ける(上吊り)ケースが多いため、単純に半分ずつ負担させると上部梁が耐力不足になる危険があります。
問題2 屋根や外壁の下地鉄骨の配置(ピッチやスパン)を決定する際、最も優先すべきは構造計算によって算出された下地鉄骨自身の耐力であり、使用する仕上げ材(ALCや折板屋根など)の既製寸法や許容スパンについては、下地鉄骨の設計後に調整すればよいため、初期段階で考慮する必要はない。
解答2 :× 解説: 既製品(仕上げ材)には製造上の定尺や、強度上の最大スパンが決まっています。下地鉄骨が強くても、仕上げ材が持たなければ意味がありません。また、規格外の寸法で切断・加工が増えるとコストアップに直結するため、まずは「既製品のモジュール」に合わせてスパン割りを計画することが鉄骨設計の基本です。
問題3 屋外に設置される目隠し壁などを支持する鉄骨梁を選定する場合、長期の鉛直荷重だけでなく、風圧力による梁の弱軸方向(横方向)への曲げも考慮する必要があるため、強軸方向の性能に特化した「細幅H形鋼」よりも、弱軸方向の性能も比較的高い「中幅」や「広幅」のH形鋼を選定する方が合理的である場合が多い。
解答3 :〇 解説:H形鋼は「I」の形をしているため、縦方向(強軸)には強いですが、横方向(弱軸)には弱い特性があります。風圧力を面外に受けるような部材では、弱軸方向にも力がかかるため、幅の広いH形鋼(フランジ幅が広いもの)を採用して、横方向の曲げや座屈に対する耐力を確保するのが適材適所の設計です。
外装材(ALC・ECP・PC)の支持部材
問題1 構造計算において外壁の重量を拾う際は、一般的に階高の中間で上下に振り分けてモデル化するが、外装材を支持する個別の部材(耐風梁やファスナー等)の設計においても、経済性を高めるため、原則としてパネル1枚の重量を上下の支持部材で均等に(50%ずつ)負担させる前提で断面算定を行うのがよい。
解答1 :× 解説:構造計算上の荷重拾いと、個別の支持部材の設計は分けて考える必要があります。 外装材は、地震時の層間変形に追従するため、ロッキング機構(一方は固定、もう一方はルーズホールでスライドさせる等)を持たせることが一般的です。その場合、自重(鉛直荷重)は「下端のみ(または上端のみ)」で全重量を受けることになります。「半分ずつ負担する」と誤解して設計すると、実際の支持部材には想定の2倍の荷重がかかり、変形や脱落の原因となります。
問題2 外装材の取り付け位置が梁の中心から離れており、片持ち形式のガセットプレート等を介して支持する場合、H形鋼の梁には「ねじれ」の力が作用する。H形鋼はこの「ねじれ」に対して非常に弱いため、反対側に補強を入れるか、スラブによる拘束効果(およびその強度発現時期と施工順序)を十分に検討する必要がある。
解答2 :〇 解説:H形鋼は「曲げ」には強いですが、「ねじれ」には極端に弱い断面形状です。外壁芯が梁芯から離れると、その偏心によって梁をねじる力が発生します。スラブが打設され硬化していれば拘束されますが、スラブ打設前に外壁を取り付ける工程の場合、梁がねじれてしまうトラブルが起きやすいため、施工手順や補強の検討が不可欠です。
問題3 ECP版(押出成形セメント板)は、ALC版(軽量気泡コンクリート)と比較すると材料自体の比重が大きいため、外壁としての単位面積当たりの重量(kg/㎡)もECP版の方が大幅に(倍近く)重くなる。したがって、ECP版を採用する場合はALC版の時よりもはるかに強固な下地鉄骨が必要となる。
解答3 :× 解説:確かに「材料単体の比重」はコンクリートに近いECPの方がALCより重いです。しかし、製品として見ると、ECP版は「中空形状」かつ「薄肉(強度が高いため薄くできる)」であるのに対し、ALC版は厚みがあります。 結果として、外壁としての「単位面積当たりの重量(kg/㎡)」で比較すると、両者に大きな差はありません。そのため、重量を理由に下地鉄骨のサイズが劇的に変わるということは基本的にはありません。
耐火被覆工法の種類から構造設計上の留意点
問題1 鉄骨造の建物において、法的に「耐火構造」が求められる場合、柱や梁といった主要構造部に限らず、長期荷重を負担しない水平ブレースや耐風梁などを含めた「全ての鉄骨部材」に対して、例外なく耐火被覆を行わなければならない。
解答1:× 解説: 耐火被覆が必須となるのは、建築基準法上の「主要構造部」に該当する部材です。記事にもある通り、長期荷重(床の重さなど)を負担しない部材、例えば地震力のみを負担するブレースや、風圧力のみを受ける耐風梁などは、耐火被覆の対象外となる場合があります。不要な部分にまで被覆を行うとコスト増になるため、区別が必要です。
問題2 意匠的な理由等で小径の柱や薄い板厚の部材を使用したい場合、構造計算によって安全性が確認できていれば自由に採用して良いが、耐火被覆の工法によっては「認定条件(最小断面積や最小板厚)」が存在し、構造計算とは別の理由で部材サイズをアップさせなければならないケースがある。
解答2:〇 解説: 耐火被覆材は、国土交通大臣の認定を受けた工法ごとに「適用範囲」が定められています。その中には、熱容量を確保するための「最小断面寸法」や「鋼材の最小板厚」が条件となっていることが多くあります。力学的にOKでも、この認定条件を満たすためにサイズアップが必要になることは実務でよくある落とし穴です。
問題3 梁に設備配管を通すためのスリーブ(貫通孔)を設ける際、耐火被覆を施工するとその厚みの分だけ「実際に配管を通せる有効寸法」が小さくなってしまうため、構造設計者はあらかじめ被覆厚を見込んでスリーブ径を大きく設定するか、スリーブ部分の被覆を薄くできる認定品を選定する等の配慮が必要である。
解答3:〇 解説: 例えば、梁のウェブにφ150のスリーブを開けたとしても、そこに厚さ25mm等の耐火被覆を巻き込むと、実際の穴径はもっと小さくなってしまいます。この被覆厚による減少分を考慮せずにギリギリの設計をすると、現場で「配管が入らない」というトラブルに直結するため、事前の調整が不可欠です。
④応力解析
柱梁接合部の本質 -歴史的背景とモデル化の理論
問題1 一般的な一貫計算プログラムにおいて、柱梁接合部を「剛域(変形しない領域)」としてモデル化する理由の一つは、接合部の変形を無視することで柱や梁などの部材に生じる応力が小さく計算され、経済的な(断面を小さくできる)設計が可能になるためである。
解答1 :× 解説: 接合部を「剛(変形しない)」と仮定すると、地震などによる建物の変形をすべて柱や梁が負担することになります。その結果、柱や梁に生じる応力は「大きめ」に計算される傾向にあります。これは、部材断面が大きくなりやすいため経済的とは言えませんが、構造設計としては「安全側」の評価になるため、このモデル化が一般的に採用されています。
問題2 RC造の柱梁接合部の検討において、接合部パネルの「せん断耐力」を計算上向上させるためには、接合部内に入れるフープ筋(帯筋)の量を増やすことが最も直接的で効果的な対策である。
解答2 :× 解説: ここは勘違いしやすいポイントです。現在の耐力式(靭性指針など)において、接合部のせん断耐力は主に「コンクリート強度」「接合部の形状(体積)」「直交梁の有無」などで決まります。 フープ筋には0.2%や0.3%といった「最小鉄筋量」の規定はあり、拘束効果として必須ですが、計算式上はフープ筋を増やしてもせん断耐力の数値自体は上がりません。耐力が不足する場合は、コンクリート強度を上げるか、柱断面を大きくする等の対策が必要です。
問題3 1995年の阪神・淡路大震災では、鉄骨造の梁端部の溶接作業用に設けられた「スカラップ(溶接孔)」に応力が集中し、そこを起点とした脆性破壊が多発したため、現在ではスカラップを設けない「ノンスカラップ工法」が標準となっている。
解答3 :〇 解説: かつては現場溶接の作業性を良くするためにスカラップ(切り欠き)を設けていましたが、震災時にそこが破壊の弱点(起点)となることが判明しました。その教訓から、現在は応力集中を避けるためにスカラップを設けない「ノンスカラップ工法」とし、完全溶込み溶接を行うことが一般的です。
ブレースの種類と設計の留意点
問題1 丸鋼やアングルを用いた「引張ブレース」は、圧縮力が作用した瞬間に座屈して耐力を失うため、一般的にX型に配置し、地震時には引張側のみが有効に働くと仮定して設計する。一方で、「座屈拘束ブレース(アンボンドブレース等)」は、圧縮力を受けても座屈せず、安定したエネルギー吸収能力を発揮する。
解答1 :〇 解説: 引張ブレースは圧縮に抵抗できませんが、安価で一般的です。対して座屈拘束ブレースは、芯材をコンクリートや鋼管で拘束しているため、圧縮時でも座屈せずに耐力を維持し、制振ダンパーのような高い性能を発揮します。
問題2 ブレースの接合部設計における「保有耐力接合」とは、大地震時に接合部(ガセットプレートやボルト)が先に破壊することで地震エネルギーを吸収し、ブレース材本体の損傷(塑性化・破断)を防ぐという設計思想のことである。
解答2 :× 解説: 保有耐力接合の原則は**「部材 < 接合部」**です。 接合部が先に壊れてしまうと、ブレースが伸びてエネルギーを吸収する前に脱落してしまい、耐震要素として機能しなくなります。必ず「ブレース材が降伏しても接合部は耐える」ように設計する必要があります。
問題3 一貫構造計算ソフトでブレースを入力する際、実際の納まり(ガセットプレート等による剛性アップ)を考慮せず、ブレース材単体の剛性のみでモデル化することは、建物全体の変形量計算においては安全側となるが、ブレースが取り付く柱や梁、基礎杭の設計にとっては、応力が過小評価される「危険側」の検討となる可能性がある。
解答3 :〇 解説: ブレースの剛性を実際よりも低く(柔らかく)評価すると、計算ソフトは「このブレースにはあまり力が流れない」と判断し、その反力(柱への軸力や杭への引き抜き力)を小さく算出してしまいます。 実際にはガセットプレート等で剛性が高く(硬く)、大きな力が流れるため、柱や杭が耐力不足になるリスクがあります。剛度増大率などで適切に補正する必要があります。
⑤断面検定
柱梁耐力比とパネルゾーンの重要性/梁ウェブ評価の注意点
問題1 建築基準法や学会規準において、大地震時に「梁降伏型(弱梁強柱)」の崩壊メカニズムを確保するために推奨されている「柱梁耐力比(柱の全塑性モーメントの和 ÷ 梁の全塑性モーメントの和)」の数値は、原則として「1.0以上」であればよい。
解説1 :× 解説: 原則として「1.5以上」が求められます。 理論上は「柱>梁(比率1.0超)」であれば柱の方が強いことになりますが、実際には材料強度のばらつきやひずみ硬化、計算では想定しきれない複雑な地震の揺れがあります。これらを見込んで、確実に柱を健全に保ち、梁を降伏させるための安全率を含んだ数値として1.5が設定されています。
問題2 柱梁耐力比の検討において、計算上で柱が梁よりも十分に強い数値となっていたとしても、接合部である「パネルゾーン」のせん断耐力が不足していると、パネルゾーンが先に破壊してしまい、意図した梁降伏型のメカニズムが成立しない恐れがある。
解説2 :〇 解説: パネルゾーンは力の伝達の要(かなめ)です。いくら柱と梁の強度バランスが良くても、その結節点であるパネルゾーンが先にせん断破壊(脆性破壊)してしまうと、梁が粘り強さを発揮する前に力が伝わらなくなり、弱梁強柱メカニズムは成立しません。
問題3 柱梁耐力比を計算する際、H形鋼の梁の「ウェブ」が持つ曲げ耐力をあえて「考慮しない(無視する)」設定にすることは、梁の耐力を実際よりも小さく見積もることになるため、柱梁耐力比の検討においては常に「安全側」の評価となる。
解説3 :× 解説: 誤り(危険側)です。 一次設計などで梁の断面を決める際は、耐力を小さく見積もることは安全側ですが、柱梁耐力比の検討では逆効果です。 柱梁耐力比は「柱÷梁」で求めます。分母である「梁の耐力」を過小評価(ウェブ無視)して小さくすると、計算結果の比率は「見かけ上高く(安全そうに)」出てしまいます。実際には梁はもっと強いため、現実の比率は1.5を下回っているかもしれず、危険側の検討となります。
鉄骨造の弱点「座屈」とは?原因と対策を解説
問題1 柱の全体座屈(長柱座屈)に対する強さは「細長比で決まる。そのため、有効座屈長さが同じであれば、断面二次半径が「大きい側(強軸)」をさらに補強して大きくすることで、柱全体の座屈耐力を効果的に向上させることができる。
解答1:×解説:座屈は、弱い方向(断面二次半径が小さい方向、つまり細長比が大きい方向)に発生します。いくら強い側(強軸)を補強しても、弱い側(弱軸)の性能が変わらなければ、柱はその弱い方向へ座屈してしまい、全体の耐力は上がりません。座屈対策では、常に「弱軸側をどう補強するか(あるいは弱軸側の座屈長さをどう短くするか)」が重要になります。
問題2 プレートガーダー(組立梁)などのウェブに垂直補剛材(スチフナー)を溶接することは、ウェブの断面積を増やす効果よりも、区切ることで板要素の「幅 」を小さくし、幅厚比を改善して局部座屈を防ぐ効果を狙ったものである。
解答2:〇解説:局部座屈のしやすさは「幅厚比」で決まります。スチフナーを入れると、物理的に板厚が増えるわけではありませんが、板が区切られることで座屈する区画の「幅」が見かけ上小さくなります。これにより幅厚比が小さくなり、薄い板でも座屈しにくくなるのです。
問題3 鉄骨梁の上部にコンクリートスラブがあり、スタッドジベルで一体化されている場合、上フランジは全長にわたって強固に拘束されるため、大梁などの端部も含めて「横座屈」の発生を考慮する必要は一切なくなる。
解答3:× 解説: スラブによる拘束は、それに接している「上フランジ」に対して有効です。 単純梁の中央部など「上が圧縮」になる部分は有効ですが、固定端となっている大梁の端部などは、曲げモーメントにより「下フランジが圧縮」となります。下フランジはスラブで拘束されていないため、ここには横補剛材(直交梁など)がないと横座屈を起こすリスクがあります。
横補剛はなぜ必要?役割と性能を解説
問題1 H形鋼の梁に生じる「横座屈」は、曲げモーメントによって「引張力」を受けている側のフランジが、過大な引張力に耐え切れずに横方向へはらみ出すことで発生する。
解説1 :× 解説: 横座屈は、「引張側」ではなく「圧縮側」のフランジで発生します。細長い柱が圧縮力で座屈するのと同様に、梁の圧縮フランジが耐え切れずに横へはらみ出し、梁全体がねじれる現象です。引張側は引っ張られることでむしろ安定するため、座屈は起きません。
問題2 横補剛材として機能するためには、対象となる梁の圧縮フランジに作用する圧縮力の「約2%」の力に対して、耐力(強度)を有していることを確認するのが一般的である。
解説2 :〇 解説: 横補剛材は、梁の変形を拘束する「剛性」だけでなく、梁が横に動こうとする力に耐える「耐力」も必要です。一般的に、梁の圧縮フランジにかかる力の約2%の水平力が作用しても壊れない強さが必要とされています。部材本体だけでなく、取合いのボルト本数などもこの力に対して検討する必要があります。
問題3 保有水平耐力計算(二次設計)において、横補剛の間隔(補剛点間距離)が規定より長くなったとしても、部材自体の「幅厚比」さえ条件を満たしていれば、部材ランク(FA~FD)が悪くなることはない。
解説3 :× 解説: 部材ランク(靭性)は、「幅厚比(局部座屈)」と「横補剛間隔(横座屈)」の両方の条件で決まります。いくら板厚が厚く幅厚比が優秀でも、横補剛の間隔が広すぎると横座屈を起こして粘り強さを発揮できないため、部材ランクは最も低い「FDランク」などになり、必要保有水平耐力(Ds値)が割増しされる要因となります。
合成梁・不完全合成梁の使い分けと評価のポイント
問題1 鉄骨梁の保有水平耐力計算において、スラブによる剛性や曲げ耐力の向上効果を無視して(鉄骨単体として)評価することは、梁の保有耐力を小さく見積もることになるため、柱梁接合部の破壊防止や柱梁耐力比の検討においても、常に「安全側」の評価となる。
解答1 :× 解説: 梁を弱く見積もると、計算上は「柱の方が強い(柱梁耐力比OK)」と判定されやすくなります。しかし、実際にはスラブ効果で梁が強くなっているため、地震時には計算よりも大きな力が柱や接合部にかかり、梁が壊れる前に柱が破壊してしまう(柱先行破壊)リスクが高まります。
問題2 合成梁としてスラブと鉄骨梁が一体となって挙動するためには、曲げモーメントを受けた際に接触面に生じる、互いに逆方向へ滑ろうとする「水平せん断力」に対して、配置された頭付きスタッドのせん断耐力の合計が上回っている必要がある。
解答2 :〇 解説: 合成梁のメカニズムの核心です。上下の部材がズレようとする力(水平せん断力)をスタッドが繋ぎ止めることで、初めて断面全体が一体となって剛性と耐力を発揮します。
問題3 「不完全合成梁」とは、配置されたスタッドの総耐力が、梁が全塑性モーメントに達する際に発生する水平せん断力よりも小さい状態を指し、この場合、梁の終局曲げ耐力は鉄骨断面の強さではなく、スタッドの総耐力によって決定(制限)される。
解答3 :〇 解説: スタッドが不足していると、鉄骨が降伏して粘りを発揮する前に、スタッドがせん断破壊してしまいます。これが不完全合成梁です。長期荷重主体の梁では合理的ですが、地震力を負担する梁では脆性的な破壊を招く恐れがあるため、採用には慎重な判断が必要です。
⑥保有水平耐力
架構用部材ランクと変形性能
問題1 部材ランク(FA~FD)を決定する「幅厚比(幅/厚さ)」の制限値は、使用する鋼材の強度(基準強度F値)が高いほど、部材が大きな力に耐えられるようになるため、制限は「緩やか(薄い板厚でもOK)」になる。
解答1 :× 解説:鋼材の強度が高いほど、降伏点(部材が塑性化する応力)が高くなります。つまり、より大きな圧縮力がかかるまで頑張れる分、その大きな力によって座屈しやすくなってしまいます。その座屈を防ぐために、高強度の材料ほど幅厚比の制限は「厳しく(板を厚く)」設定されています。
問題2 FAランクの部材は、塑性変形倍率が約4倍程度あり、層間変形角でいうと1/50程度まで粘り強く変形できる性能を持っているため、保有水平耐力計算におけるDs値(構造特性係数)は最も小さい「0.25」を採用することができる。
解答2 :〇 解説:FAランクは最も靭性(粘り強さ)が高い部材です。 ・FAランク:Ds=0.25(層間変形角1/50程度、塑性率4) ・FBランク:Ds=0.30(層間変形角1/100程度、塑性率2) ・FCランク:Ds=0.35(弾性限度、層間変形角1/150~1/200) ・FDランク:Ds=0.40(弾性範囲内) という関係性をイメージしておくと設計方針が立てやすくなります。
問題3 鉄骨造の部材ランクを確保するためには、部材自体の「幅厚比」の条件さえ満足していればよく、柱梁の継手・仕口の接合方法や、梁の横座屈に対する補剛条件などは、部材ランクの決定には影響しない。
解答3 :× 解説: 幅厚比は重要な要素ですが、それだけではありません。部材がその性能(ランク)をフルに発揮するためには、接合部が先に壊れないこと(保有耐力接合)や、H形鋼などの横座屈しやすい部材が適切に補剛されていることが前提条件となります。これらが満たされない場合、幅厚比が良くてもランクは下がってしまいます。
保有耐力接合とは?鉄骨造の原則「部材<接合部」
問題1 保有耐力接合の主たる目的は、大地震時に接合部(ボルトや溶接部など)が部材(柱・梁・ブレース)よりも先に破壊することで、接合部で地震エネルギーを効率的に吸収させることである。
解答1 :× 解説: 順序が逆です。保有耐力接合の目的は、「接合部が壊れる前に、部材が先に降伏する」ことです。接合部の破壊はエネルギー吸収の乏しい「脆性的な破壊」になりがちです。一方、部材がぐにゃりと曲がったり伸びたりする(塑性化する)ことで、粘り強く地震エネルギーを吸収(靭性を発揮)します。そのために接合部を部材よりも強くしておく必要があります。
問題2 保有耐力接合の設計において重要なのは「接合部が破壊しないこと」であるため、大地震時において接合部が完全に無変形(弾性状態)であることまでは必ずしも求められていない。
解答2 :〇 解説: 記事にあるように、「重要なのは、接合部が『破壊』しないことであり、必ずしも『無変形(弾性状態)』である必要はありません」。部材が降伏してエネルギーを吸収しきるまで、接合部が破断せずに持ちこたえる強さがあれば、保有耐力接合の目的は達成されます。
問題3 梁の継手や仕口の検討において、接合部の耐力が梁の「全塑性モーメント(降伏時の最大耐力)」と同等の数値であれば、梁は十分に塑性化できるため、それ以上の耐力を接合部に持たせる必要はない。
解答3 :× 解説: 梁などの鋼材は、降伏して全塑性モーメントに達した後も、変形が進むと「ひずみ硬化」によってさらに材料強度が上昇します。そのため、接合部の耐力が全塑性モーメントと「同等」では、ひずみ硬化時に接合部が負けて破壊してしまう恐れがあります。このひずみ硬化や材料強度のばらつきを考慮し、所定の安全率を乗じて、全塑性モーメントよりも高い耐力を接合部に持たせる必要があります。
⑦現場(監理・施工)
高力ボルトの強度・寸法・施工の重要数値
問題1 溶融亜鉛めっきを施した部材を摩擦接合する場合、めっきによってすべり係数は「0.40」に低下するが、ボルト自体は高い締め付け力を維持するために、通常と同じ高強度の「F10T」を使用することが推奨される。
解答1:× 解説: 溶融亜鉛めっきを施すと、工程内で鋼材中に水素が侵入し、「遅れ破壊」のリスクが高まります。高強度のF10Tはこの水素脆化への感受性が高いため使用できません。そのため、強度は下がりますが遅れ破壊のリスクが低い「F8T」ボルトを使用するのが鉄則です。
問題2 高力ボルト摩擦接合において、ボルト孔径がボルト軸径+2mm(M24以下)と厳密に定められている理由は、施工時のクリアランス確保だけでなく、ボルト孔による断面欠損を抑え、接合部が破断する前に母材が塑性化する「保有耐力接合」を成立させるためである。
解答2:〇 解説: ボルト孔を大きくしすぎると、部材の断面積(純断面積)が減ってしまいます。そうなると、地震時に部材(フランジなど)が粘り強く伸びる(塑性化する)前に、ボルト孔の部分でちぎれて(破断して)しまう恐れがあります。これを防ぎ、保有耐力接合を満足させるために孔径は厳密に管理されています。
問題3 高力ボルトの締め付け完了後の検査において、ナットから突き出ているボルトの「余長(ねじ山数)」は、短すぎるとナットのかかり不足で危険だが、長い分には強度的には問題ないため、6山を超えていても合格として扱われる。
解答3:× 解説: 余長の合格基準は「1山~6山の範囲」です。短すぎるのがNGなのはもちろんですが、長すぎる(7山以上)場合も不合格です。 長すぎる場合は、ボルトの選定ミス(首下長さが不適切)のほか、過剰な締め付けによってボルトが伸びてしまっている(降伏してしまっている)可能性があり、所定の軸力が確保できていない恐れがあるためです。
現場溶接はなぜ難しい?メリットと品質確保の鉄則
問題1 鉄骨造の接合方法は、かつてはリベット接合が主流だったが、1970年代以降、施工効率が高く品質管理がしやすい「高力ボルト接合」が普及し、現在では高力ボルト接合と溶接接合が主流となっている。
解説1:〇 解説: かつてのリベット接合は騒音や熟練技術が必要という課題がありましたが、アメリカで開発された高力ボルトの導入により、施工効率が劇的に向上しました。現在では、工場での溶接と現場での高力ボルト接合(または現場溶接)を組み合わせるのが一般的です。
問題2 現場溶接を採用するメリットの一つに、ボルトやプレートといった副資材が不要になることによる部材の軽量化や、それに伴うコスト削減が挙げられる。
解説2:〇 解説: 高力ボルト接合では、添え板(スプライスプレート)や多数のボルトが必要となり、これらは主体鉄骨重量の1~2割程度を占めることがあります。現場溶接(特にノンブラケット工法など)を採用することで、これらの副資材を削減し、軽量化とコストダウン、さらには輸送効率の向上を図ることができます。
問題3 現場溶接の品質検査において、溶接部の表面にひび割れなどの欠陥がないかを「目視(外観検査)」で確認すれば、内部の欠陥についても十分に把握できるため、超音波探傷試験(UT)などの非破壊検査は必須ではない。
解説3:× 解説: 目視による外観検査は重要ですが、それだけでは溶接内部の「溶け込み不足」や「気泡(ブローホール)」などの欠陥を見つけることはできません。そのため、現場溶接の信頼性を確保するには、超音波探傷試験(UT)などの「非破壊検査」を行い、内部の健全性を確認することが不可欠です。