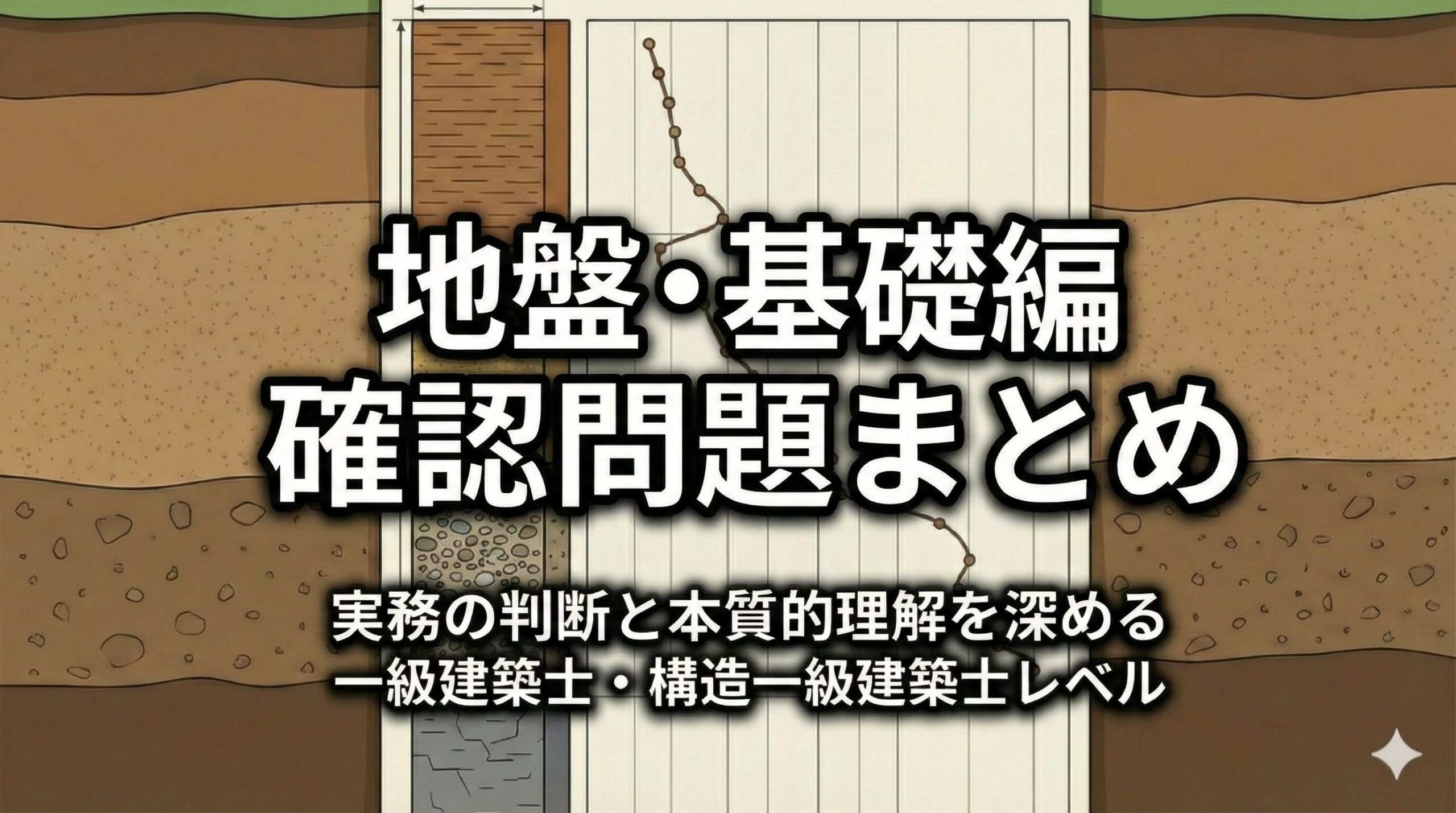地盤・基礎に関する記事での確認問題のまとめになります。問題のレベルとしては一級建築士と構造一級建築士の間くらいだと思いますが、実務の判断をベースに本質的な部分を深められるようにしています。
解答できなかった部分を改めて記事に目を通してみてください。
①地盤関連
N値だけで終わらない地盤調査の読み解き方|支持力・沈下・液状化検討のポイント
問題1 直接基礎の設計において地耐力を確認する際、標準貫入試験のN値から算出する推定式は安全側の(小さめの)値となる傾向があるため、より高い地耐力を期待し経済的な設計を行うためには、土をサンプリングして行う「一軸・三軸圧縮試験」や、現地で直接載荷する「平板載荷試験」を併用することが有効である。
解答1 :〇 解説: N値からの換算式はあくまで推定であり、ばらつきを考慮して安全率が高く設定されています。実際に土を採取して行う圧縮試験(粘着力cや内部摩擦角φを直接測定)や、実物大に近い平板載荷試験を行うことで、地盤が持つ本来の耐力をより正確に、かつ高く評価できる可能性が高まります。
問題2 杭基礎の耐震設計において、地震時の水平力に対する抵抗(水平地盤反力)を正確に評価するために「孔内水平載荷試験」を行う場合、杭の全長にわたって均等に試験を行うことが最も重要であり、特に杭頭付近の地盤データだけを重点的に取得する必要はない。
解答2 :× 解説: 杭に作用する水平力や曲げモーメントは、地表面に近い「杭頭付近」で最大となります。つまり、杭頭付近の地盤の硬さが杭の変形や応力を決定づけるため、孔内水平載荷試験は杭頭付近(およびその下の層)で重点的に行うことが、合理的かつ経済的な設計に直結します。
問題3 液状化の検討において、発生リスクが高いと判定される地盤の条件は、「地下水位が高い(飽和している)こと」「N値が低い(緩い)砂質土であること」に加え、粒度試験によって「細粒分含有率(Fc)が低い(粘りのないきれいな砂である)」ことが確認された場合である。
解答3 :〇 解説: 液状化は「水・緩さ・土質」の3要素が揃った時に発生します。特に土質については、粘土分やシルト分(細粒分)が少ない「サラサラした砂」ほど粒子がバラけやすく、液状化しやすい傾向にあります。これを粒度試験の「細粒分含有率(Fc)」で確認します。
盤の評価(液状化)~法・評価手法の変遷と設計者の役割
問題1 建築基準法や関連告示において、液状化のおそれのある地盤は「地表面から20m以内でN値が低い砂質土」等が目安とされているが、1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)などの被害実態から、粘土分やシルト分を含む地盤であっても条件によっては液状化が発生することが知られている。
問題1 :〇 解説: かつては「砂」だけが液状化すると考えられていましたが、阪神・淡路大震災の埋立地などで、細粒分(シルトや粘土)を含む地盤でも液状化が発生しました。そのため、現在の実務では粒度試験を行い、細粒分含有率(Fc)を考慮して判定を行います。
問題2 液状化の検討において算出される「FL値(液状化に対する安全率)」は、1.0を下回ると液状化が発生すると判定されるため、構造設計の実務においては、検討対象とするすべての地震動(レベル1、レベル2等)に対して、必ずFL値を1.0以上確保するよう地盤改良等の対策を行わなければならない。
問題2 :× 解説: FL値が1.0を下回る(液状化する)からといって、必ずしも地盤改良などの対策義務があるわけではありません。 設計者の判断により、例えば「大地震時(350galなど)には液状化を許容し、杭の水平抵抗を低減して設計する」あるいは「ベタ基礎で不同沈下を防ぐ」といった工学的な対処がなされていれば、FL値が1.0未満のままでも法適合および安全性の確保は可能です。
問題3 2011年の東北地方太平洋沖地震では、液状化に伴って地盤が水平方向に大きく移動する「側方流動」による護岸や杭基礎への被害が顕著に見られたため、近年の設計においては、単なる液状化の有無だけでなく、流動による変形量や構造物への影響を考慮することが重要視されている。
解答3 :〇 解説: 新潟地震でも見られましたが、特に東日本大震災でクローズアップされたのが「側方流動」です。 液状化した地盤が傾斜や護岸の移動に伴って低い方へ流れ出す現象で、杭が地中でせん断されるなどの深刻な被害をもたらします。そのため、護岸近くや傾斜地では、FL/PL値だけでなく流動リスクの検討が必要になります。
②基礎関連
杭の耐震設計の変遷と外力の考え方
問題1 杭基礎の耐震設計に関する法的な義務付けは、上部構造の耐震設計と同時に古くから整備されており、1981年の新耐震設計法の導入時には既に、現在と同様の中地震時(一次設計)における杭の応力検討が義務化されていた。
解答1 :× 解説: 杭の耐震設計が法的に義務化されたのは比較的新しく、2000年(平成12年)の建築基準法改正からです。それまでは、1978年の宮城県沖地震などの被害を受けて指針などは出ていましたが、法的な義務ではありませんでした。上部構造に比べて歴史が浅い分野です。
問題2 杭基礎に作用する地震時の水平力を静的に評価する場合、一般的には地盤の変位による影響よりも、上部構造(建物)が揺れることによって生じる「慣性力」の影響が支配的であると考え、建物の重量と層せん断力係数に基づいた水平力を杭頭に作用させて検討を行う。
解答2 :〇 解説: 杭は地盤変位の影響も受けますが、静的設計においては建物の揺れ(慣性力)が支配的として扱います。一次設計では「1階の地震力+基礎・地中梁重量×0.1(震度0.1相当)」を水平力として用いるのが一般的です。
問題3 2019年に改定された「建築基礎構造設計指針」により、杭の大地震時に対する検討方法や地盤定数の設定等が明確化されたが、地盤の性状は不確定要素が多く、解析手法によって結果(外力や変形)に幅が出るため、設計者は状況に応じて適切な検討方法を選択し、過剰になりすぎないよう性能設計を行う姿勢が求められる。
解答3 :〇 解説: 指針で手法は整備されましたが、地盤の非線形性や減衰効果など未知の部分も多く、どの手法を選ぶかでコストが大きく変わります(1.5倍以上になることも)。盲目的に安全側を積み上げるのではなく、建物の重要度や地盤リスクを踏まえた「性能設計(バランスの良い判断)」が設計者には求められています。
その計算結果は”現実”ですか?杭の転倒検討から学ぶ、電算との正しい付き合い方
問題1 過去の大地震で見られる「建物が根元から転倒している被害」において、杭頭の鉄筋が引きちぎられて露出している光景がよく見られることから、転倒の主要な原因は、地震の強大な引張力によって建物が浮き上がり、杭が引き抜けたことにあると判断するのが一般的である。
解答1 :× 解説: 杭頭鉄筋の破断は、転倒した「結果」として見えている現象であることが多いです。 実際の転倒メカニズムの多くは、「圧縮側」の杭が過大な軸力に耐え切れず圧壊(破壊)したり、地盤が沈下したりすることで建物が傾き、重心が外れて倒れる(足払いをかけられるような)ケースです。単純に引張力で空中に持ち上げられて転倒するケースは稀です。
問題2 保有水平耐力計算(増分解析)などの静的解析において、耐震壁の脚部などに計算上非常に大きな引抜力(浮き上がり)が発生したとしても、実際の地震は向きが絶えず反転する動的なエネルギー入力であるため、計算通りの変位量で建物全体が浮き上がり続けるとは限らない。
解答2 :〇 解説: 静的解析は、一方的に力をかけ続けた場合の「つり合い」計算です。しかし、実際の地震は揺れ戻しがあるため、建物全体を持ち上げるほどのエネルギーが長時間作用し続けることは稀です。計算上の浮き上がり量は、あくまで静的な仮定に基づく「評価値」であることを理解しておく必要があります。
問題3 建物の転倒を防ぐための設計方針として、静的計算で顕著に現れる「引張側(浮き上がり側)」の杭の引抜き耐力を確保することはもちろん重要だが、物理的な崩壊メカニズムとしては、「圧縮側(押し込み側)」の杭や地盤が圧壊して建物が傾くことを防ぐことの方が、転倒防止においてはより本質的で重要である。
解答3 :〇 解説: 問題1の解説の通り、転倒のトリガー(引き金)は圧縮側の破壊であることが多いです。 引張側が浮き上がっても建物は元の位置に戻りますが、圧縮側が潰れてしまうと建物は傾き続け、自重による転倒モーメント(P-δ効果)が加速して倒壊に至ります。したがって、圧縮側の耐力を確保し、沈下を防ぐことが転倒防止の要となります。
既製杭の計算書チェックリスト|メーカー任せにしないための確認ポイント
問題1 杭の検討をメーカーに依頼する際、建物重量(支点反力)の情報として、長期荷重時の軸力と地震時の軸力を単純に合計した「最大軸力」のみを伝えれば、圧縮側・引張側ともに安全側の検討が可能であり、設計上の齟齬は生じない。
問題1 :× 解説: 単純な合計だけでなく、地震時の「変動軸力」を伝える必要があります。長期軸力が小さく変動軸力が大きい箇所では「引抜力」が発生する可能性があるため、最大圧縮力だけでは引張側の検討が漏れてしまいます。変動幅を正しく伝えることで、メーカー側も引抜対応が必要な杭を把握できます。
問題2 既製杭の引抜耐力を検討する際、その許容耐力は常に「杭体の引張強度」または「杭頭接合部の耐力」によって決まるため、杭の種類や配筋仕様を変更すれば耐力を上げることができ、地盤の周面摩擦力については安全率に含まれるため考慮しなくてよい。
解答2 :× 解説: 引抜耐力の決定要因(クリティカルな要因)は、「杭体・継手の耐力」か「地盤の引抜き抵抗力(摩擦力)」のいずれか小さい方で決まります。 地盤の摩擦力で決まっている場合は、いくら高強度の杭を使っても耐力は上がりません。杭径を太くするか、杭長を長くして摩擦面積を増やす必要があります。
問題3 杭メーカーから提出された計算書において、荷重条件が似ている箇所であっても検定比の違いにより細かく異なる杭符号が割り当てられている場合、それはコストを最小限に抑える経済的な設計であると判断できるため、施工時の管理の手間が増えたとしても、そのままの符号計画を採用するのが構造設計として最も合理的である。
解答3 :× 解説: 確かに材料コストは最小になりますが、杭種や長さが頻繁に変わる複雑な符号計画は、現場での杭の取り違え(施工ミス)や管理コストの増大を招きます。 多少の材料費増となっても、似た条件の杭は同じ符号に統合(グループ化)し、現場管理をシンプルにすることが、トータルでの品質確保と合理化につながる「良い設計」と言えます。