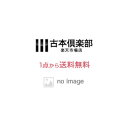【わかりやすい構造設計】鉄骨造の基本を知る~材料の特徴/計算条件とディテールの整合
【わかりやすい構造設計】鉄骨造の基本を知る~外装材(ALC・ECP・PC)の支持部材
鉄骨造を設計する際に耐火被覆については意匠設計者に任せがちになる部分ですが、耐火被覆は建築基準法や耐火認定など守らないといけないルールが多くあります。
それらを満足するためには部材サイズが決まってくることもあるため、構造設計者も基本的なことを理解しておかないと構造力学とは関係ないこところで、思わぬ部材サイズの変更を迫られることになります。
今回は構造設計者も知っておいた方がよい耐火被覆の基本について書いていきます。
①鉄骨に耐火被覆が必要な理由
鉄の基本的な性質として材料強度は高いですが、熱には弱い性質があります。
具体的には鉄骨の温度が300~500度に達すると強度が半減し、900度以上になるとさらに著しく強度が低下します。
強度が低下すると、鉄骨が変形・損傷し、最悪の場合は建物が倒壊する危険があります
建築基準法では、一定規模以上の建築物や防火・準防火地域の建物には「耐火構造」や「準耐火構造」が求められています。これを満たすために、鉄骨造には耐火被覆が必要となっています。
どのような建物が「耐火構造」や「準耐火構造」となるのかは他の方の方が詳しいので以下のサイトを参照してください。
耐火建築物の基礎知識|準耐火建築物や耐火・防火構造の違いなど基礎知識をわかりやすく解説(suumoサイトより引用)
また耐火被覆が必要となる部材はすべての部材ではありません。建築基準法で言うところの『主要構造部』になります。構造耐力上主要な部分とは異なり、耐火の観点から重要な部材に対してなので、長期荷重を負担していない耐震ブレースや水平ブレース、耐風梁のような部材には耐火被覆の対象になりません。
②耐火被覆に関する留意点
どの工法においても基本的には認定品になるので必ず認定条件をきちんと確認して、それに適合した鉄骨部材を使用するようにしましょう。
小径部材を使用する場合には要注意です。デザイン的に力を入れたい部分で力学的には工夫をして部材サイズや板厚を小さくした場合でも耐火被覆の認定条件によってサイズや板厚で決まってくる場合があります。
外壁に面する箇所においては外壁材のALCなどとセットで耐火認定となるのでその際の寸法関係を理解して柱芯と壁芯の関係をおさえるようにしましょう。特に梁側面での施工ができる寸法を確保しつつ、追加ピースが多くならない程度の持ち出しにすることがコスト面では重要な視点になってきます。
被覆にはさび止めの効果はないので設置環境に応じて適切にさび止め塗装は行いましょう。
最後に構造として大事な留意事項としては被覆厚によってスリーブの有効寸法が小さくなることです。被覆厚によってはスリーブのサイズを大きくしておく必要があります。もしくは既製品でスリーブ部分の被覆厚を薄くできるものがあるので有効に利用していきましょう。
参考:日本インシュレーション株式会社 鉄骨はり貫通部耐火被覆材 -すりーぶたすけ
③耐火被覆の工法種別
耐火被覆の種類は大きく分けて5種類の工法について簡単に説明していきます。
吹付け工法
ロックウールやセメントなどを混合し、鉄骨に直接吹き付けて固める工法です。耐火被覆の中では最も安価だと思われる工法です。細かい部分にも継ぎ目なく施工がしやすいです。
安価なこともあり仕上がりの美観性はあまり良くないため、室内で見える箇所にはあまり使用せず、天井や柱を石膏ボード等で囲って隠す場所に使用します。
コスト優先の半屋外の駐車場では見える箇所でも使用していることがよくあります。
成型板(成形板)工法
日常のやり取りの中ではボードと言っていることが多いと思います。材料としては繊維入りけい酸カルシウム板などでできた耐火被覆板を鉄骨に貼り付ける工法になります。表面が硬くフラットで、そのまま仕上げ下地としても使えます。工場製品なので品質が安定し、施工も容易です。
巻き付け工法
高耐熱ロックウールや不織布などを鉄骨に巻き付け、ピンで固定する工法です。製品名としてよく耳にするのはマキベイだと思います。粉じんがほとんど発生せず、軽量で施工性が高い工法になります。
参考:マキベイ
参考:ロックウール工業協会 巻付け耐火被覆材
耐火塗料工法
意匠性に特化した工法で耐火塗料を直接塗布する工法になります。これまで説明してきた工法に比べて意匠性が高く、鉄骨を露出させるデザインにも対応可能になりますがコストは高めになります。
貼付け工法
耐火塗料よりもさらに意匠性に特化した被覆厚が非常に薄く、平滑に仕上がるシートを貼付ける工法になります。コストとしては他の工法に比べて高めにはなるので意匠性にこだわる箇所に絞って使用することが多いと思います。
まとめ:耐火被覆は「仕上げ」ではなく「構造計画の一部」
今回の記事では、構造設計者が意外と見落としがちな「耐火被覆」の重要性と基礎知識について解説しました。 「耐火被覆は意匠の範疇」と割り切ってしまうと、後から認定条件によるサイズアップや納まりの不整合で大きな手戻りが発生するリスクがあります。重要なポイントを振り返ります。
- 認定条件の縛り: 力学的にOKでも、耐火認定上の「最小断面・最小板厚」によって部材サイズが決まることがあるため、特に小径部材の使用には注意が必要です。
- 納まりへの影響: 被覆厚によってスリーブの有効径が小さくなる点や、外壁(ALC等)との取り合い寸法を考慮した部材配置が不可欠です。
- 工法の適材適所: コスト重視の「吹付け」から意匠重視の「塗料・シート」まで、それぞれの特徴を理解し、場所に応じた使い分けを意識しましょう。
構造設計者も耐火被覆の特性を理解し、初期段階から意匠設計者と「どの工法で、どのくらいの被覆厚を見込むか」をすり合わせておくことが、合理的で手戻りのない鉄骨造設計を実現する鍵となります。

【理解度チェック】知識を定着させる〇×クイズ
この記事の重要ポイント、しっかり理解できましたか?3つの〇×クイズで腕試ししてみましょう!
問題1 鉄骨造の建物において、法的に「耐火構造」が求められる場合、柱や梁といった主要構造部に限らず、長期荷重を負担しない水平ブレースや耐風梁などを含めた「全ての鉄骨部材」に対して、例外なく耐火被覆を行わなければならない。
解答1:× 解説: 耐火被覆が必須となるのは、建築基準法上の「主要構造部」に該当する部材です。記事にもある通り、長期荷重(床の重さなど)を負担しない部材、例えば地震力のみを負担するブレースや、風圧力のみを受ける耐風梁などは、耐火被覆の対象外となる場合があります。不要な部分にまで被覆を行うとコスト増になるため、区別が必要です。
問題2 意匠的な理由等で小径の柱や薄い板厚の部材を使用したい場合、構造計算によって安全性が確認できていれば自由に採用して良いが、耐火被覆の工法によっては「認定条件(最小断面積や最小板厚)」が存在し、構造計算とは別の理由で部材サイズをアップさせなければならないケースがある。
解答2:〇 解説: 耐火被覆材は、国土交通大臣の認定を受けた工法ごとに「適用範囲」が定められています。その中には、熱容量を確保するための「最小断面寸法」や「鋼材の最小板厚」が条件となっていることが多くあります。力学的にOKでも、この認定条件を満たすためにサイズアップが必要になることは実務でよくある落とし穴です。
問題3 梁に設備配管を通すためのスリーブ(貫通孔)を設ける際、耐火被覆を施工するとその厚みの分だけ「実際に配管を通せる有効寸法」が小さくなってしまうため、構造設計者はあらかじめ被覆厚を見込んでスリーブ径を大きく設定するか、スリーブ部分の被覆を薄くできる認定品を選定する等の配慮が必要である。
解答3:〇 解説: 例えば、梁のウェブにφ150のスリーブを開けたとしても、そこに厚さ25mm等の耐火被覆を巻き込むと、実際の穴径はもっと小さくなってしまいます。この被覆厚による減少分を考慮せずにギリギリの設計をすると、現場で「配管が入らない」というトラブルに直結するため、事前の調整が不可欠です。