 【モデル化】
【モデル化】 【わかりやすい構造設計】一貫計算設定の考え方~「非剛床」設定の基本と3つの留意点
一貫計算設定の応力計算条件の中に非剛床に関する設定があります。部材の応力や変形量が大きく変わり、時には建物の安全性を左右することもあります。非剛床の設定はよく使用する設定でもあるので、十分に理解しておく必要があります。今回の記事では非剛床の...
 【モデル化】
【モデル化】  【モデル化】
【モデル化】  【モデル化】
【モデル化】  【モデル化】
【モデル化】  【モデル化】
【モデル化】  【まとめ】
【まとめ】  【モデル化】
【モデル化】 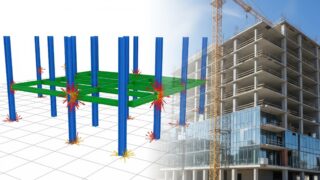 【モデル化】
【モデル化】 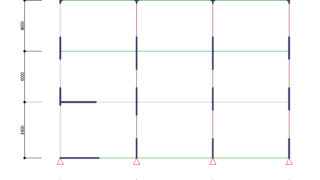 【モデル化】
【モデル化】 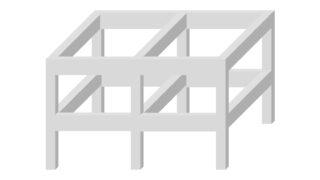 【モデル化】
【モデル化】