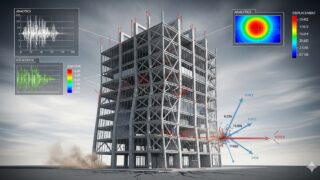 【保有水平耐力計算】
【保有水平耐力計算】 【わかりやすい構造設計】変形をどう評価する?① なぜ変形が重要か、3つの評価方法を知ろう
建物の地震時の被害や、その後の継続利用の可能性を考えるうえで、建物がどの程度変形するのか(特に層間変形角)を評価することは、耐力を評価することと同じくらい、あるいはそれ以上に重要です。大きな耐力を持つ頑丈な建物でも、変形が大きすぎれば内外装...
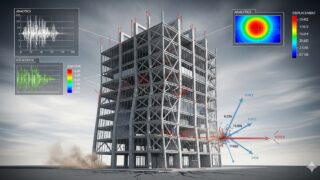 【保有水平耐力計算】
【保有水平耐力計算】  【まとめ】
【まとめ】  【構造設計】
【構造設計】 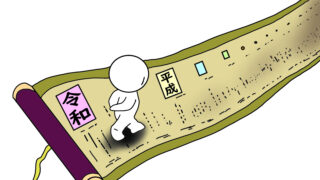 【構造設計】
【構造設計】  【構造設計】
【構造設計】  【モデル化】
【モデル化】  【モデル化】
【モデル化】  【地盤・基礎構造】
【地盤・基礎構造】  【RC造】
【RC造】