 【S造】
【S造】 【わかりやすい構造設計】二次部材設計の留意点~見落としがちな鉄骨二次部材の荷重とモジュールの考え方
これまでの記事で二次部材の検討での全体概要と、具体的な検討にあたっての荷重表の作り方、RC部材について解説してきました。▼ これまでの記事二次部材設計の留意点二次部材設計の留意点~すべての基本「荷重表」と力の流れの始点「RCスラブ」編今回の...
 【S造】
【S造】 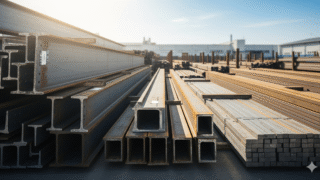 【S造】
【S造】  【RC造】
【RC造】  【S造】
【S造】 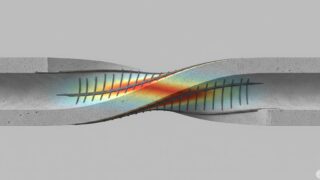 【RC造】
【RC造】  【S造】
【S造】  【S造】
【S造】  【S造】
【S造】  【S造】
【S造】  【S造】
【S造】