設備に関する内容として以下のような記事を書いてきました。
・機械設備図のチェックの視点
・電気設備図のチェックの視点
図面の内容に限らず設備の耐震性について、人命や建物を守るといった観点では分野が別だからといって関与しないということにはなりません。
今回は簡単にですが、建築設備の設計用地震力と建築物への地震力の関係と安全率の考え方について書いていきます。
①建築設備の設計用地震力
まず建築設備を設計する際に指針とすることが多いのは、『建築設備耐震設計・施工指針』(日本建築センター)だと思います。今回の記事はこの指針に沿っての考え方になります。
この指針の中では地階および1階に設置するものに対しては設計用の水平震度は0.4以上としています。この0.4が何を想定しているのかを見ていきたいと思います。
水平震度0.4は建築物の大地震時(二次設計)の入力地震動に相当との考え方からきています。実際の入力地震動が400~500cm/s2となっているのかという部分には追求の余地が残っていますが、この想定と整合する形で建築設備の設計用地震力は設定されています。
まずここで認識しておく必要があることは、建築物のように中地震時と大地震時という考え方で区分しているのではなく、大地震時を想定しているということです。
②クライテリアの考え方
地階および1階については地面からの入力地震動と同等の設定でした。それに対応して上層階・屋上・塔屋については、揺れが増幅されることから水平震度として1.0として設定されています。これは地上と比べて頂部では2~3倍の増幅があるという考え方になります。
中間階についてはその間を取った形の1.5倍の増幅として水平震度0.6になります。これらの水平震度の違いはあくまでも設置階による違いになります。
これまで示してきた値はグレードとしては1番低い耐震クラスBの値にあります。その上には耐震クラスA(上層階:1.5、中間階:1.0、1階:0.6)、耐震クラスS(上層階:2.0、中間階:1.5、1階:1.0)があってそれぞれの水平震度は前述のようになります。
ここでのポイントは設置階による増幅とグレードによる割り増しは別々に設定されているという構造を把握しておくことになります。
上層階に設置されていると揺れやすいから耐震グレードSにするという考え方にはならないと言うことです。
③指針にはない構造設計者として留意すること
ここまでの内容については『建築設備耐震設計・施工指針』(日本建築センター)の内容にちょっと解説を加えただけなので、原本を読んでもらえればそれに沿った検討自体はできてしまうと思いますが、検討時の判断をする際に考えてもらいたいことを書いていきます。
まずは、検討時の材料強度に関する考え方です。指針の中では検討時は許容応力度設計をしています。これは構造設計をしている人からすると大地震時なのだから終局耐力に対して検討を行ってもよいのでは?と思うかもしれません。
設備設計者が取り組みやすいように許容応力度設計が用いられているとも言われていますが、個人的には建築物と違って不静定次数の少ない設備支持のアンカーなどに対しては許容応力度で設計するくらいの安全率が必要だと考えています。短期許容応力度を超えるということはそれだけ変形するということでもあります。
不静定次数の少ない構造での変形というのは不安定構造に直結するので必ず避けるべきことになります。
また、設計用水平震度についても許容応力度設計と同様に設備設計者が取り組みやすいようにかなり簡略化された設定になっています。中間階の設定範囲(上層階と1階以外)にも幅があったり、建物全体の階数の考え方についてもざっくりとしたものになっています。
指針で定義された数値は必ずそれを使えというものではありません。それ以上の数値を構造設計者が設定することは問題ありません。時刻歴応答解析をしているのであればその結果の加速度や、Ai分布を見るなどして適切な水平震度を考えるなどの配慮をするようにしましょう。
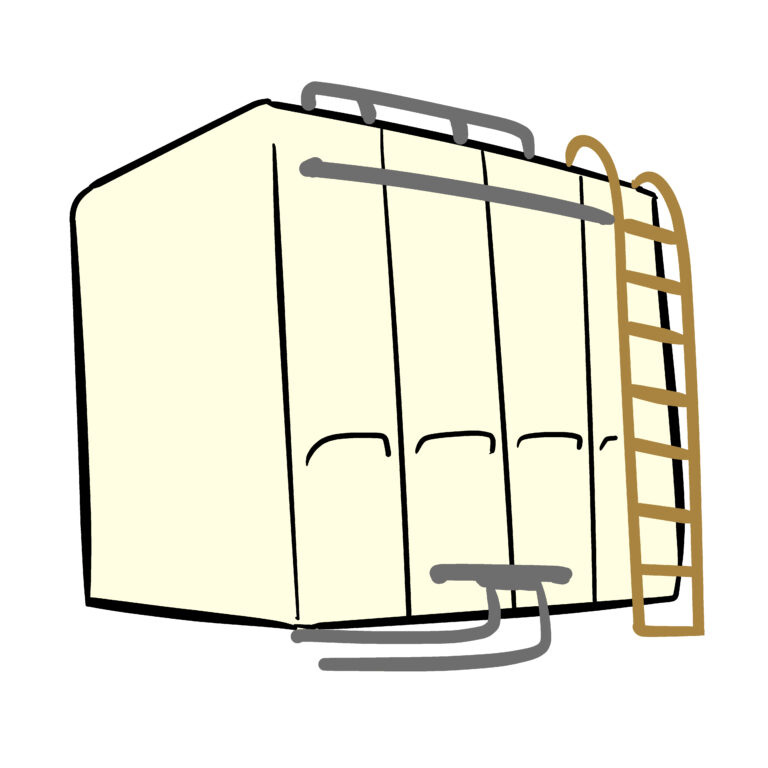



コメント