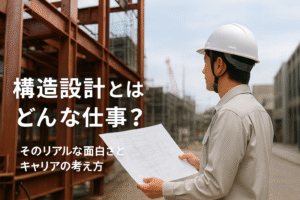構造設計は、目に見えない自然の力と対峙し、人々の安全な暮らしと未来の建築を創造する、ダイナミックで知的な非常にやりがいのある仕事です。
専門的でやりがいのある仕事への期待と共に、その奥深さや責任の大きさを感じているかもしれません。あるいは、若手技術者として日々の業務に向き合う中で、次々と現れる課題に「もっとうまくやりたいのに」と歯がゆさを感じているかもしれません。
終わらない計算、迫りくる納期。目の前のタスクをこなすだけで精一杯になり、自分がただの「計算屋」のように感じてしまう。その経験は、多くの先輩技術者が乗り越えてきた壁です。
しかし、その壁は、次のステージへと導くための、成長のチャンスです!
仕事への向き合い方、物事の捉え方を少し変えるだけで、景色は一変します。
- バラバラに見えていた課題が、実は一つの本質で繋がっていることに気づく。
- 計算結果の「OK」「NG」に振り回されずに、本当の意味を深く追求したくなる。
- 「無理だ」と諦める前に、「どうすれば実現できるか?」と知恵を絞ることに夢中になる。
こうした視点を持つことで、仕事は受け身でこなす「作業」から、自ら未知に挑む「知的探求」へと変わっていきます。
また、彼らを指導し、導く立場にある方々にとっても、人材育成のヒントとなる視点を盛り込んでいます。
- 強固な「思考の土台」:多くの課題の”本質”を見抜き、悩みを成長の糧に変える考え方。
- 差がつく「実践スキル」:仕事の段取り、質問力、調べる力を飛躍的に向上させる具体的なテクニック。
- 「計算屋」で終わらないための「専門性の深化」:計算プログラムを使いこなし、自らの意志で”決断”できる構造設計者になるための心構え。
今回の記事ではこれらを小手先のテクニックととらえるのではなく、構造設計者として、これからの設計者人生を自らの手で切り拓くための「思考の軸」になる内容を解説していきます。
①すべての「なぜ?」を武器にする – 成長を止めない思考の土台
仕事が思うように進まない。たくさんの課題を抱え、何から手をつけていいかわからない。そんな袋小路にはまっているなら、まずは物事を捉えるための「思考の土台」を築き、固める必要があります。
1-1. すべてを「繋げて」考える – 課題の本質を見抜く力
仕事が上手くいかないとき、人は「できていないこと」ばかりに目が行きがちです。「あれも指摘された、これも直さなきゃ…」と、課題が山積みに見えてしまいます。しかし、一歩引いて見てみると、一見バラバラに見える複数の課題が、実はたった一つの”本質的な壁”に起因していることが少なくありません。
例えば、「Aの案件で指摘されたこと」と「Bの案件で注意されたこと」。事象は違えど、その根底には「成果イメージの共有不足」や「根拠の確認不足」といった、共通の原因が潜んでいるのです。
この「本質は繋がっている」という視点を持つと、仕事の進め方が劇的に変わります。
- 課題が一気に減る:10個の課題だと思っていたものが、実は1つの根本課題の表れだと気づけば、取り組むべきは1つになります。
- 成長が加速する:1つの本質的な課題を克服すれば、複数の業務で同時に成果が上がります。一石二鳥ならぬ、一石十鳥の効果です。
では、どうすればこの思考を身につけられるのか?その第一歩が「すべてを理解してみようとする」という意識です。
新しいことに取り組むとき、「初めてだから、わからなくても仕方ない」と無意識にブレーキをかけていませんか?その思考の起点を「すべてを理解するには、どうすればいいか?」に変えてみます。
もちろん、本当にすべてを一度に理解することは不可能です。しかし、この意識を持つだけで、「なぜ?」「どうして?」という疑問が次々と湧き上がり、表層的な理解から一歩踏み込めるようになります。都合のいい部分だけを拾い読みするのではなく、自分が理解できていない範囲を自覚できるようになる。これが、本質を見抜く思考が始まります。
参考:仕事の壁を乗り越える思考法|複数の課題に共通する「本質」の見つけ方
1-2. 「わからない」を最強の武器に変える
「わからないことが、わからないんです…」
新人時代、誰もが一度は経験するこの状態。しかし、これは決して恥ずかしいことではありません。むしろ、「何がわからないか、わかる」状態になることこそ、エンジニアとして成長するためには不可欠なことです。わかったつもりになってしまうことが、未知な自然を相手にする構造設計者に取っては致命的です。
「わからないことがわからない」状態に陥る最大の原因は、言葉の定義が曖昧なまま物事を捉えていることにあります。
「この柱、強いですか?」「この建物、壊れますか?」
一見、普通の会話ですが、思考が浅い典型例です。「強い」とは、剛性のことか?耐力のことか?「壊れる」とは、曲げ破壊か?せん断破壊か?許容応力度を超えた状態か?
このように、曖昧な言葉を使っている限り、思考は具体化されず、疑問点も生まれません。最初の頃は相手が状況を汲んでくれるので伝わってしまいます。
そして、そういった状況に慣れてしまうと「理解している」と勘違いしてしまいます。
この状態から脱却する鍵は、「自分なりの定義を持つこと」です。
参考書に書いてある言葉を、自分なりに「こういうことだろう」と定義してみる。そして、その定義と目の前の事象を照らし合わせます。
- 自分の定義:「柱の剛性は、部材の長さが短いほど高くなるはずだ」
- 目の前の事象:「あれ、この計算結果だと、短い柱に応力が集中しすぎている…なぜだ?」
このように、自分なりの定義(仮説)と現実の間に「ズレ」や「違和感」が生まれたとき、初めて質の高い「疑問」が生まれます。これが「何がわからないか、わかった」瞬間です。
最初のうちはこの自分なりの定義は間違っていてもよいというのが重要な点です。初めから正しい定義をしようと思うと、自分で考えて仮説を立てることよりも、正しい答えを教えてもらう受け身の思考になってしまいます。
最初は間違っていても照らし合わせているうちに正解に近づいていきます。この過程を積み重ねていくことが何よりも大切です。
【育成のヒント】
部下から質問がないとき、それは「全て理解している」サインではありません。「何がわからないかわからない」状態に陥っている可能性があります。すぐに答えを教えるのではなく、「〇〇について、どう定義する(どう捉えている)?」と問いかけ、言語化を手助けすることで、思考の解像度を上げることができます。
1-3. 「わかったつもり」が最大の敵 – 未知と謙虚に向き合う
少し経験を積んでくると、「この仕事はもう慣れた」「大体わかっている」という気持ちが芽生えてきます。しかし、これこそが成長を止める最大の敵、「わかったつもり」という過信です。
構造設計は、未知の自然外力を相手にする世界です。絶対的な正解は存在しません。どんなに計算プログラムが進化しても、それはある仮定に基づいたシミュレーションに過ぎず、自然の前では常に謙虚でいなければなりません。
未知の課題を前にしたとき、私たちの心にはいくつかの「逃げ」が生まれます。
- 過信:「どうせいつもと同じだろう」と高を括る。
- 保身:「忙しいから、面倒なことは避けたい」と見て見ぬふりをする。
- 恐怖:「失敗するのが怖い」と挑戦を避ける。
こうした気持ちは、成長の機会を自ら手放す行為に他なりません。
大切なのは、常に「無能の自覚」を持つことです。自分がどれだけ経験を積んでも、知らないこと、わからないことは無限に存在します。自分の評価は周りが決めるものであり、「自分は役に立っている」と思った瞬間から、役に立たなくなっていきます。
この謙虚さを持ち、他の人ならどう考えるだろう?と視野を広げることで、今まで見えていなかった未知の課題に気づけるようになります。そして、その課題に自ら挑戦していくことでしか、本当の意味で成長できません。
誰かに言われたからやるのではなく、自ら課題を発見し、主体的に取り組む。その方が苦労は増えるかもしれませんが、得られる充実感や達成感は比較になりません。何より、そのプロセス自体が知的探求として非常に面白いのです。
参考:計算の「わかったつもり」から脱却/成長の壁を壊す”言語化”の思考法
参考:構造設計者(エンジニア)は未知課題に謙虚に向き合うことが不可欠
参考:建築構造設計の世界を知る~自然の未知をどう掴むか
【第1章まとめ】
✅ 課題は繋がっている。本質を見抜けば、悩みは激減する。
✅ 「わからない」を放置せず、自分なりの定義を持って疑問を生み出そう。
✅ 「わかったつもり」は成長の敵。常に謙虚に、未知の課題に挑戦し続けよう。
②信頼を築く実践スキル – 段取り・質問・調査の解像度を上げる
思考の土台が固まったら、次は実践的な能力を磨いていきましょう。ここでは、若手時代に必ずぶつかる「段取り」「質問」「調査」の3つの壁を乗り越え、周囲と差をつけるための実践術を解説します。
2-1.【段取り力】
「若手のうちは、段取りが仕事の8割」と言っても過言ではありません。成果を出す人は例外なく段取りが上手く、そうでない人はいつまでも時間に追われ、長時間労働なのに成果が出ません。段取りとは、単なる作業リストを作ることではありません。「限られた時間で最高の結果を出すための戦略」そのものです。
① まずは「成果イメージ」を固める
時間がないと、すぐに作業に取り掛かりたくなりますが、それが破綻への第一歩。段取りの起点は、常に「最終的な成果イメージを明確にすること」です。
② 「やらないこと」を決める
近年の業務は複雑化し、情報も過多。段取り上手な人は、「やるべきこと」よりも「やらなくてもよいこと」の抽出に長けています。
③ 期間から逆算して「やり方」を考える
仕事が遅い人は、「自分のやり方でやったら、どれくらい時間がかかるか」を起点に考えます。成果を出す人は、「決まった期間でやりきるには、どう取り組めば良いか」を先に考えます。
④ 段取りに「根拠」を持つ
なぜその作業をそのタイミングでやるのか?全てのタスクに明確な根拠を持ちましょう。特に、周囲に影響のある作業を最優先する配慮ができる人は、絶大な信頼を得ます。
⑤ 毎日「塗り替える」
どんなに完璧な段取りを組んでも、想定外の事態は必ず起こります。1日の始めと終わりには必ず課題を再整理し、状況に合わせて段取りを柔軟に「塗り替えて」いきましょう。
【育成のヒント】
若手に仕事を任せるとき、完璧な段取りをこちらで組んで渡すのは逆効果です。まずは本人に段取りを考えさせ、実践してもらいましょう。ここでの失敗は失敗ではなく成功のための過程として捉えましょう。その上で「なぜこの順番なの?」「ここのリスクは考えた?」と問いかけ、改善点を本人に気づかせることが、信頼される人材を育てるには必須の経験です。
参考:デキる人が実践する段取り|周囲から信頼される仕事の進め方
2-2.【質問力】
質問をしないリスクは、質問をするリスクより遥かに大きいです。間違った方向に進んでからでは、手戻りが増え、周りにも迷惑をかけます。
① 質問は「仮説」を持ってぶつける
最悪な質問は、「わかりません。教えてください」という丸投げです。成長に繋がる質問は、必ず「自分なりの仮説とその根拠」をセットにします。「〇〇という理由で、私は△△だと考えたのですが、この認識で合っていますか?」
② 相手の答えを「予測」する
質問をする前に、「相手はどんな答えを返しそうか?」を予測する習慣をつけましょう。この一手間が、質問の質を劇的に高めます。そうすることで相手が答えられる情報を提供できているのか、質問する相手としてふさわしいのかを事前に気づくことができます。
③ 質問で信頼を得て「仲間」を増やす
高度な専門分野になればなるほど、自分一人で解決できることは少なくなります。的を得た質問は、相手に「信頼」を生み、協力者を増やす力があります。
【育成のヒント】
部下が質問に来たときは、成長のチャンスです。答えだけを求める丸投げ質問であれば、「あなたはどう思う?」と差し戻しましょう。仮説を持ってきたなら、その思考プロセスを褒め、さらに深い視点を与える。質問しやすい雰囲気を作りつつ、質問の質を要求することが、チーム全体のレベルアップに繋がります。
参考:評価される「質問力」の鍛え方|成長と信頼を勝ち取る3つのステップ
参考:思考が深い人と浅い人の違いは?思考を深める3つのポイント
2-3.【調べる力】
どんな仕事でも「調べる」という行為は不可欠です。特に、基準や指針が多岐にわたる構造設計では、この能力が成果に直結します。
① 「仮説」を持って調べる
建築設計を行うための情報というのは非常に膨大に存在します。しかも、建築設計は答えが1つではないのでテスト勉強のように1つの答えを探すような意識で、闇雲に情報を探しても、情報の海に溺れるだけです。「〇〇は△△である、という仮説を検証するために調べる」という意識を持ちましょう。ここでも自分なりの定義や正しい言葉の理解が活きてきます。
② 「根拠」をおさえる
誰かに聞いた話やネットの不確かな情報は、根拠になりません。必ず、建築基準法や学会規準といった一次情報に立ち戻り、自分の目で確認する習慣をつけましょう。「法規の第〇条にこう書いてあります」と言える人は、圧倒的に信頼されます。
③ 「暗記」をやめ、「立ち戻れる仕組み」を作る
膨大な情報をすべて暗記するのは不可能です。そこに力を注ぐのはもったいないです。
重要なのは、「どこに何が書いてあるか」を把握し、いつでも立ち戻れるようにしておくことです。時々立ち止まって、ぜひ「学びなおし」をしてください。わかったつもりでいた知識が、より深く理解できるはずです。
いつの間にか自分なりの解釈が混じって事実から少しずれていることに気づいたり、知識が増えた状態で見ると見え方もかわってきて新しい気づきが得られます。
【育成のヒント】
部下が壁にぶつかったとき、安易に答えを教えるのは成長の機会を奪います。「どの基準のどこを見ればヒントがありそう?」「似たような事例は、どうやって探す?」など、答えそのものではなく「調べ方」や「情報のありか」を教えること。これが、自ら答えにたどり着ける人材を育てるための、指導者の重要な役割です。
参考:デキる人は「仮説」から調べる/成長を加速させる調べる技術
参考:設計根拠のおさえ方/学びなおしのススメ
参考:生産性が劇的に向上!「考えているフリ」から脱却し成果を出す思考習慣
【第2章まとめ】
✅ 段取りは未来を描く戦略。成果イメージから逆算し、「やらないこと」を決める。
✅ 質問は仮説を持ってぶつけろ。相手を予測し、質問を仲間作りのきっかけにする。
✅ 調べる力は自走のエンジン。仮説を持って根拠をおさえ、立ち戻れる仕組みを作る。
③自らの意志で建築を創造する
思考の土台を固め、実践スキルを磨いた先に、単なる「計算屋」で終わらず、自らの意志で建築を創造する「構造設計者」になるための道が拓けます。ここからは、より専門的な領域に踏み込んでいきます。
3-1. 電算に使われるな、使いこなせ -「判断」と「決断」の違い
現代の構造設計は、一貫計算プログラム(電算)なしには成り立ちません。しかし、この便利なツールは、使い方を間違えると設計者の思考を停止させるツールにもなり得ます。
よくある過ちは、電算が出した「OK/NG」という結果だけで一喜一憂してしまうこと。これは、電算に思考を支配されている「使われている」状態です。
電算に使われないためには、「判断」と「決断」を明確に区別する必要があります。
- 判断:情報を十分に検討し、客観的な事実や数値を導き出すこと。(電算の役割)
- 決断:判断の結果を踏まえ、どの道を選ぶか、自らの意志で決めること。(設計者の役割)
その結果を受けて、どうするか。最終的な「決断」をするのは、設計者自身です。電算に「決断」をさせてはいけません。決断に自信が持てないなら、それは「判断」の材料が不足している証拠。腹を括って「決断」する。この繰り返しが、主体的な設計者を育てます。
【育成のヒント】
部下の計算結果をレビューする際、「このOK/NGの根拠は?」だけでなく、「この結果を受けて、設計者としてどう決断する?」と問いかけることが重要です。電算の判断と、設計者の決断は違うということを明確に伝え、当事者意識と責任感を育てることが不可欠です。
参考:直感が置き去りにならない一貫計算との付き合い方
参考:計算プログラムに使われない付き合い方
参考:判断と決断を分ける技術~仮説思考で“判断”の質を上げる
3-2. 耐震設計の本質 – 「耐力」と「硬さ」のバランスをデザインする
大地震に対して建物がどう振る舞うか、自分の言葉で説明できるでしょうか?
建築基準法では、大地震時には、ある程度の損傷を許容しているのが基本です。地震のエネルギーに対抗する方法は、力で受け止める「強度型」と、変形で対応する「靭性(じんせい)型」に大別されます。
この「耐力」と「硬さ(剛性)」の最適なバランスはどこかを常に考える。これが、人命だけでなく、財産や生活を守る設計の基本概念です。
3-3. 安全性をデザインする – 「幅」と「塩梅」を掴む
構造設計は、絶対的な正解がない世界です。だからこそ、「完璧な正解」を求めるのではなく、「安全性の幅」をデザインしていくという発想が重要になります。
① 両極端を把握する
まずは、最も安全側と厳しい条件の両極端で略算し、検討すべき「幅」を見定めます。
② 塩梅(あんばい)を把握する
式の成り立ちや検討の趣旨を理解することで、「どこに、どのくらいの余力(安全率)を持たせるべきか」という勘所、すなわち「塩梅」がわかってきます。ありがちな失敗は、あらゆる項目で安全率を上乗せし、過剰設計になること。余力は、「荷重」など、一つの項目に集約して管理するのが合理的です。
参考:幅を持って安全性をデザインしていく
参考:異常気象・地震に備える「フェイルセーフ」という考え方
参考:余裕を持たせすぎ?余力を最適化するシンプルな考え方
3-4. 構造設計者は「通訳者」であれ
専門性が高いからこそ、構造設計者は「通訳者」になる必要があります。関係者、自然、工学、そして建築の形を繋ぐ架け橋となるのです。
- 豊富な言語力で「翻訳」する:専門用語を、相手にわかる平易な言葉で伝える力。
- 具体的な「数値」で議論を進める:「大きくなります」ではなく、「柱が100mm大きくなります」と具体的に示す。
- 「譲れない部分」を伝える信念:安全性に関わる部分は、絶対に譲らない。その信念が信頼を築きます。
計算力だけでなく、この「伝える力」を磨くこと。構造設計者に限らずみんなと分かり合うことで初めて成果になったと言えます。
【育成のヒント】
部下の説明が要領を得ないとき、能力不足と断じる前に、言語化の訓練をさせましょう。「今の説明を、建築を知らない人に伝わるように言い換えてみて」「その『なんとなく』を、具体的な数字で表現すると?」といった問いかけが、部下の「通訳者」としての能力を引き上げます。
参考:構造設計者は自然・工学・形を繋ぐ通訳者
参考:「自分で考えたか?」思考の言語化で仕事は劇的に変わる
【第3章まとめ】
✅ 電算の「判断」に頼らず、自らの意志で「決断」する。
✅ 耐力と剛性の最適なバランスを探り、建築の安全性をデザインする。
✅ 専門知識の「通訳者」となり、数値で語り、譲れない信念を伝える。
おわりに
この記事で解説した内容は、突き詰めれば非常にシンプルです。しかし、実践すれば確実に成果に繋がり、設計が楽しくなります。
構造設計は、決して楽な仕事ではありません。しかし、自らの思考と技術で、目に見えない力と対峙し、人々の安全と生活を支える空間を創造する、非常にダイナミックでやりがいのある仕事です。
ここで学んだことを、明日からの仕事や学業、就職活動の中で一つでも実践してみてください。とにかくまずは実践です。実践が早い人は必ず成長します。
- 課題にぶつかったら、「本質は何か?」と考えてみる。
- 質問する前に、「自分なりの仮説」を立ててみる。
- 電算の結果を前に、「で、自分はどう決断する?」と問いかけてみる。
その小さな一歩の積み重ねが、5年後、10年後のあなたを、誰からも頼られる構造設計者へと成長させていくはずです。
ロードマップ関連記事
- 【構造設計ロードマップ①】1年目が最速で成長するための必須スキル3選
- 【構造設計ロードマップ②】「わかったつもり」を脱却し、設計力を伸ばす3つのステップ
- 【構造設計ロードマップ③】中堅エンジニアへの道|専門性を深め、チームを動かす思考法
- 【構造設計コラム】構造設計の「しんどさ」は「完璧主義」のせい? やりがいを見出すための思考法